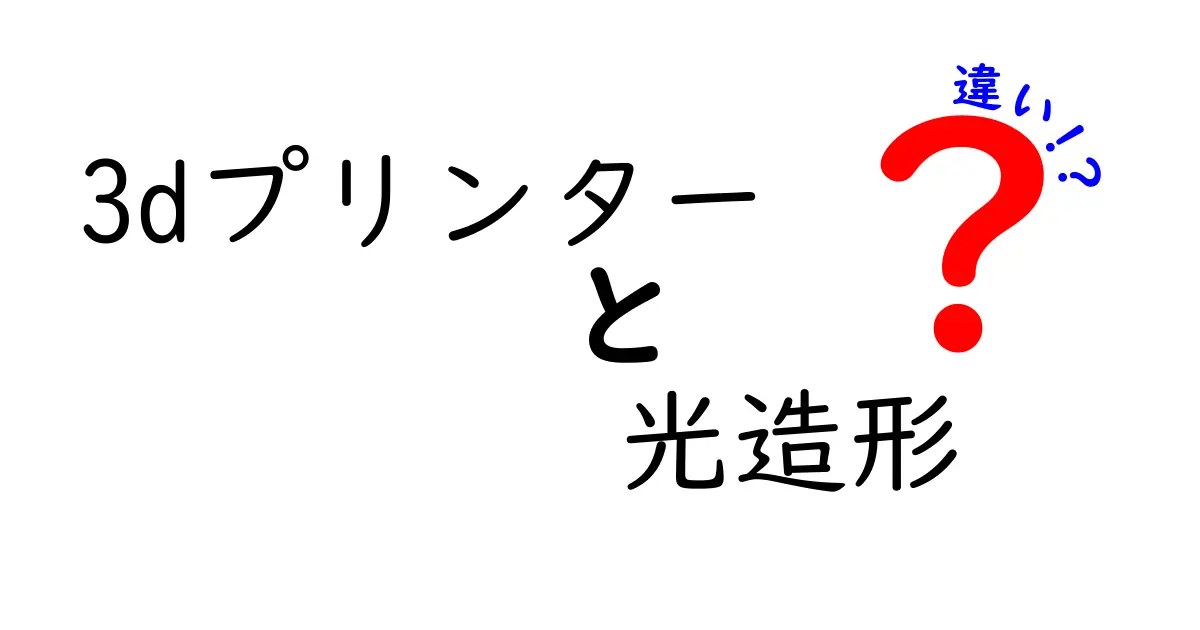

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
光造形とFDMの違いを理解する総合ガイド
このガイドでは、光造形と呼ばれる3Dプリンターの技術と、従来のFDM方式の違いを、中学生にもわかる言葉で丁寧に解説します。
光造形は樹脂を光で硬化させて形を作る方法で、細かな表面仕上げや複雑な形状の再現に強みがあります。
一方のFDMは糸状の材料を積み上げて作る方式で、部品を大きく安く作るのが得意です。
両者にはそれぞれ得意分野と限界があり、使い方次第で作品の仕上がりが大きく変わります。この記事を読むと、どんな用途にどちらを選ぶべきかが見えてきます。
光造形とは何か
光造形は液体状の樹脂を光で硬化させて形を作る3Dプリンターの一種です。DLPやレーザービームを使って樹脂を一層ずつ固め、細かい凹凸や滑らかな曲線を再現します。
仕上がりの精密さは非常に高く、表面が滑らかで組み立てが必要な部品にも向いています。
作業の流れは、まずデジタルデータをスライスして薄い層に分解します。次にプリンターのビルドプレートを移動させ、光を当てて樹脂を硬化させます。これを繰り返して1つの立体が完成します。
完成後には樹脂の残留物を洗浄する工程と、硬化を完了させる追加の照射が必要です。このプロセスの強みは高精度と滑らかな表面仕上げ、難しい形状でも再現しやすい点です。欠点としては樹脂のコスト、プリント後の処理時間の長さ、臭いが発生する点などが挙げられます。
FDMとの違いと適した用途
FDMは熱で溶かしたフィラメントをノズルから押し出して積み上げる方式です。材料の多様性は光造形より少ないですが、部品としての強度を出しやすく、耐熱性のある樹脂やABSなどが使われます。印刷速度は大きな部品を作るときに有利で、最初の費用も低めで手軽に始められます。対して光造形はレーザーや光源で樹脂を固めるため、非常に高い解像度と表面の滑らかさを得られますが、材料コストが高く、ビルドサイズは比較的小さめです。実際の活用としては、プロトタイプの試作、宝飾品や歯科技工、模型の精密部品など、細部の再現性を求める場面に向いています。価格面では初期投資はやや高く、樹脂の補充や洗浄液の処理といった運用コストも考慮が必要です。
光造形を選ぶときのポイントとコツ
光造形を選ぶ際のポイントは、ビルドサイズ、解像度、樹脂のコストと入手のしやすさ、そして後処理の労力です。ビルドサイズが大きいと部品全体を一度に作れるメリットがありますが、同時に樹脂の消耗も増えます。解像度は層の厚さに直結しますので、細かいディテールが求められる場合は薄い層を設定します。
ただし薄い層はプリント時間が長くなる点に注意です。後処理では、洗浄、湿式撹拌、そして硬化のためのUV照射が必要です。乾燥や保管にも注意が必要で、樹脂は日光や高温で劣化しやすいので、専用の保管容器を使いましょう。
初心者には安価な機種から始め、徐々に樹脂の種類や光源の違いを学ぶと良いです。
実践的な活用例と表での比較
実際の活用としては、教育用のモデル、細かな歯科技工のミニチュア、機能部品の試作、ジュエリーの原型など、滑らかな表面と細部の再現性が活かせる場面が多いです。以下の表は代表的な特徴を比較したもの。
この表を見れば、どの目的でどちらを使うべきかが一目で分かります。総括として、手頃に大きな部品を素早く作りたいならFDM、精密で滑らかな表面が必要な部品には光造形が適しています。
光造形の小ネタ話。友だちと雑談していて気づいたのは、光造形を深掘りするとき、ただ『すごい』とか『早い』だけでは選べないという点だよ。材料費の現実、後処理の時間、臭いの影響、そして環境への配慮など、実際の使い心地を知ることが大切。だからこそ、まずは自分が作りたい物のサイズと精度をはっきりさせてから選ぶのがコツ。光造形は小さくて細かな部品に強いけれど、長時間の作業や洗浄作業も伴うことを覚えておこう。
次の記事: 粘土と紙粘土の違いを徹底解説!中学生にも分かる選び方と使い方 »





















