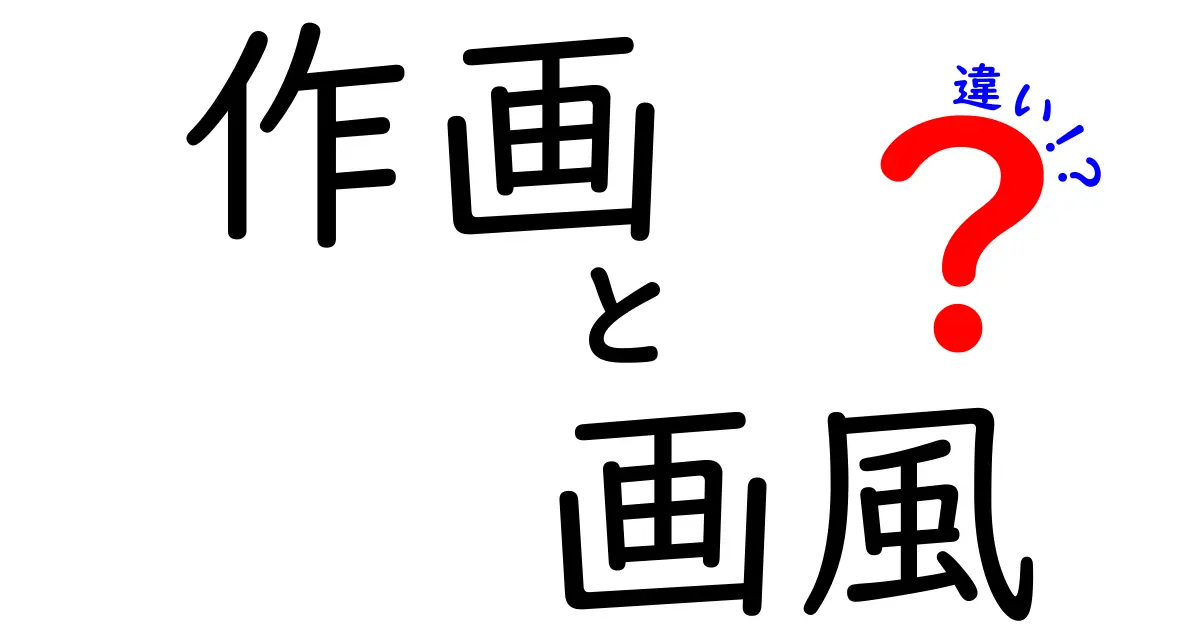

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
作画と画風の違いを理解する基本の考え方
作画は絵を描く技術的な動作の集合です。線の引き方、影のつけ方、人物の比率、ポーズの取り方、道具の使い方など、実際の作業としての技術が中心です。作画は技術の領域で、練習すれば誰でも向上します。画風と混同されがちですが、ここは分けて考えるのが大事です。画風はその技術を使った作品全体の「色合い」や「雰囲気」を指す、作り手の個性の表れです。画風はセンスと表現のスタイルの集積であり、同じ作画技術を使っていても、線の太さの揺れ方、陰影の描き方、色の選び方、背景の描き方などが違うと、作品の印象は別物になります。
例えば、同じ場面を描く場合でも、作画の技法が同じでも画風が違うと感じ方が変わることがあります。Aさんは線を細く滑らかに走らせ、影はわずかに階調をつけるのに対し、Bさんは線を太く力強く描き、影をはっきりと塗ることで別の緊迫感を出します。こうした差は、担当の編集部や読者の年齢層、ジャンルの性格によっても影響されます。作画が安定しているほど、画風の個性を際立たせる準備が整うと言えます。
- 作画は見える「技術の積み重ね」
- 画風は見える「個性や世界観」
- 両方が組み合わさって作品の魅力になる
- 時代や媒体によって画風は進化する
作画と画風の具体的な違いを見分けるコツ
描き方や印象の違いを「見るポイント」で整理します。例えば線の太さの揺らぎは手描きなら自然な癖として現れ、デジタルでもブラシ設定で再現可能です。陰影はどの程度グラデーションを使うか、ハイライトの位置が作品の立体感をどう決めるか、カラーは鮮やかさと落ち着きのバランスで画風を作ります。表現手法は時代と共に変化しますが、基本の構図と重さの感じ方を押さえると、作画と画風の両方を読み解く力がつきます。
また、実践としては次の練習が有効です。
1) 好きな作家の連載ページを選び、同じシーンを別の作画で模写してみる。
2) 画風が同じでも作画を変えるとどう印象が変わるか比較する。
3) デジタルとアナログの両方で同じ絵を描いてみて、手の動きとペンの質感の違いを体感する。
このように、作画と画風は別の軸として理解すると、絵を読むときの視点が変わります。自分の好きな画風を追求するのか、それとも技術を極めて作画力を高めるのか、どちらを優先するかは人それぞれですが、両方を意識して練習することで、作品の品質は確実に上がります。
ある日の放課後、私は美術室で友だちと絵の話をしていました。彼が『画風ってどうやって決まるの?』と尋ねたので、私なりの言葉で雑談風に説明してみました。画風は使う道具や線の癖、陰影の塗り方、色の組み合わせ、キャラクターの表情の作り方、背景の描き方など、技術だけでなく表現の仕方まで含む“個性”の集まりです。一方で作画はその技術を実際に描く行為で、練習すれば上達する部分です。私たちは同じ題材を描いても、線を細くする人と太く力強く描く人では全く違う印象になることを実感しました。なので、画風を追求するのか、技術を磨くのか、どちらを重視するかで絵の雰囲気は大きく変わります。次の課題では、同じポーズで線の癖を変える実験をして、違いを体感することにしました。
前の記事: « 刺繍枠 百均の違いを徹底解説!安さだけで選ばない選び方と使い分け





















