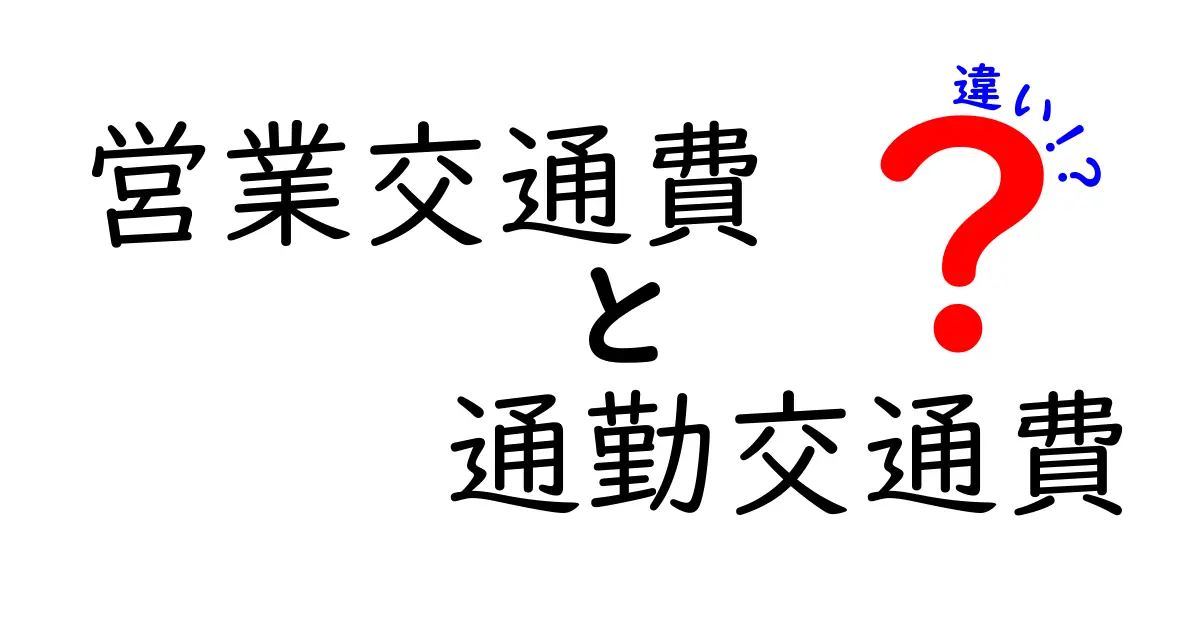

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
営業交通費と通勤交通費の違いを正しく理解するための基礎知識
営業交通費とは、会社が社員の業務上の外出のために発生する交通費のことです。ここには取引先訪問、現場調査、顧客プレゼンの移動、会議のための移動など、仕事を進めるために必要な移動が含まれます。私的な通勤や休憩中の移動は基本的に対象外です。
この区別は経費精算の際の基準にも直結します。なぜなら、営業交通費は会社の業務原価として処理され、税務上の扱いも異なるため、適切に分けることが社内の財務の透明性を高め、監査時にもスムーズに進みます。
一方、通勤交通費は従業員が自宅と職場を往復する際の交通費です。通常、日常の通勤は業務の一部とみなされ、個人的な娯楽や私的な旅費とは区別されます。会社が通勤手当を支給している場合、その手当は非課税枠の範囲で扱われることが多く、給与計算の際の社会保険料や所得税の計算にも影響します。ここで重要なのは、通勤交通費は原則として業務外の移動であり、勤務時間外や出張時の移動は対象外になることがある、という点です。
つまり、通勤交通費と営業交通費の線引きは「日常の通勤か、業務上の特別な移動か」という基準で判断します。
本記事の狙いは、2つの交通費の扱いの違いを、日常の申請や会計処理の場面で迷わず判断できるようにすることです。具体的には「どの移動が営業交通費になるのか」「どの移動が通勤交通費として扱われるのか」を、実務でよくあるケースと照らし合わせて解説します。表や例を交えつつ、給与計算・経費精算の基礎知識を中学生にもわかりやすい言葉で噛み砕いて説明します。
営業交通費と通勤交通費の実務的な使い分けと具体例
実務では、業務の性質が移動の中心になるほど営業交通費として扱う判断が強くなります。たとえば、取引先へ車で向かい、現地で商談を行い、帰社する一連の動きは「営業交通費」です。途中で私的な寄り道が混ざっても、目的が業務であることを証明できれば、票の分け方は保守的に整理します。領収書は必ず保管し、日付・目的・出発地・到着地を分かるように整理します。
通勤交通費は、日々の自宅-職場の往復に発生する費用で、通勤手当として支給されることが多いです。公共交通機関を利用した場合は運賃、車を使用した場合はガソリン代・駐車場代などが該当します。
重要なのは、私用の移動と業務移動を混ぜないこと、そして「勤務時間内の移動かどうか」「会社の規定に沿っているか」を確認することです。
また、経費精算の現場では、
・領収書の提出方法
・出張日程と交通費の整合性
・業務目的の明確化
・社内規定や税務のルールの遵守
を満たすことが重要です。下の表は、実務上の基本的な分類を整理したものです。
表の各行は、判断の柱となる要素を簡単に指し示しています。
営業交通費と通勤交通費の比較表
この表を見ながら、日常の申請時に「業務目的かどうか」を最初のチェックポイントにする習慣を身につけると、ミスが激減します。社内規定の改定にも敏感になり、必要であれば上司へ事例を添えて相談することをおすすめします。
koneta: 友人と雑談風に話すとこうなる。『通勤交通費って、毎朝の満員電車代を毎月もらえる感じだよね。でも本当に私生活の寄り道が混ざると経費としてはアウトになることもある。つまり“この移動は仕事に直結しているか”が大事。だから通勤手当の範囲や非課税の枠を理解しておくと、給料明細を見ただけで自分の費用がどこまでカバーされるか分かるんだ。』
前の記事: « 社用車と自家用車の違いを徹底解説:使い分けのポイントと落とし穴





















