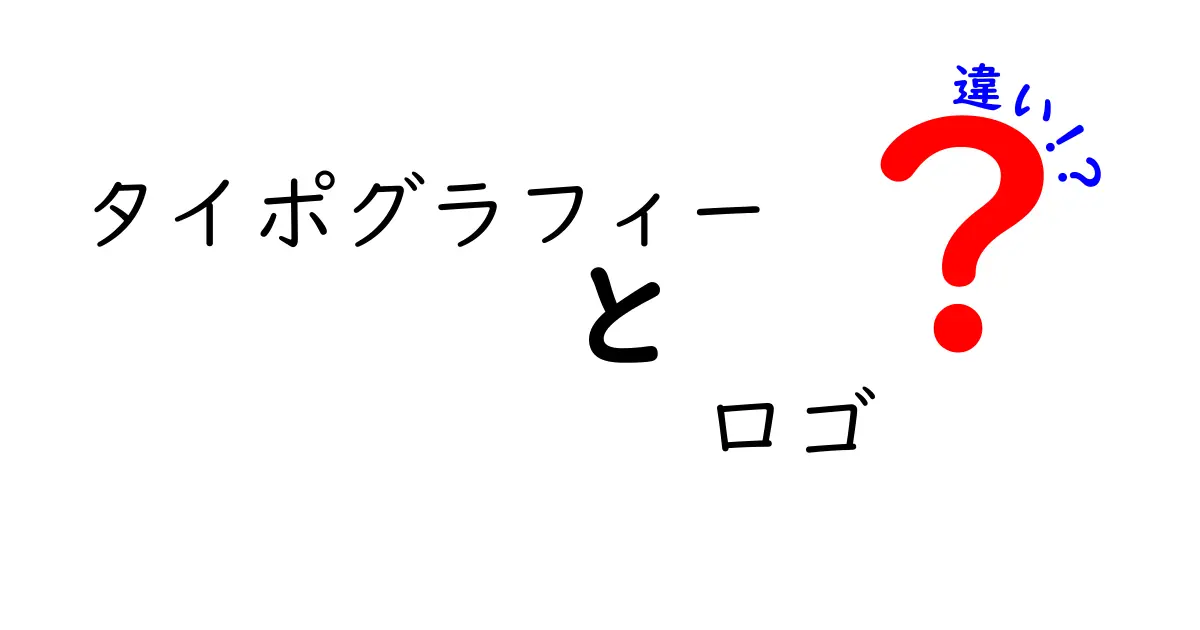

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
タイポグラフィーの基本とロゴの役割を見分けるコツ
タイポグラフィーとは文字そのもののデザインのことです。文字の形、字形、字間、行間、サイズ、そして読みやすさを整える技術を含みます。日常生活では、ニュースの見出しや教科書の本文で文字がどのように並ぶかが目に入ります。読みやすさを第一に考え、情報を伝える力を高めることがタイポグラフィーの役割です。一方、ロゴは企業やブランドの“顔”としての役割を持ちます。ロゴは文字だけでなく図形やシンボルを組み合わせることが多く、識別性と記憶に残る印象を作るのが目的です。
この二つの違いを理解すると、デザインの考え方が見えてきます。ウェブの本文や見出しに使う文字は長時間読んでも疲れないように選び、デザインの雰囲気を大切にします。ロゴは小さく表示される場面や看板、広告の中で、一瞬でブランドを伝える力が求められます。一貫性を保つためにはフォント同士の相性、色の組み合わせ、余白の使い方をブランド全体で揃える必要があります。
さらに、色と形の組み合わせは読む人の感情にも影響します。
実務でのコツとしては、まずブランドの目的や価値観を言葉にしてから字形を選ぶという順序を守ることです。例えば柔らかい雰囲気なら丸みを帯びたフォントを選び、力強さを出したいときは角の鋭いフォントを検討します。さらにロゴが縮小されても読みやすいこと、黒と白だけでも強い印象を与えられることを確認します。こうした視点を持つと、タイポグラフィーとロゴの間にある境界が自然と見えてきます。
雑談のように言えば、デザイナーは文字の形と看板の形の両方を同時に見るわけです。読みやすさと識別性は両立させるべきであり、一方だけを優先すると他方が崩れます。現場ではフォントの選択だけでなく、実際の印刷物やディスプレイでの見え方を何度もチェックします。こうした作業を積み重ねると、タイポグラフィーは「情報を整えた言葉の美しさ」、ロゴは「ブランドの顔としての強さ」という二つの道具として確かな役割を果たすことが理解できます。
タイポグラフィーがロゴに与える影響とデザイン実務での活用
タイポグラフィはロゴデザインの基盤として働くことが多いですが、実際にはロゴの多くは文字そのものと記号部分の組み合わせで成り立っています。文字をどう配置するか、どのフォントを選ぶか、字間をどう調整するかは、ブランドの性格を左右します。文字を選ぶときにはモダンさ、伝統、遊び心といった雰囲気を意識します。
たとえばモダンな企業ならサンセリフ体で清潔感を出し、伝統を守る企業ならセリフ体で信頼感を強めるなどの判断が必要です。
現場のワークフローでは、フォントガイドを作ることがよくあります。フォントの種類、太さ、サイズ、カラー、間隔のルールを文書化しておくと、デザイナーが変わっても作品の見た目を崩さずに広範囲へ展開できます。ロゴを紙に印刷する場合とスマホの画面で表示する場合では読まれる文字の大きさが違い、同じ文字でも感じ方が変わる点を忘れてはいけません。
また一貫したブランドガイドラインがあると、広告、SNS、商品パッケージなど異なる媒体間でデザインの連携がとれます。タイポグラフィーの選択は色との組み合わせにも影響し、色温度や背景色によっては同じフォントでも見え方が大きく変わります。こうした点を意識して設計すれば、視認性と覚えやすさを両立させられます。
最後に実務のコツとして、段落を区切る、見出しを使い分ける、空白を活用するなどの戦略があります。これらはすべてタイポグラフィの力を活かしてロゴの伝えたいメッセージを受け手に正しく届けるための手段です。
今日はロゴについての小ネタを雑談風に。ロゴは看板の顔のようなものだけど、その顔が一瞬でブランドの印象を決めます。実は同じ文字でも横書きの流れ方や曲線の角度一つで雰囲気ががらりと変わることがあり、友だちと話すときの声のトーンみたいなものだと考えると分かりやすいです。私がよく使う雑談のコツは“文字の形だけを見ないで、全体のイメージと使われる場を想像する”こと。覚えやすさと再現性、そしてブランドストーリーを三つ巴でバランスさせることが、いいロゴを作る近道なんです。





















