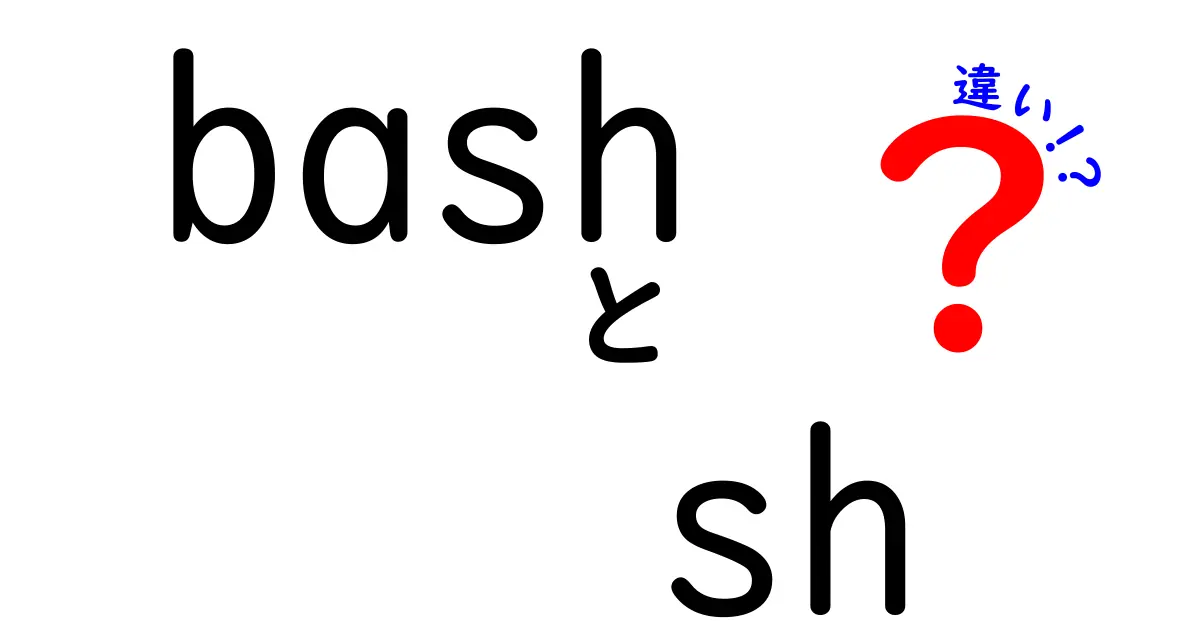

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
bashとshの違いを理解するための基礎知識
まずは基本の整理から始めます。bashとはBourne Again SHellの略で、GNUプロジェクトの一部として生まれたシェルです。開発が進むにつれて当初のshの機能を大きく拡張し、コマンドラインの編集履歴補完、配列や関数、条件分岐の便利機能などが追加されました。これによりスクリプト作成の表現力が大幅に上昇しました。対してshは元々の Bourne Shell の実装で、長い歴史の中でPOSIX準拠の仕様が定められ、互換性を重視する設計になっています。つまり bash はshの拡張版と捉えるのが自然ですが、sh 自体はより厳密な標準に従い移植性を高める役割を果たします。
現代の環境ではLinuxの多くがデフォルトの対話シェルとしてbashを提供しており、スクリプトを走らせる際にもbashを前提に書くケースが多いです。
ただし配布先の環境が POSIX 準拠を厳格に要求する場合や、他のシェルを使うエンジニアの環境に移植する場合は sh 互換の書き方を選ぶことが安全です。さらにWindowsの WSL や macOS の古い環境では sh の実装が別物だったりするため、実行環境を意識した選択が必要です。
理解を深めるためのポイントをまとめます。
1) bash は高機能で学習コストが少し高めだけれど、日常の作業効率を大きく改善します。
2) sh は標準準拠の動作が安定しており、移植性を高めたい場合に適しています。
3) 互換性の点では bash はposix 準拠モードを使えば sh と同様の動作を取りやすくなります。
以下のポイントを押さえると迷いが減ります。
- 実務ではまず POSIX 準拠の書き方を意識して sh 互換を確保する。
- どうしても bash 独自機能を使う場合は shebang を明示して実行環境を限定する。
- 移植の際には echo の振る舞いなど細かな差異に注意する。
実務での使い分けと違いの要点
実務での使い分けは主にスクリプトの移植性と機能要件に左右されます。bash は補完機能や配列の操作、関数の定義方法、条件式の拡張など日常的な作業を楽にします。例えばファイル名の配列から特定の要素を取り出す場合や、任意の長さのコマンド履歴を操作する場合など便利な機能があるため、学習コストを少し上げても長期的には作業効率を上げやすいです。
一方 sh は最小限の機能で動作するため、スクリプトの互換性を最優先したいときに選択します。特に古いLinuxディストリビューションや UNIX 系のシステム、あるいは他のシェルを使うエンジニアの環境に移植する場合には sh で書くことが安心です。
なお /bin/sh の実装は環境によって異なることが多く、bash と sh で挙動が微妙に変わるケースがあります。これが原因でシェルスクリプトが期待通りに動かない状況もあるため、作成時には事前の検証が欠かせません。
表での比較も実務には役立ちます。以下の表は実務で特に押さえるべき違いをまとめたものです。
結論としては、現代の多くのケースでは学習と開発を進めやすい bash を基準にして、特定の環境へ移植する必要がある場合のみ sh 互換の書き方を選ぶのが現実的です。プロジェクトの要件に応じて shebang で実行環境を限定するなど、初期設計の段階で方針を決めておくと後の混乱を防げます。
ある日友達と勉強していると bash の補完機能の話題が盛り上がりました。補完はタブを押すと次々候補を出してくれる便利機能ですが、設定次第で挙動が変わります。私のおすすめは ~/.bashrc を少しずついじって補完の順序と候補の範囲を自分好みに最適化すること。sh には標準の補完機能は少なめですが、外部ツールを使えば同様の体験が得られます。要は使い方を知っていれば、どちらの環境でも作業の効率を上げられるということ。
前の記事: « awkとsedの違いを徹底解説:初心者でも分かる使い分けのコツ





















