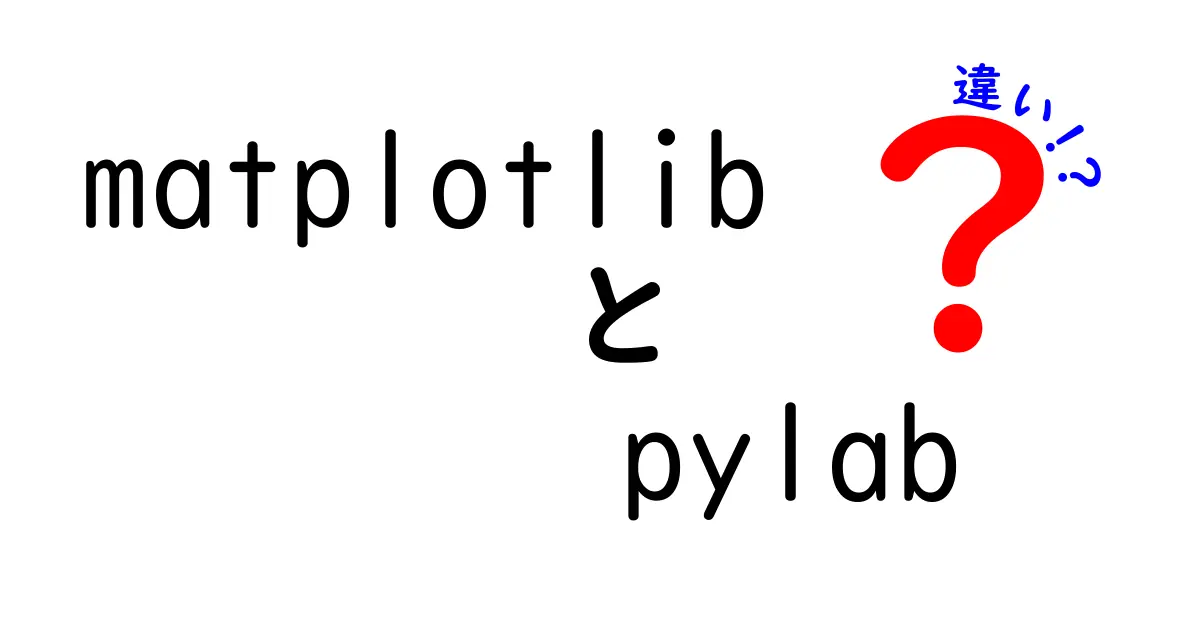

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
matplotlibとpylabの違いを理解する基本ポイント
matplotlibはデータを可視化するための最も広く使われているPythonライブラリです。折れ線グラフ、棒グラフ、散布図、ヒストグラムなど、さまざまな図を描くための関数がたくさん用意されていて、研究や授業、業務の現場でも日常的に登場します。長い歴史の中で多くの機能が追加され、APIも成熟しています。一方のpylabは、かつてmatplotlibの中でnumpyの機能とpyplotを一つの名前空間にまとめて提供していた「まとめモジュール」でした。MATLAB風の操作感を目指して、初心者にも覚えやすい設計になっていました。しかし現代のPythonコードの推奨パターンは、pylabを避け、matplotlib.pyplotを個別にimportして使うスタイルです。理由は、名前空間の衝突を減らし、コードの可読性とデバッグ時の原因追跡を容易にするためです。ここでは、そんな違いを中学生にも分かる言い方で、実例とともに丁寧に解説します。
ここで覚えておきたいのは、大事な機能はどちらの名前空間にも存在しますが、推奨される書き方は「import matplotlib.pyplot as plt」とすることです。そうすることで、関数の出所がはっきりし、デバッグやコラボレーションがスムーズになります。
さらに、pylabを使うとミニマムなコードで同じ結果を得やすい場面はありますが、違いを混同するとコードの可読性や再現性が落ちる可能性があります。
なぜこの違いを知ることが大切なのか
この違いを知っておくと、授業ノートや研究ノート、プレゼン資料の作成時に「何をどう呼び出しているのか」が明確になります。名前空間の衝突を避けることは他のライブラリと組み合わせるときにも重要で、特に複数の人が同じコードベースを使う場合に効果を発揮します。pylabは昔は手軽さが魅力でしたが、現代のコードはモジュール単位のimportを基本とするのが安全です。これにより、どの関数がどのモジュールから来ているのかを追いやすく、バグの原因を特定しやすくなります。さらに、学習の観点からも、pltとnumpyの機能を別々に理解する練習が効率的です。新しいデータサイエンスの教材や公式ドキュメントもこの書き方を推奨しています。例えば授業で配布するサンプルコードや研究の再現性を高めるときには、コードの依存関係が薄くなるほど良い結果が出やすくなります。現場では、他のPythonライブラリ(例えばpandasやseaborn)と組み合わせる際にも、どの関数がどのモジュールに属しているのかを明確にすることがトラブルを減らします。
具体的な使い分けと実践テクニック
ユースケースごとの考え方を整理します。まず、図を描く基本的な処理はpltを使うのが最もわかりやすいです。コードの可読性を高めるためにも、関数の呼び出し元をpltに統一すると、他の人が読み解きやすくなります。次に、データの準備や数値処理はnumpyやpandasの機能を別のモジュールとして扱い、描画だけ plt を使うのが実務的です。pylabのような「一気に全体を import する」スタイルは、現在の大規模プロジェクトでは推奨されません。以下に実践的な使い分けのポイントを挙げます。
- モジュール分離: データ処理は numpy/pandas、描画は plt
- 再現性: 依存を最小化する import構成
- 学習の順序: まずpltとnumpyの基本を理解し、徐々に高度な描画へ
具体的な実践としては、まず次のような書き方を習慣づけると良いでしょう。
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.style.use('seaborn-darkgrid')
fig, ax = plt.subplots()
表で見る違いと実務上の選択
以下の表と実践のコツを見れば、いつpltを使い、いつpylab風の書き方を避けるべきかがすぐ分かります。安全第一の観点から説明します。最初は混同しやすい点を整理しておくと、コードの品質が長期的に安定します。
昔、友達とデータをいじっていたとき、pylabという魔法の箱を開くと、numpyとpyplotの世界が一緒くたになって、コードが一気に短くなる感覚がありました。だけど、時間がたつにつれて『どの機能がどこにあるのか』がわかりづらくなるデメリットも気づきました。今はそうした経験を踏まえて、必要な機能だけを丁寧に import して使うのが一番だと思います。pylabは懐かしい気持ちを呼び起こす存在ですが、現場ではpltを使う選択が安全で賢いと感じます。





















