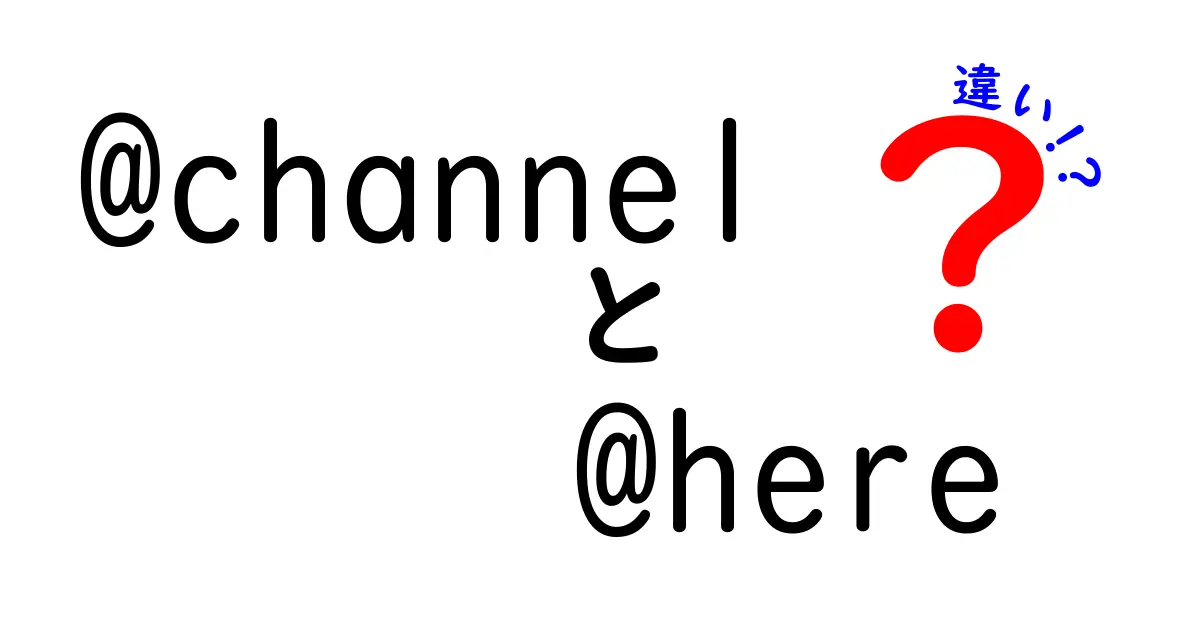

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
この記事のタイトル: 【最新】@channelと@hereの違いを徹底解説!使い分けで職場の通知を最適化
この二つの用語は通知の範囲を決める重要な仕組みですが 日常の業務で使い分けを間違えると混乱を生む原因にもなります。まず @channel についてです。@channel はチャンネルの全員に通知を送る機能であり その時点でチャンネルに参加していない人や オフラインの人にもメッセージが届きます。緊急のお知らせや全体会議の連絡、プロジェクトの方針変更など、"全員に知らせたい"場面で活躍します。逆に言えば 緊急性が低い連絡をこの機能で乱用すると 重要な通知の価値が薄れてしまいます。だからこそ 文脈と頻度の管理が大切です。
続いて @here です。@here は現在オンラインのメンバーに限定して通知を送る機能であり つまりその場にいる人だけが受け取ることになります。これにより オンラインで作業している人に対してのみリアクションを促すことができますが 眠っている人や別のタスクに集中している人には通知が届かない点にも注意が必要です。会議の開始を伝えるときや すぐに回答が必要な質問を投げかけるときには有効ですが 求められていない場面で使うと 迷惑に感じる人も出てくるかもしれません。結局のところ 片方だけを万能と思わず 文脈と相手の状況を見て使い分けるのがコツです。
実務での使い分けと注意点
現場での使い分けのコツは 事前のルールを作ることです。例えば チームの中で緊急の連絡は @channel それ以外の一般的な連絡は @here で対応するといった基本ルールを共有します。
具体的には以下のような運用を検討してください。まず 緊急性が高い情報や全体に影響する連絡は @channel を使い 先に状況を一行で要約し その後に詳しい説明を補足します。次に 個別の質問や短時間で回答が望まれる依頼は @here で 問い合わせの意図と締切を明記します。これにより 現場のメンバーは通知を受け取った後にすぐ対応可能か判断できます。さらに 適切な文脈を添えることは忘れずに。例として"今の仕様変更について確認します。回答は本日中にお願いします"のように 緊急性と期限を明記すると 読み手の混乱を減らせます。
またプラットフォームごとの違いにも注意が必要です。Slack ではチャンネル全体へ通知を送る能力が強力ですが 過度な使用は通知疲れを招きます。一方 Discord など他のツールでは同様の機能名が別の挙動になることがあるため そのサービスの仕様を事前に把握しておくとよいでしょう。総じて重要なのは"誰に 何を いつ伝えるべきか"という問いに対する明確な基準を作り その基準に沿って運用することです。
最後に 実務での運用を成功させるコツとしては 説明付きの短い通知を心がけることと 頻度を控えめにすることです。これらを守ると 受け手は何を伝えたいのかを素早く理解でき、情報伝達の効率が上がります。
ねえ ここだけの話 @here を使うとき 私たちはついつい手を抜きがちだけど 実はそれだけ場の空気を感じる力が必要なんだ。@here は今この場にいる人だけに伝えるという 小さな気遣いの技なんだよ。全員に伝えるべき時と 今この瞬間だけ確認が必要な時の境界線をどう引くか その感覚があなたのチームのコミュニケーション力を支える。日常の雑談や急ぎの質問の判断を丁寧に行えば みんなのレスポンスは速くなり 結果として作業の流れがスムーズになる。小さな一手が 大きな信頼につながると覚えておこう。





















