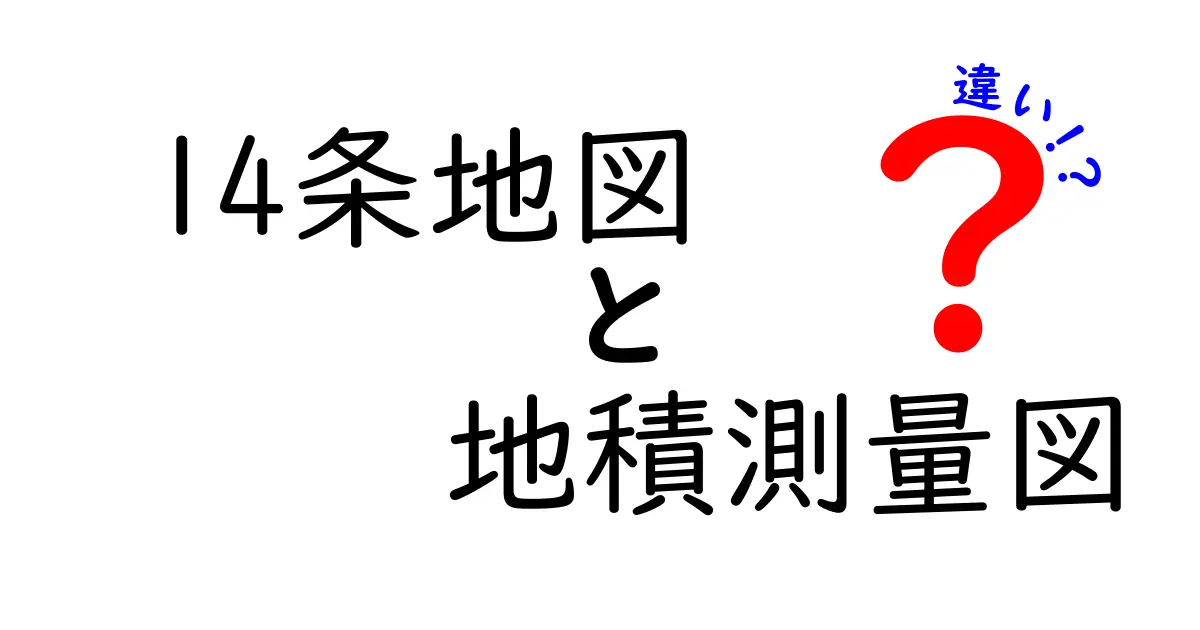

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
14条地図とは何か?その特徴をわかりやすく解説
まずは14条地図について見ていきましょう。14条地図とは、土地家屋調査士や測量士が土地の境界や面積を調べる際に作成される地図の一種です。正式には「土地基本調査図」とも呼ばれていますが、これは不動産登記法第14条に基づき作成されるため、一般的に「14条地図」と呼ばれています。
14条地図は主に土地の境界の位置や隣接地との関係を表すため、土地の全体像をつかむことができます。具体的には、土地の形状や隣接地との境界線、道路の位置などが描かれており、土地の所有者や利用者にとって重要な情報源となります。
また、14条地図は行政や登記所で管理されており、土地の売買や相続の際に重要な根拠資料となるため、信頼性も高いです。以上の特徴から、14条地図は土地の大きな枠組みを理解するのに適した地図と言えます。
地積測量図とは?その目的と使い方
一方で、地積測量図は土地の面積を正確に測るために作成される詳細な測量図です。こちらは登記簿に登録する目的で作成されることが多く、土地の正確な面積や形状を記録するための最も基礎的な図面の一つです。
地積測量図には、土地の隅々の座標や各辺の長さが表示され、これにより土地の面積が正確に把握できます。特に土地の分割や合併、境界確定が必要なときに用いられ、不動産登記の際に必須になることが多いです。
また、地積測量図は土地の形状が細かくわかるため、建築計画や土地の利用計画を立てる際にも重宝されます。このように、地積測量図は土地の実際の状況により近い形で表現していることが特徴です。
14条地図と地積測量図の違いを比較表で解説
ここまで説明した2つの地図の違いをわかりやすく比較するために、以下の表を見てみましょう。
| ポイント | 14条地図 | 地積測量図 |
|---|---|---|
| 作成目的 | 土地の境界全体を把握するため | 土地の面積と境界を正確に測定するため |
| 主な内容 | 土地の形状、境界線、隣接関係 | 土地の座標、辺の長さ、面積 |
| 利用場面 | 土地の全体的な把握、行政手続き | 登記申請、土地の分割・合併など |
| 作成者 | 土地家屋調査士や行政 | 土地家屋調査士 |
| 信頼性 | 比較的信頼度高い | 非常に高い(法的根拠となりやすい) |
こうしてみると、自分の土地を正確に知りたいときは地積測量図、土地の大まかな全体像や場所を確認したいときは14条地図を利用すると良いことがわかります。
まとめ:どちらを使うべき?目的別の選び方
最後に、どちらの地図を使うべきかについてまとめます。
1. 土地を売買したり、正確な面積を証明したいときは
→地積測量図を利用しましょう。これは法的な証明力が強く、登記簿の記録にも基づきます。
2. 土地全体の場所や隣接関係をざっくり把握したいときは
→14条地図を確認すると便利です。手軽に土地のつながりや境界をイメージできます。
このように、ケースに応じて使い分けることが土地トラブルの防止にもつながります。土地の売買や建築計画の際には、専門家に相談しながら適切な地図を参照することをおすすめします。
さて、今回の記事では「14条地図」と「地積測量図」の違いについて詳しく説明しましたが、中でも面白いのは「14条地図」が土地の全体像を示すのに使われることです。実は、この14条地図はかなり大まかな情報が多く、細かい寸法までは分かりません。
だから、例えば隣の家ギリギリに塀を作りたいとか、細かな境界の争いを解決したい場合にはあまり役立たないんです。でも逆に、大規模に地域の土地の形を把握するのには適しているので、街づくりや都市計画の下地資料として活躍しているんですよ。
こんな感じで、それぞれの地図には得意な用途があって、土地の世界はとても奥深いんだなと思いました!
前の記事: « 地積測量図と求積図の違いとは?初心者にもわかる徹底解説!
次の記事: 地積測量図と地籍図の違いとは?初心者でもわかる図面の見方ガイド »





















