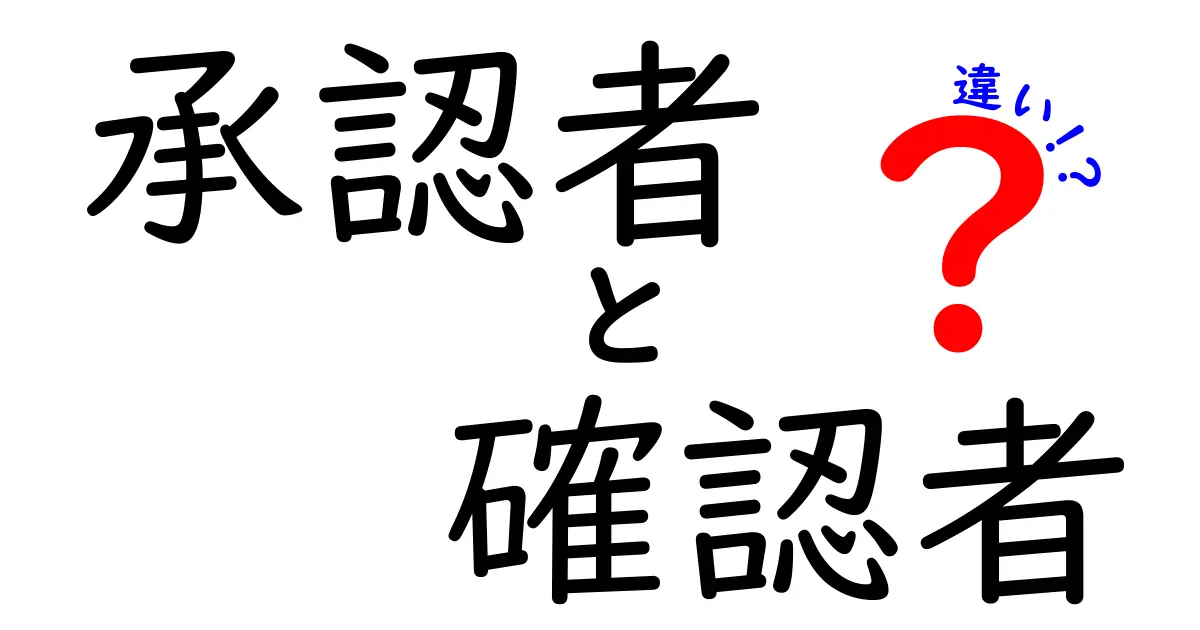

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
承認者と確認者の基本的な違い
承認者と確認者は、組織の中で意思決定の流れを支える重要な役割です。承認者は権限を持って最終判断を下す人で、予算の承認や文書の署名など、決裁の最終責任を負います。これに対して確認者は提出物の正確性や手続きの適切さを検証する役割で、情報の間違いを防ぎ品質を守る役目を担います。両者の違いは、誰が決定を下すかと、誰が品質を保証するかという点に集約できます。
実務では承認者と確認者の順序が決まっており、通常はまず確認者が資料を精査し、次に承認者が正式に決裁します。もし確認者が誤りを見逃した場合、承認者の判断にも影響を与え、プロジェクト全体のリスクが高まることがあります。だからこそ、事前の準備と分担の明確化が重要です。ここで押さえるべきポイントを3つ紹介します。
- 確認者は情報の正確性を最優先にチェックし、事実関係・データの整合性を確認します。
- 承認者は全体の戦略とリスクを考え、組織の方針に沿って最終的な判断を下します。
- 両者の役割が混ざらないよう、事前に手順書や承認の枠組みを共有しておくとミスが減ります。
表では両者の違いを端的に比較します。読み手がすぐ理解できるよう、要点だけを整理した表を次に示します。
この表を見れば、両者の役割の違いが一目でわかります。承認者は「決断の責任者」、確認者は「情報の信憑性を担保する人」です。
現場ではこの2つの役割を混同しやすい場面があり、特に急ぎの案件や新しい手続きが導入されたときに混乱が生じがちです。
したがって、事前の教育と役割の再確認が不可欠です。
現場で差が出る具体的な場面と注意点
実務で承認者と確認者の違いがはっきり現れるのは、文書の最終リリース前のタイミングです。例えば新規予算の申請、契約書の締結、重要な社内通知などでは、確認者が先に質を担保し、承認者がリスクと方針を総合して最終承認を行います。こうした場面を想定して、手順書を作成しておくと効果的です。
現場での注意点を3点挙げます。
1) 情報の出所を明記すること。
2) 変更履歴をきちんと残すこと。
3) 緊急時の代替承認ルールを事前に取り決めておくこと。これらを守れば、承認者と確認者の役割がはっきりし、トラブルを減らせます。
- 確認者がデータの正確性を確認する手順を簡潔に説明する。
- 承認者が最終決裁の基準を明確に記述する。
- 双方が連携するための連絡窓口と連携手順を定義する。
最後に、現場での実例を挙げておきます。ある案件で確認者が「データの出典が不足している」ことを指摘し、承認者は「戦略的影響を考慮して追加の分析を求めた」という流れが発生しました。ここでは両者の役割がきちんと分かれていたおかげで、プロジェクトは遅延を最小限に抑えつつ、品質を担保できました。
友達と話しているような雑談形式の小ネタです。承認者という言葉を耳にすると rigid で難しそうに思えるかもしれませんが、現場では“決断の人”と“情報の確かさを守る人”の2人によって物事が動きます。ある日、部長が新しい予算案を出した瞬間、確認者が「この数字はどこから来たのか?」と尋ね、承認者が「この案にはこのリスクがあるから、追加分析を求めよう」と答え、結局案は改善されて前に進みました。つまり、承認者は決断の責任を引き受け、確認者はデータの信頼性を守る。二人の協力がうまく回れば、会議はスムーズに進み、成果はしっかり現場に落ちていきます。日常の業務でも、急ぎのときほど役割の線引きを意識すると、ミスや混乱を減らせます。私はこの2つの役割を意識して仕事を回しています。
次の記事: 伺い書と稟議書の違いを徹底解説 – 使い分けのコツと実務ポイント »





















