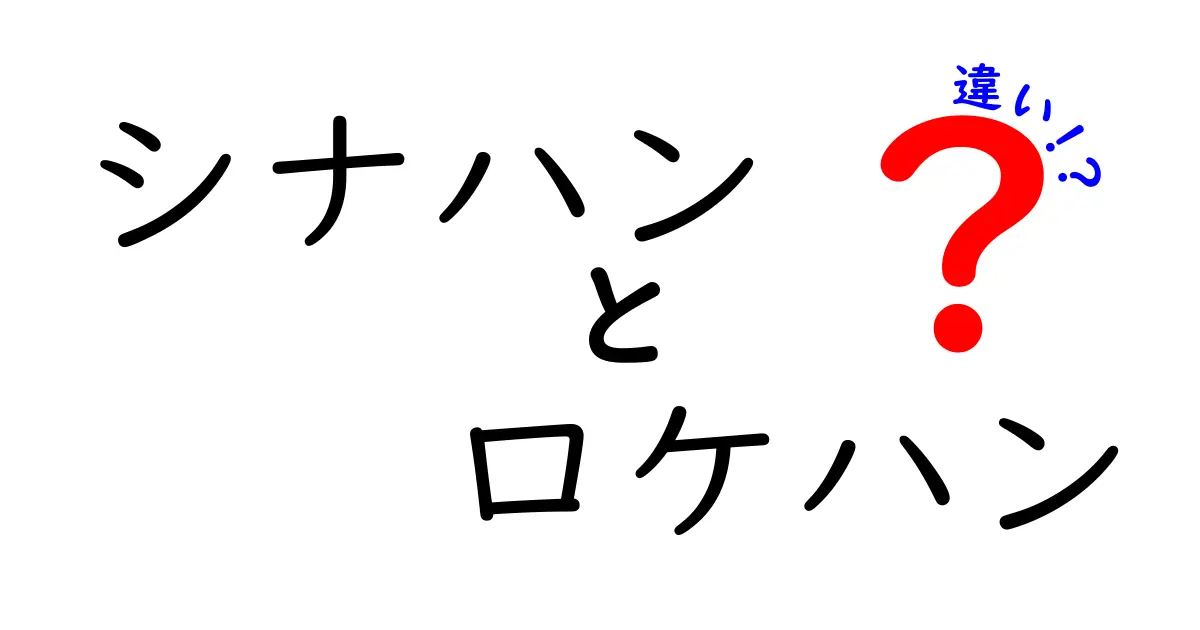

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
シナハンとロケハンの違いを徹底解説!初心者でも分かる撮影準備の秘密
シナハンとロケハンは、映画やドラマ、CMなどの制作現場でよく耳にする言葉ですが、その意味と役割はかなり異なります。シナハンは物語を形にする設計図を作る作業で、ストーリーの骨格を決め、場面のつながりを検討します。ロケハンは実際の場所を歩き回り、撮影が現実に成立するかどうかを判断します。どちらも作品を動かす大切な工程ですが、目的が違えば進む道筋も変わってきます。理想の演出を生み出すためには、シナハンとロケハンを別々に行うだけでなく、それぞれの成果物を相互に照合していくことが求められます。
例えば、シナハンで決まった場面配置が、現場の場所の形や光の具合と食い違っていると、後で修正が発生します。逆に、ロケハンで見つけた場所の特徴が、シナハンで描いた世界観と合わない場合には、演出や予算の見直しが必要になることもあります。そのため、企画の初期段階から両者を組み合わせる「前提の共有」が重要です。ここでは、初心者にも分かるよう、二つの工程の違いを分解し、実務上のコツを具体的な事例を交えて紹介します。
このガイドを読んだあなたは、シナハンとロケハンの違いを理解したうえで、企画書作成から現場準備までの流れを自分の言葉で説明できるようになります。物語を作る人と場所を選ぶ人、それぞれの視点が噛み合えば、観客に伝わる強い体験を作り出せるのです。
シナハンの意味と役割
シナハンとは「シナリオ・ハンティング」の略称として使われることが多く、物語の設計と演出方針の決定を中心に行われます。まずは作品の核となるテーマを明確化し、物語構造を整え、各場面の目的を定義します。続いて、キャラクターの動機や成長、対立構造、転換点を詳しく詰め、視聴者が飽きることなく引き込まれる流れを作ります。これには、ビートシートやシーン別の「キーとなる出来事」の設計、セリフのトーン、画面構図の意図を文書化する作業が含まれます。
また、予算制約や放送尺、対象年齢などの現実条件を踏まえ、最適な演出案を練り上げることも大切です。シナハンの成果物には、台本のドラフト、演出ノート、ショットリストの土台、登場キャラクターの性格像、しかく化された場面展開の指示などが含まれます。これらは最終的な撮影計画の根幹となり、監督・脚本家・プロデューサーが共通認識を持つ基盤になります。
ロケハンの意味と役割
ロケハンは「ロケーション・ハンティング」の略称で、現場の条件を現場で確かめ、撮影の実現性を判断します。現場の雰囲気だけでなく、光の具合、音の収集、天候、アクセス、機材搬入の難易度、撮影許可の要件、安全リスクの有無を総合的に評価します。現場での実測は写真・動画・メモを組み合わせ、時間帯ごとの光の変化、風の影響、騒音源の有無、近隣の迷惑にならないかといったポイントまで記録します。さらに、撮影の予算とスケジュールの現実性を検討し、必要ならば別の場所の候補を並行して検討します。ロケハンの成果物としては、場所の基本情報をまとめたロケ地ファイル、現場の写真・動画、撮影許可の取得に向けた連絡先リスト、当日のスケジュール案、代替案の案内が含まれます。こうした情報は、撮影日までの意思決定をスムーズにするための道案内となります。
具体的な作業フローの違い
シナハンの作業フローは、まず企画の核となるテーマを固め、次に登場人物の動機や関係性、物語の主要な転換点を設定します。続いて、シーンの順序を決めるビートシートを作成し、ショットのイメージを描くショットリストの土台を作成します。これにより、台本のドラフトが生まれ、演出方針と台詞のトーンが具体化されます。ここでの成果物は、台本ドラフト、演出ノート、ショットの方向性の指示などで、予算尺・放送尺・納期などの制約と擦り合わせを行いながら、最適な撮影計画の骨格を作り上げます。ロケハンの作業フローは対照的で、まず事前リサーチで候補地を洗い出し、現場へ出向いて光・音・風・背景の条件を実測します。次に、現場の情報を写真・動画・ノートにまとめ、撮影可能性・搬入動線・安全性・費用を総合的に評価します。撮影許可の手続きや保険加入の必要性、機材の持ち込み経路、スタッフの動線もこの段階で検討します。最後に、最適候補を選び、候補地ごとの代替案を準備して、ロケハン報告書として関係者へ共有します。これらの段階を経ることで、実際の撮影日が近づいても迷いが少なく、スムーズに進行できます。
使われる場とタイミング
シナハンは企画の初期段階から撮影直前まで、物語の方向性や演出の基本方針が固まっていく時期に特に重要です。脚本の完成度を高め、場面のつながりを明確化することが目的なので、監督・脚本家・プロデューサーの共同作業が活発に行われます。ロケハンは主に撮影準備の前半〜直前にかけて実施します。現場の条件が整っているかを確認し、日程調整や機材搬入、許可取得などの実務を詰めていきます。天候や季節の影響は作品の印象を大きく左右するため、ロケハンの情報は日程決定にも直結します。例えば、同じ脚本でも街の近代的な場所と古い町並みを選ぶ場合、シナハンで想定したテンポ感とロケハンで確認した現場の雰囲気にズレが生じやすいです。こうしたズレを防ぐコツは、両者の情報を密に共有すること、そして代替案を常に用意しておくことです。
まとめ
シナハンとロケハンは、作品を完成させるための「設計」と「現場の現実」という対照的な役割を担います。物語をどう伝えるかと場所をどう活かすか、この二つの視点を結ぶ橋渡しができる人材が、良い作品づくりには欠かせません。最初は混乱しやすいですが、順序としてはシナハン→ロケハン→両者の統合という流れが基本です。経験を積むにつれて、脚本の段階での演出方針と現場の実情が一つのビジョンに収束していく感覚を味わえるようになります。
友達とカフェでの会話スタイルの小ネタです。『ねえ、シナハンとロケハン、実際どう違うの?』と聞かれたので、私の体験を元に話してみました。シナハンは物語の設計図を描く作業で、登場人物の気持ちや動機、場面のつながりを丁寧に考えます。台詞のリズムや視点の切り替え、物語のテンポをどう作るかを決めるのが主な仕事です。つまり、「どう伝えるか」を決める工程ですね。一方のロケハンは現場の空気を読み、場所の魅力を確かめる作業です。光の向きや騒音、車の搬入経路、天候など、現場の現実性を検証します。私は実際に現地で写真を撮り、スタッフと共有して、どの場所が最も作品の世界観を映し出せるかを討論します。結局、二つの作業は別々の役割を担いながらも、良い作品を作るための情報を集める点で同じ目的を持っています。だから、私は両方の情報を一つのビジョンに結びつける“橋渡し役”になることを心がけています。
前の記事: « ヘアメイクとメイクの違いを徹底解説!中学生にもわかる基本とコツ
次の記事: 実寸と採寸の違いを徹底解説!サイズ表の誤解をなくす3つのポイント »





















