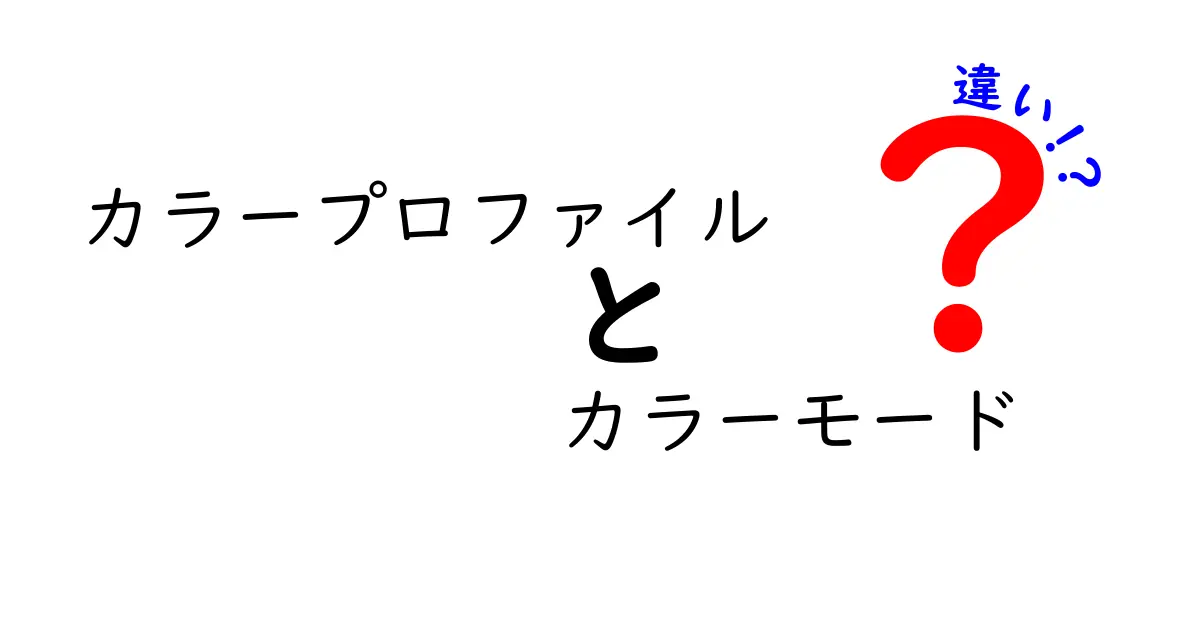

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カラープロファイルとカラーモードの基本的な違い
色を扱う場面で「プロファイル」と「モード」という言葉はよく出てきますが、初心者には混同しやすいポイントです。ここでは、カラープロファイルとカラーモードの意味の違いを丁寧に見ていきます。まず前提として、私たちが見ている色は“物体が反射する光の色の集合”であり、機械によって表示される色はその機械の性質に左右されます。
このため、写真や映像を正しく表示するには、撮影後のデータが他の機器でも同じように解釈されるようにする仕組みが必要です。
ここで登場する2つの要素は、それぞれ役割が違います。
まずカラープロファイルは、色を別の機器へと“翻訳”するための辞書のようなものです。
ICC(International Color Consortium)という標準を使い、機器間で色を同じように解釈できるように対応させます。具体的には、撮影したデータを現像・編集する際に「この画像はどの色空間で作られたか」「この色はどう解釈するべきか」を決める指針です。代表的な例としてはsRGB、Adobe RGB、ProPhone RGBなどがあります。
一方、カラーモードは「そのデータをどのように見せるか・どう扱うか」という表示側の解釈ルールを指します。例えば、画面で表示する場合には「このデータをどの空間として扱うか」を決める設定です。
ここには“表示時の空間”と“作業空間”という二つの考え方があり、OSやアプリの設定、モニターの色域といった要素が絡みます。すなわち、カラーモードは見た目の色に直結し、勝手に色が変わって見えたらそれは自分の設定とデバイスの組み合わせが原因です。
このように、プロファイルは色を正しく翻訳するための辞書、モードは表示・運用の仕方を指示する設定という役割分担になります。以下の表で、それぞれの特徴と使いどころを整理します。
この2つの概念を正しく区別して理解することが、色の統一感を保つ第一歩です。
実務での使い分けとよくある誤解
写真部やデザイナーの現場では、色の再現性を保つために日常的にこの2つを組み合わせて使います。まず、ウェブ用の画像を作るときは基本はsRGBで保存します。これはほとんどのモニターやスマホで同じように表示される標準の空間だからです。モニターの色域が狭いと感じても、Web上の表示ではこの統一が崩れにくくなります。反対に印刷物を意識する場合には、プリンターのICCプロファイルに合わせることが重要です。ここで「作業空間をAdobe RGBにしておくと印刷時の色が豊かに見えることがあるが、Web用には不向き」という現場の声があります。これはカラーモードの選択とカラープロファイルの適用が別々の段階で行われているため起こる現象です。
具体的には、撮影時にAdobe RGBで撮影して現像する場合、作業中の表示空間をAdobe RGBに設定することで色の滑らかさや階調を保ちやすくなります。しかし公開先がsRGBの場合、最終出力時に「sRGBへ変換」する処理を忘れると色がくすんだり、派手に見えたりする原因になります。
このような誤解を避けるコツは、最終出力先を最初に決めること、そしてプロファイルとモードの組み合わせを事前に確認することです。さらに、モニターのキャリブレーションと照明環境も色の見え方を左右する大きな要因です。
難しく感じるかもしれませんが、基本の考え方はとてもシンプルです。データの「色の辞書」と「表示の約束事」を分けて考え、最終的にどの空間で公開するのかを決めるだけで、多くのトラブルが減ります。これからも写真やデザインを学ぶときには、自分が何をどう見せたいのかを軸に、プロファイルとモードを使い分けていきましょう。
ねえ、今日はカラープロファイルとカラーモードの話で、空想の友達と雑談風に深掘りしてみるよ。まず、色はデバイスごとに見え方が違うから、写真部では『この色はどの空間で作るべきか』を決めるところから始まる。カラープロファイルはその“辞書”の役目、カラーモードは“表示のルール”の役目。話は続く。ある日、私がスマホとプリンタで同じ写真を開くと、同じデータでも色が違って見える。どうして? それはプロファイルとモードの設定が統一されていないから。そこで私たちはまずウェブ用にはsRGB、印刷にはプリンタのICCを使う前提で作業を進めるよう心掛けた。色を正しく伝えるには、データの出力先を先に決め、次にその出力先の要求に合わせてプロファイルを適用する、という順番を守るのがコツだ。さらに、モニターをキャリブレーションしておくと、現場の人と同じ感覚で色を判断できるようになる。こうした地道な積み重ねが、写真やデザインの“色のズレ”を減らす鍵になる。
前の記事: « 縦横比と解像度の違いを徹底解説!写真と動画の使い分けガイド





















