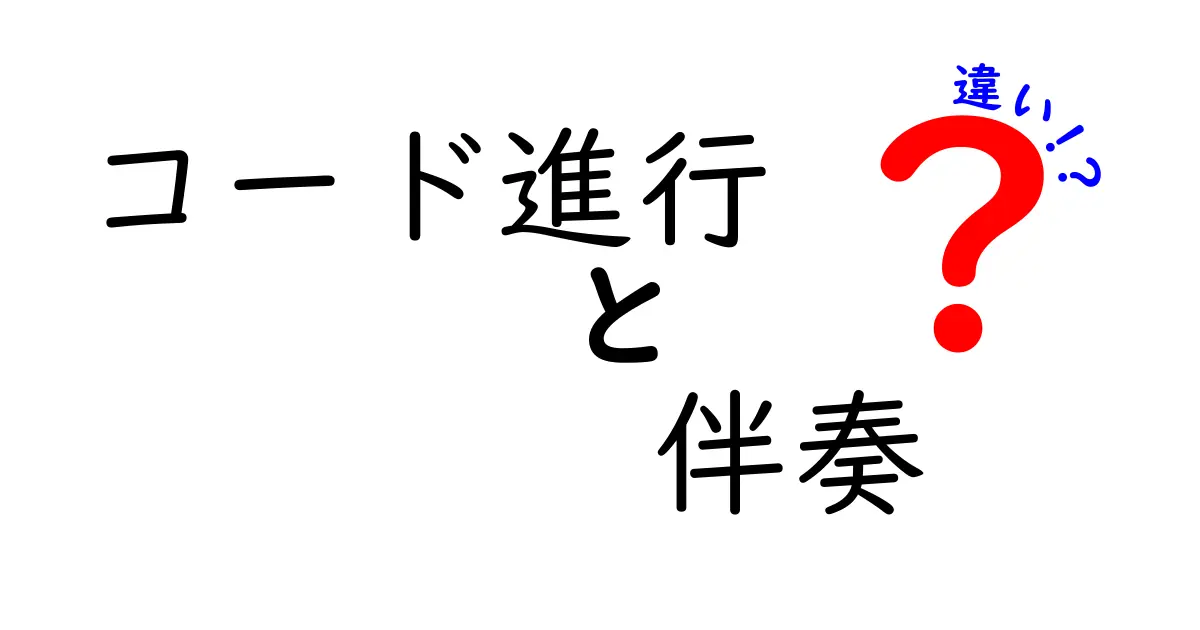

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
コード進行と伴奏の違いを正しく理解するための前提
コード進行は曲の和声的骨格を作るもので、主に和音の順番と機能で構成されます。C majorのような長調-keyを選ぶと、聴く人は安定感を感じやすく、A minorのような短調-keyに進むと切なくなったり緊張感が生まれたりします。コード進行は歌のメロディがどこへ進むべきかの道しるべになる呼吸のリズムと似ており、曲の方向性を決める指針になります。ここで覚えておきたいのは「主和音・属和音・下属和音」などの機能の概念です。主和音は曲の帰結点、属和音は次の主和音へと導く動力、下属和音は新しい方向性を示す。これらを組み合わせると、自然な流れが生まれます。
伴奏はこの和音の“声をつける”役目を持ち、リズムと音色で聴覚的な厚みを作ります。単に和音を鳴らすだけでなく、左手のベースラインや右手のコードブロック、アプローチ音、アルペジオなど多様な表現を使って、曲全体の雰囲気を決定します。大切なのは伴奏がメロディを壊さず、むしろ支える形であること、そしてテンポやスタイルに応じて軽快にも落ち着かせることができる点です。
コード進行とは何か、基本のしくみを押さえる
コード進行は数ある和音の並びのことですが、同じ和音でも位置や転回、ボイシングによって響きが変わります。小学生でもわかるように言えば、コード進行は曲の“道順”で、最初にC、次にG、次にAm、最後にFのように曲が進むと曲の雰囲気が変わります。ここで重要なのは“機能”という考え方で、どの和音が曲の安定した終点を作るか、どの和音が次の和音へと橋渡しをするかを理解することです。実際の曲を聴くと、同じ音符でも和音の順序で聴こえ方が違います。これは歌の歌詞と同じく、言い回しが変わることで意味が変わるのと似ています。
伴奏とは何か、音の支え方とリズムの役割
伴奏はメロディを取り巻く“背景の演奏”です。ベースの動きが低音で曲の土台を作り、コードブロックが和音の厚みを生み、時にはアルペジオで空間を作ります。リズムパターンは曲の速さやノリを決め、それによって聴く人の体の動きが変わります。例えば4拍子の曲では、左手のベースを2拍ごとに動かすパターンと、8分音符で細かく刻むパターンがあります。どちらも同じコード進行を使っていても聴こえ方が大きく異なるのです。伴奏はあくまでメロディを引き立てる役割、そのバランスを崩さないことが良い伴奏のコツです。
実践的な聴き分けと練習のコツ
聴くときにはまず“コード進行の流れ”を頭の中で追い、次に“伴奏のリズムと音色”を聴く練習をします。たとえば好きな曲のサビだけを取り出して、コード進行を紙に書き出してみると、和音の変化が見えてきます。次に同じ曲の伴奏だけを聴くと、どのリズムパターンが使われているか、どの音色が厚みを出しているかが分かります。練習法としては、まずコード進行を固定して伴奏を自由に変えてみる方法、そして逆に伴奏のテンポを変えずにコード進行だけを変える方法の2つを繰り返すと効果的です。
また、実際の演奏では指の動きと耳の感じ方を同時に鍛えることが重要です。両手の動きを分解して練習し、最後に合わせることで全体のバランス感覚が養われます。
放課後のソファで友達と音楽の話をしているとき、コード進行の話題が飛び交いました。コード進行は曲の骨格、伴奏は衣装のようだね、という結論に落ち着きました。私はこう思う、コード進行は聴く人の心の位置情報を決める道順。ドミナントが来たときの背筋の伸び方、サブドミナントで新しい気分になる瞬間、これを理解しておくと作曲の際に無意識に迷いが減る。友人は“伴奏は空気感を作る”と整理してくれて、それぞれの役割を分けて考えると、曲作りのステップが見つけやすくなると納得しました。
次の記事: メサイアの楽譜の違いを徹底解説|聴き方と読み方が変わる理由 »





















