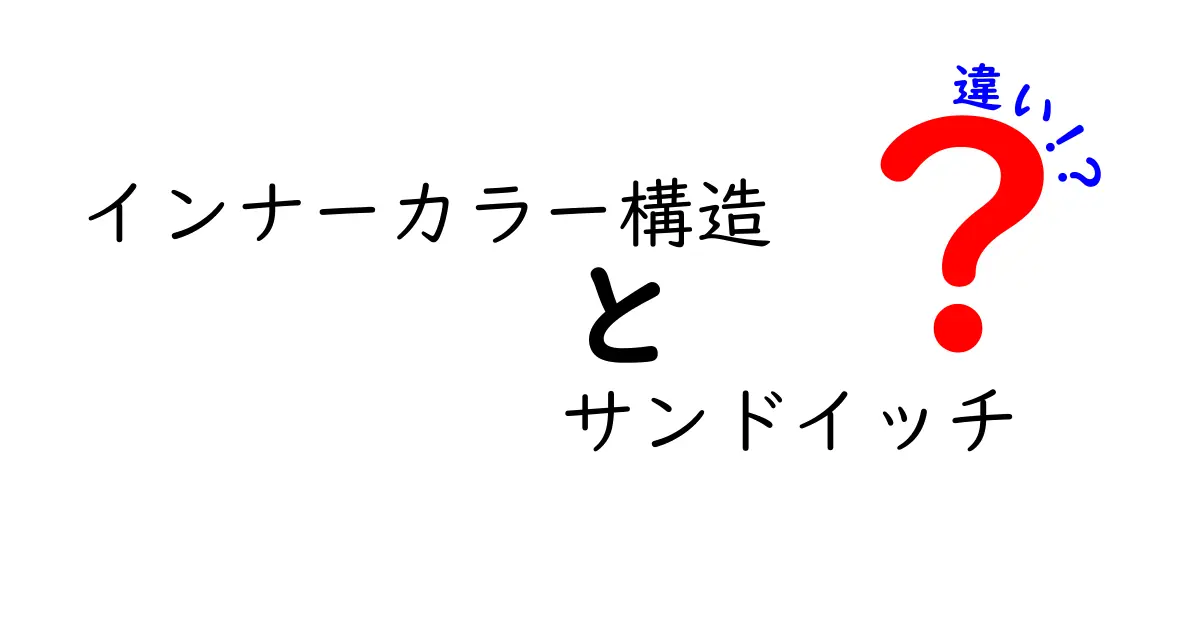

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
インナーカラー構造とは何か?その基本を深掘り
インナーカラー構造は、物体の内部にある色の配置や階調の作り方を指す考え方です。デジタルデザインや印刷、アートの分野でよく使われ、外見の色だけでなく内部の色の広がり方を意識して設計します。
この考え方を使うと、同じ形でも内側の色の変化によって“深み”や“立体感”が生まれ、観る人に強い印象を与えやすくなります。
例えばゲームのキャラクターの影の付き方一つとっても、表面の色だけでなく内側の陰影がどう見えるかを計算して描くと、よりリアルに近づきます。
ここで大切なのは、内側の色を決めるときに外側の色とぶつからず、自然につながるようにすることです。
そのためには、色相・明度・彩度といった基本の色要素を組み合わせ、グラデーションの幅を調整していく練習が必要です。
- 実践ポイント: 内部の光源を意識して、同じ色相でも明度を少しずつ変えると深みが増します。
- 初心者は小さな図形を使って、内側の色がどう見えるかを観察する練習から始めましょう。
この考え方は、色の世界を広く理解する第一歩となるはずです。
サンドイッチとは何か?材料と作り方・色の話
サンドイッチは、パンとパンの間に具材を挟んだ食品の基本形です。見た目の色だけでなく、具材の取り合わせによって味や食感が大きく変わります。
私たちが身近に食べる朝ごはんの定番から、ランチのメニューまで、工夫次第で無限の組み合わせが生まれます。ここで覚えておきたいのは、色も構造の一部だということです。焼いたパンの焦げ色、野菜の緑、チーズの白やオレンジなど、材料の色が視覚的な楽しさを作ります。
また、サンドイッチを作るときには「味だけでなく見た目のバランス」も大切です。例えば、濃い色の具材と淡い色のパンを組み合わせると、全体が引き立ちます。パンの種類や具材の厚さ、ソースの有無が、食感の違いを生み出し、食べるときの満足感に直結します。
初心者でも挑戦しやすい基本の作り方は、パン・具材・パンの順で積み重ね、最後に軽く押して形を整えることです。具材の配置を工夫すれば、断面の色のコントラストも楽しく作れます。
コツ: 色のコントラストを意識して、野菜の緑とチーズの黄色、パンの茶色の組み合わせをバランス良く選ぶと、見た目も味も良くなります。
サンドイッチは、日常の中で気軽に色と構造のバランスを学べる良い教材です。
この2つは同じ「色を使う」という点を持ちながらも、使い方や目的が大きく異なる例です。
一方は内側の色の設計で、もう一方は食材の色と組み合わせを楽しむ実践です。
違いを理解して使い分けると、デザインの創造力と食の楽しさの両方を高められます。
ねえ、インナーカラー構造って難しそうだけど本当に大事なのは“中の色の組み方”なんだよね。外側の色がきらきら光っていても、中身の色の連続性が崩れてしまうと深さが出ない。友達と話していても、同じ青い色でも内側を少し暗めにしてグラデーションをつくると、冷たい感じが強く見えるけど温かさも同時に残せるんだ。サンドイッチの話にも似ていて、パンの色だけでなく中の具の色をどう組み合わせるかが味と見た目を決める。つまり、色の“内側”を見る訓練をすると、デザインも料理ももっと楽しくなるんだよね。





















