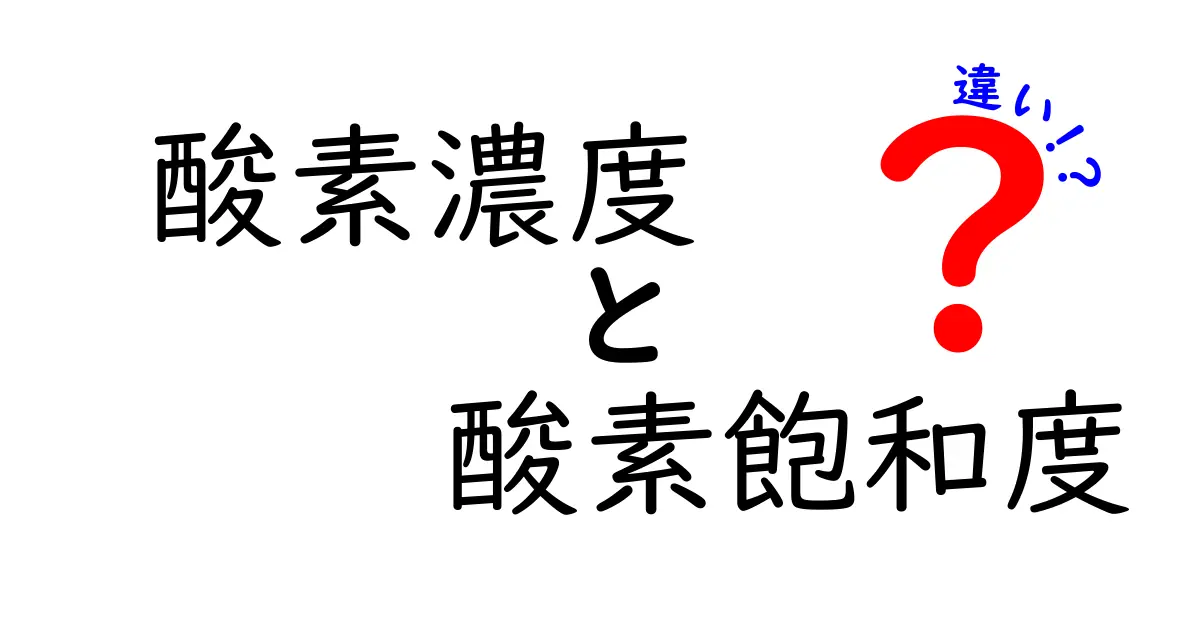

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:酸素濃度と酸素飽和度、似て非なる2つの指標
酸素濃度と酸素飽和度は名前が似ているため、つい同じものだと勘違いしがちです。しかし、体の中で実際に意味するものは異なります。酸素濃度は、空気中や呼吸しているガスの中に含まれる酸素の割合を示す指標が一般的です。室内の空気は約21%の酸素で成り立っています。これに対して、酸素飽和度は血液の中のヘモグロビンがどれだけ酸素と結合しているかを示す割合です。教育現場や医療現場ではこの二つは別の意味として使われ、患者さんの呼吸状態を評価する際には、酸素濃度と酸素飽和度の双方を確認することが重要です。
日常生活の場面でも、深呼吸をしているときの呼吸の速さや深さは酸素飽和度の変化と関係しますが、空気中の酸素不足を直接的に示すのは酸素濃度ではなく酸素飽和度です。たとえば高地での運動時には呼吸の調整が必要で、酸素濃度が低い環境下で体がどう反応するかを見ることで、体力の見極めにもつながります。
このように、酸素濃度と酸素飽和度は「どの場面で測るべきか」「何を意味するのか」が異なる指標です。正しく使い分けることは、健康管理や緊急時の対応をスムーズにする第一歩です。
具体的な違いと測定の仕方:日常と医療の場面での使われ方
ここでは、二つの指標が日常生活と医療現場でどう使われるかを詳しく見ていきます。
まず酸素濃度はガスの組成を測る基本的な数値で、空気中や人工呼吸に用いる混合ガスの中の酸素の割合を表します。
この値はガス分析計や近代的なセンサー、計量機器で測定され、室内の酸素濃度は通常約21%、高地や閉鎖空間では低下することがあります。
次に酸素飽和度は血液のヘモグロビンが酸素と結合している割合を示す指標です。
代表的な測定方法はパルスオキシメータで、指先などに小さなセンサーを取り付けて動脈血に含まれる酸素の割合を推定します。
健康な大人のSpO2は通常95〜100%の範囲にあり、低下すると息苦しさや疲労、頭痛につながることがあるので、適切な対応が求められます。
表を見れば、どちらが体内の“酸素の状態”を、どちらが空気の“酸素の量”を示しているかが分かります。
実際の生活での活用例として、スポーツ時の呼吸法の練習、山登り前の酸素環境チェック、救急時の初期評価などが挙げられます。
理解を深めるコツは、「酸素濃度は景色のように外部の空気の状態を示す指標」、酸素飽和度は体内の状態を示す指標として覚えることです。
友人A: 酸素濃度と酸素飽和度って同じものだと思ってた。友人B: 実は違うんだ。酸素濃度は外の空気やガスの酸素の割合、酸素飽和度は体内の血液がどれだけ酸素と結合しているかの割合。山道を登ると空気が薄くなるから酸素濃度が低く見えるけど、体は酸素飽和度を保つように呼吸と心臓の動きを調整する。だから両方のデータを見て初めて、今の体の状態が分かるんだ。日常生活でも、運動や高地での活動時にはこの二つを正しく読み解く練習をすることが大切だ。さらに詳しく学べば、健康管理や救急時の判断も速く正確になります。





















