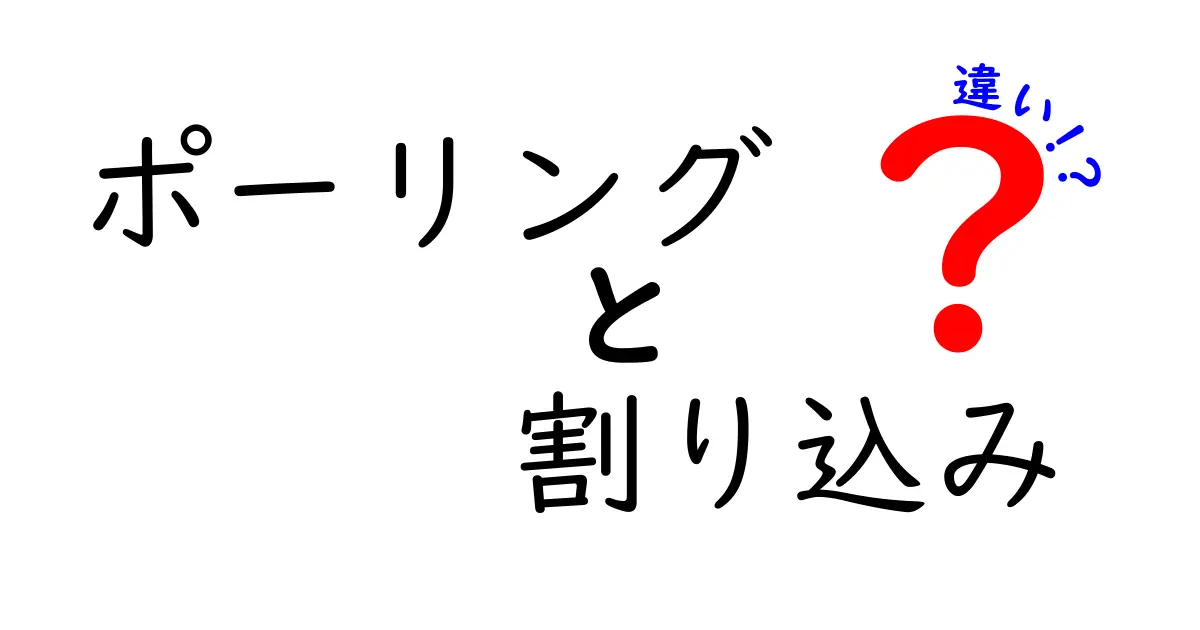

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ポーリングと割り込みの違いを徹底解説:いつ使うのが正解?
ポーリングと割り込みは、コンピューターが外部機器や入力信号の状態をどうやって知るかという点で大きく異なる考え方です。ポーリングは機器の状態を自分のペースで定期的に問い合わせる方法で、CPUが一定の時間間隔ごとに「今この状態か」を自分で確認します。割り込みは外部の機器がイベントを発生させたときに、即座にCPUへ通知して処理を開始する仕組みです。この違いは、実際のアプリケーションでの実行順序、反応性、エネルギー消費、そして設計の難しさに大きな影響を与えます。ポーリングは実装が比較的単純で、プログラミングの流れを追いやすい点が魅力です。しかし、機器を待つ間、CPUは他の作業をしていない時間が生まれやすく、CPUの使用率が高くなりがちで、電力消費や熱にも影響します。割り込みはイベントが起こるたびに処理を始めるため、遅延を小さく抑えやすく、CPU資源を効率的に使えるのが大きな利点です。一方、同時に発生する複数のイベントや、長い処理時間を持つISR(割り込みサービスルーチン)をどう設計するかが難所になります。現代の多くのシステムは、両方の考え方を組み合わせて使うハイブリッド設計を取り、リアルタイム性の要件と資源の制約を天秤にかけながら適切な方法を選んでいます。ここから先は、より具体的な使い分けのコツと、場面別の利点・欠点を見ていきましょう。
基本の考え方:ポーリングとは何か、割り込みとは何か
まず、二つの基本的な考え方をしっかり区別することが大切です。ポーリングは、CPUが自ら定期的に状態を確認し続ける作業です。待機時間が長いほど、実際には「今この状態かどうか」という問いに対してCPUが繰り返し割り当てられる時間が増え、電力消費とCPUリソースの浪費につながります。
これに対して、割り込みは外部イベントが発生した瞬間に割り込み信号を受けて、現在実行中の処理を一時停止して割り込み処理へ切り替えます。割り込みの設計では、競合状態の回避、非同期性の管理、ISRの長さを短く保つ工夫が重要です。実世界の話としては、学校のベルが鳴ったときに教室の計画を変更する「割り込み方式」は、事前の準備がなくてもすぐに対応できます。一方、待機電車を見張るような待機ルーチンは、ポーリングに近い発想で動く場面が多く、シンプルさと引き換えに遅延と消費電力が課題となります。
つまり、リアルタイム性と資源効率のどちらを重視するかで、使い分けの判断が変わってくるのです。
放課後、友だちとカフェで『ポーリングと割り込みの違いって何?』と雑談していました。私はこう説明しました。ポーリングは機械の状態を自分のペースで繰り返し確認する作業で、常にCPUが“今この状態か”を問いかけます。その一方で割り込みは、外部のイベントが発生した瞬間にCPUへ知らせる仕組みです。私たちのスマホの通知の仕組みを思い浮かべるとわかりやすいです。ポーリングは待機時間が長いほどCPUが自分の都合で動き続けるため、エネルギーと計算資源を多く消費します。一方、割り込みはイベント時だけ処理を走らせるので、効率は良いですが、同時に複数のイベントが同時に来たときの順序やデータの整合性を管理する難しさを感じます。例を出すと、ゲーム機のコントローラの入力が連続して来る場合、割り込みを使えばすぐ反応できますが、入力が途切れたときの待機時間をどう抑えるかが課題になります。このあたりを理解すれば、リアルタイム性と資源のバランスをとる判断が自然に身についてくるはずです。





















