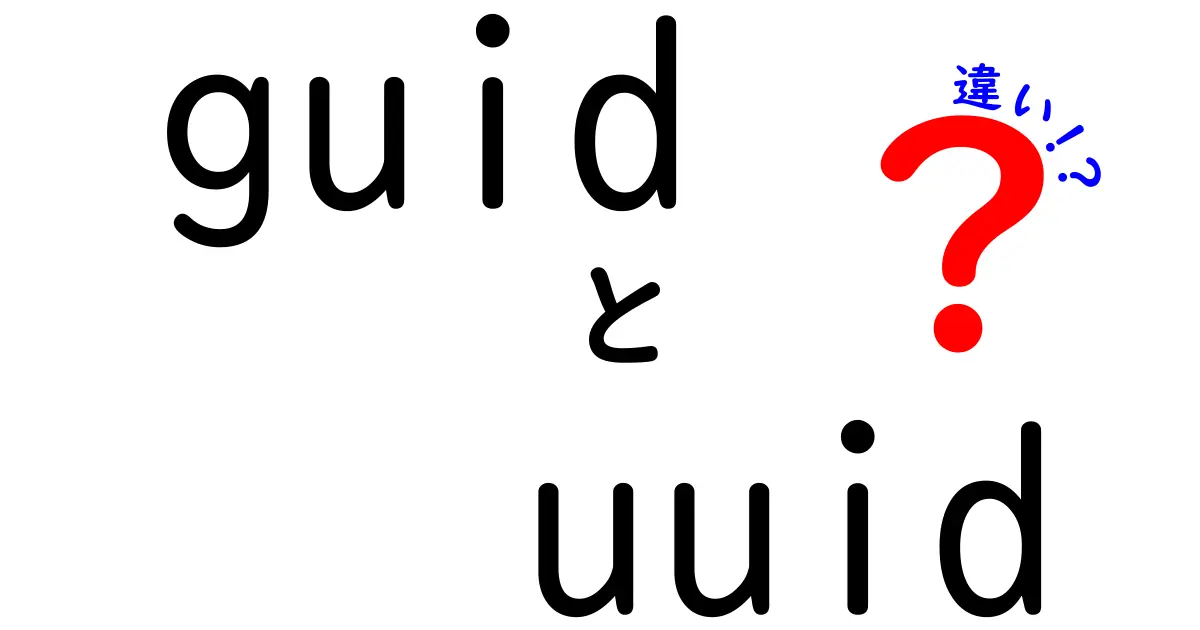

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:GUIDとUUIDの基本概念
GUIDとUUIDはどちらも128ビットの識別子で、世界中で一意性を保証するための値です。
GUIDは主にWindowsの開発環境で使われる名称で、UUIDは Universally Unique Identifier の略で RFC 4122 という国際規格に基づいています。
「違い」というとき、実務上はほとんど同じ意味で使われることが多いのですが、規格の成り立ちや採用する場面の違いを理解しておくと混乱を減らせます。
まず覚えておきたいのは両者が基本的には同じ128ビット長の識別子であるという点です。その長さと表現のルールはほぼ同じで、実質的な機能は同等です。
ただしGENERATEのアルゴリズムや命名の由来、実装の場所によって用語が異なります。
この記事では GUID と UUIDの定義の差、表現の違い、そして実務での使い分けを分かりやすく整理します。
違いを理解するための具体的な比較ポイント
まず最初に押さえるべき点は規格と使用環境の違いです。Guid は Windows 系の開発環境でよく使われる名称で、内部的には UUID と同じく128ビットの識別子です。
一方 UUID は RFC 4122 で定義された国際規格で、広く多様なプラットフォームで利用されます。
このため表現形式を崩さない限り、ほとんどの言語やデータベースで相互運用が可能です。
次に生成方法とバージョンについてです。UUID にはバージョン1(時刻ベース)やバージョン4(ランダム)などがあり、それぞれの生成元情報が含まれることがあります。
GUID もバージョン付きの生成方法を提供しますが、実装言語やライブラリによって呼び方が異なることがあります。
この点が混乱の原因になることがあるため、作成時には「どの規格で作られているか」を確認することが大切です。
以下の表は両者の代表的な違いを簡潔に比較したものです。
実務での使い分けと注意点
実務の現場では、GUIDとUUIDのどちらを選ぶかは「どの環境で使うか」「どのシステム間の連携を考慮するか」で決まります。
新規開発でクロスプラットフォームを想定する場合はUUIDを選ぶのが無難です。
データベースのキーとして扱う場合には、長さや検索性能には影響がほとんどなく、ユニーク性を保証する仕組みとして適しています。ただしデータベースの文字列型の長さ制限やインデックスの作成コストを考慮する必要があります。
アプリケーションの localization やローカル仕様が混在する場合は GUID という名称が使われることが多いですが、実際には内部的な構造は UUID と同じため、適切なライブラリを選択して扱うことが重要です。
最後に重要なのは「識別子をどのように送受信するか」です。ネットワーク越しの通信やファイルのメタデータとして渡す場合、文字列長やエンコードの影響を受けやすいため、文字列として安全に扱える形式に正規化しておくことが必要です。
このような点を意識しておくと、後から別のシステムへ移行する際の手戻りを大幅に減らすことができます。
- UUID を選択する場面はクロスプラットフォームの連携や標準化を重視する場合が多い
- GUID は Windows 系の環境での互換性や既存コードの整合性を維持する際に使われやすい
- どちらを使っても長さは同じ128ビット、表現はハイフン付きの形式が一般的
ある日プログラミング教室でAとBが GUID と UUID の違いについて雑談をしていた。AはWindows 系の開発をしていて GUID という言葉になじみが深い。BはRFC 4122 に基づく UUID を使う場面が多い。二人はまず128ビットの識別子という共通点を確認し、表現形式が同じである点を指摘する。次に使われる場面の違いを議論する。データベースの主キーとしての互換性や、異なるシステム間の識別子の受け渡しの際の注意点を話し合う。最後に重要なのは規格名より実際の運用であると合意し、UUIDを選ぶ場面を整理して会話を締めくくる。





















