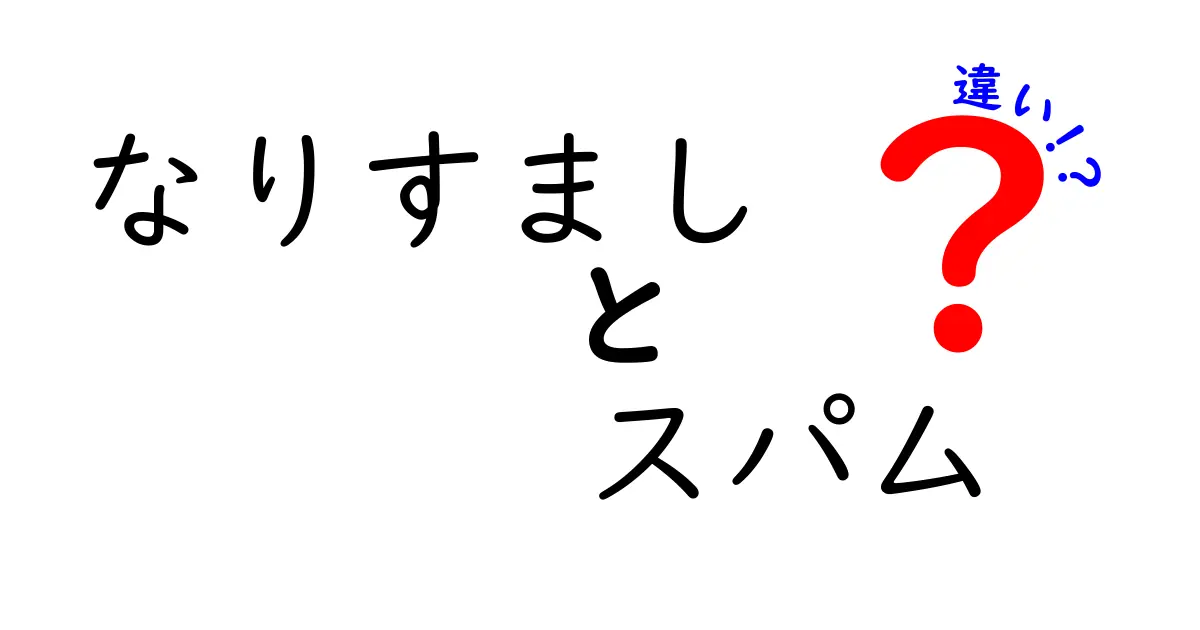

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
なりすましとは何か?
インターネットを使っていると、「なりすまし」という言葉を聞くことがあります。
なりすましとは、誰かが他の人になりすまして、悪意ある行動をすることを指します。
たとえば、メールの送信者名を偽ったり、SNSのアカウントを乗っ取って本人になりすましたりすることです。
なりすましは被害者の信用を失わせたり、詐欺などの犯罪に使われるため非常に危険です。
インターネット上で「自分はログインしていないのに、誰かが自分になりすまして行動をしている」といった問題に遭遇したことがある人もいるでしょう。
なりすましは相手を騙して情報を盗み取ったり、悪いことをさせたりする目的で行われます。
例えば「なりすましメール」は、送信元が本物に見えるメールで、そこに記載されたリンクをクリックするとウイルスに感染したり、詐欺サイトに誘導されたりするケースが多いです。
なりすましが増えている背景には、メールアドレス偽装やアカウント乗っ取りの技術が進んだこともあります。
だからこそ、自分のパスワードをしっかり管理したり、怪しいメールやメッセージは開かないよう注意が必要です。
スパムとは?どんなものか?
スパムとは、 簡単に言うと大量に送られてくる迷惑メールや、宣伝・広告のことで、受け取る相手にとって役に立たず、迷惑なものが多いのが特徴です。
例えば、身に覚えのない商品の勧誘メールや、怪しげなリンクが記載されたメールをイメージしてください。
スパムメールは「送り手が特定の人ではなく、多数の人に一斉に送る」ことが多いです。
また、スパムは単なる宣伝メールだけでなく、悪意ある内容が含まれていることもあり、ウイルス感染や個人情報の漏えいなどのリスクが高いです。
そのため、メールサービスやSNSでスパム対策(迷惑メールフィルターなど)がされています。
スパムの特徴は、「大量」「承諾なしの一方的な送信」「宣伝や広告が目的」であり、これらの行為はネット利用者にとって非常に迷惑です。
具体的には次のようなものがスパムにあたります。
- 無断で送られる商品やサービスの広告メール
- 詐欺を狙った怪しいリンク付きのメール
- SNSで無差別に送られる宣伝メッセージ
スパムは被害を減らすために、メールやメッセージで見知らぬ送信者からのものは安易に開かないことが基本です。
なりすましとスパムの違いをわかりやすく解説
「なりすまし」と「スパム」はよく混同されやすいですが、基本的に違うものです。
まずなりすましは、“他人を騙すこと”が目的で、たとえばあなたになりすまして悪いことをする行動です。
一方、スパムは“大量に迷惑な情報を送ること”自体が問題で、送り手の目的は主に宣伝や詐欺です。
違いを表にまとめると、次のようになります。
| ポイント | なりすまし | スパム |
|---|---|---|
| 目的 | 他人を騙して信用を失わせる、詐欺や不正行為 | 宣伝や大量送信による迷惑行為 |
| 手法 | 他人の名前やアカウントを偽る | 大量のメールやメッセージを送る |
| 特徴 | 本人になりすまし騙すことに重点 | 数多くの人に送られる迷惑メッセージ |
| 危険性 | 詐欺被害や信用失墜 | ウイルス感染や詐欺へ誘導 |
また、「なりすまし」と「スパム」は同時に起こることもあります。
たとえば、スパムメールの送信者がなりすましのメールアドレスを使うこともあるのです。
そのため両方に気をつけることが安全なインターネット利用のポイントです。
いずれにせよ、怪しいメールやメッセージは開かず、疑わしいリンクをクリックしない、パスワードを複雑にするなど自己防衛が重要だと言えます。
なりすましは他人を騙すことが目的ですが、その中でも思わず名前やアカウントの変化に気づかないことがあります。例えば、有名人のアカウントが乗っ取られて偽物が投稿するケースです。これによって普通の人が混乱したり、重要な情報が誤って拡散されたり。インターネットでは“人の顔”を偽ることが簡単になってしまい、だからこそSNSの公式認証マークなどが注目されているんですね。身近なところでも、詐欺メールはなりすましが絡んでいることが多いので、日頃から送信者情報に注目してみましょう。
前の記事: « スキミングと磁気の違いとは?カードトラブルの仕組みを徹底解説!





















