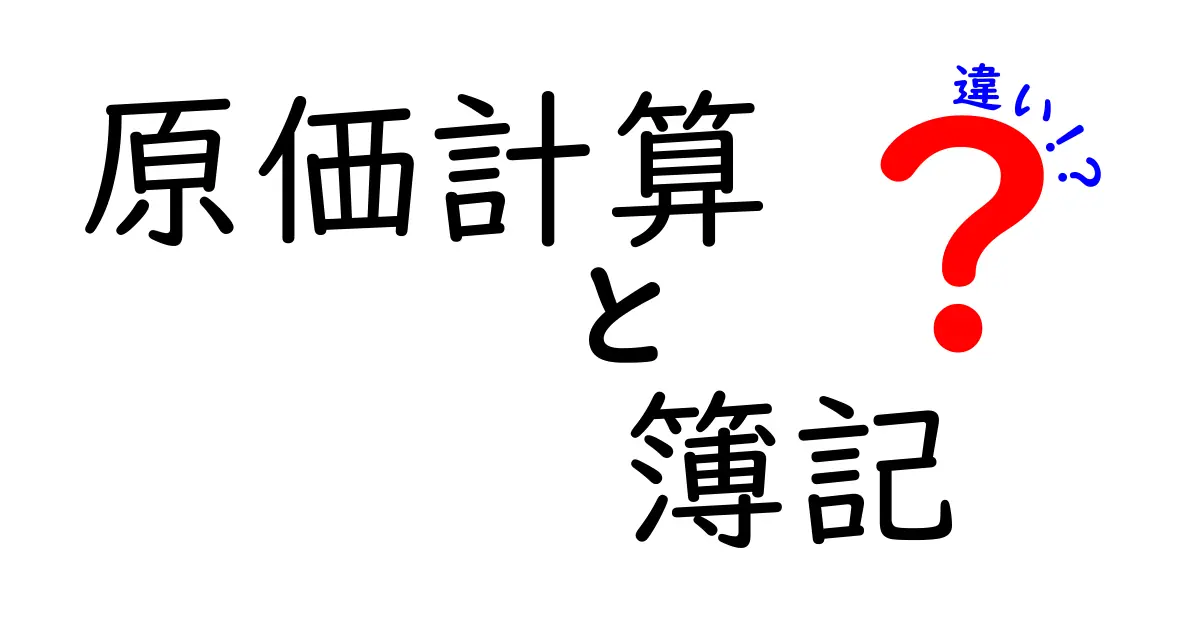

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
原価計算と簿記の基本の違い
原価計算と簿記はどちらも会社のお金の動きを管理する仕組みですが、その目的や扱う内容には大きな違いがあります。
簿記は、会社の売上や支出といったお金の取引を記録し、帳簿にまとめることです。これは税金や財務報告に必要で、会社の全体のお金の動きを整理します。
一方、原価計算は、商品やサービスを作るためにかかった費用を細かく計算する作業です。どれだけの材料費、人件費、機械の費用がかかっているのかを調べ、利益を正しく把握したり、価格を決める参考にします。
つまり、簿記は「全体のお金の流れを記録」し、原価計算は「商品やサービスのコストを詳しく分析」することが役割です。
原価計算と簿記の具体的な使い方の違い
では、実際の会社で原価計算と簿記はどのように使われるのでしょうか。
簿記は、会社が行った取引をすべて会計帳簿に分けて記録します。売上や仕入れ、人件費の支払いなど、すべてのお金のやりとりが対象です。そのデータは決算書を作るときに使われ、会社の経営状況を外部に伝えるためにも必要です。
原価計算は、例えば製品Aを作るのに材料がいくらかかり、工場で働く人の時間や機械の使用料がどれくらいかかったかを細かく計算します。こうしたデータをもとに、適正な販売価格を設定したり、コストを下げる方法を見つけたりします。
まとめると、簿記は会社全体のお金を管理し、原価計算は製品やサービスごとの費用を分析する役割があるのです。
原価計算と簿記の違いをまとめた表
ここまでの説明をわかりやすく表にまとめました。
| 項目 | 簿記 | 原価計算 |
|---|---|---|
| 目的 | 会社全体の取引記録と財務報告 | 製品・サービスの原価把握とコスト管理 |
| 対象 | すべての取引(売上、費用など) | 製品やサービスにかかる費用 |
| 使う場所 | 財務諸表作成、税務申告 | 価格設定、経営管理、コスト削減 |
| 方法 | 仕訳帳、総勘定元帳への記録 | 材料費、人件費、経費の配賦などの計算 |
| 結果 | 決算書、試算表 | 製品別原価表、利益分析 |
この表を参考に、原価計算と簿記の違いを理解しましょう。
まとめ:原価計算と簿記は連携しながら会社の経営を支える
原価計算と簿記はそれぞれ別の役割を持っているように思えますが、実際には互いに関連しています。
簿記で記録された取引のデータを基に、原価計算は細かい費用分析を行います。逆に原価計算の結果は経営の意思決定に役立ち、会社全体の財務状態を意識しながら進められています。
つまり、簿記は会社のお金の“全体図”を描き、原価計算は“細部のコスト”を理解するための手段です。どちらも経営に欠かせない大切な仕組みと言えるでしょう。
実は原価計算の中でも特に面白いのが「間接費」の扱いです。間接費とは、例えば工場の電気代や管理部門の人件費のように、直接商品に結びつけにくい費用のこと。
どうやってこれらを商品の原価に割り振るかがポイントで、色々な方法があるんですよ。『配賦(はいふ)』という考え方で、適切にコストを分ける技術が原価計算には必要です。
この仕組みがしっかりすると、経営者は無駄を見つけやすくなり、会社の利益をアップさせる手助けができるんです。





















