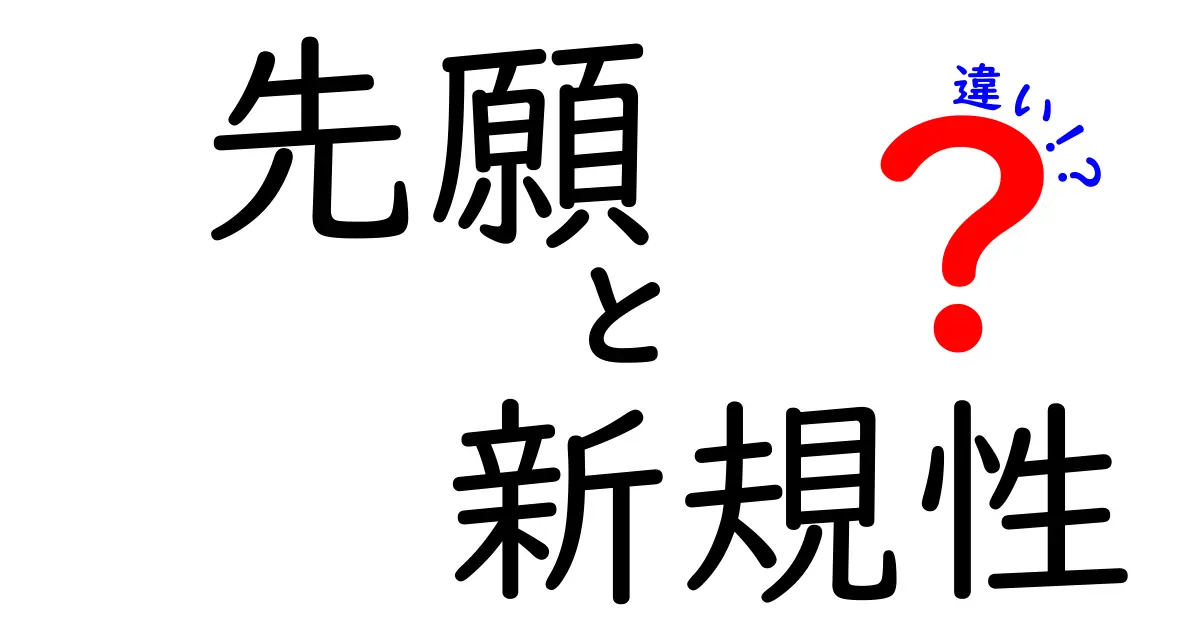

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
先願とは何か?
特許の世界でよく聞く言葉の一つに「先願(せんがん)」があります。これは簡単に言うと、誰よりも早く特許の申請を出した人が優先権を持つというルールです。つまり、同じような発明が複数あった場合、最初に特許を申請した人だけがその発明の独占権を得られます。
例えば、あなたが新しいスマホの技術を考えたとします。もしほかの誰かも同じような技術を発明していても、最初に特許を申請した人だけがその権利を持つので、他の人はその技術を勝手に使えなくなります。これが先願主義と呼ばれる特許の重要なルールです。
特に日本は先願主義を採用している国で、申請した順番が特許権を得るかどうかのポイントになります。
ですから、アイデアを思いついたらなるべく早く特許申請を行うことが大切です。これが先願の意味とその重要性です。
新規性とは?
次に「新規性」という言葉について説明します。新規性とは、簡単に言えばそれまでに世の中に存在しなかった新しい発明であることを意味します。
特許をもらうためには、その発明がすでに公開されているものと違うこと、つまり誰も知らない新しいものであることが必要です。これを新規性の要件と言います。
例えば、もし同じ発明が雑誌やインターネットなどで公開されていた場合、その発明には新規性がなくなってしまいます。そうなると、特許をもらうことはできません。
このように、新規性は発明の独自性や新しさを判断する大切なポイントです。
先願と新規性の違いとは?
「先願」と「新規性」は特許をとるための大切なルールですが、意味や役割が違います。
先願は申請した順番の問題であり、一番早く申請した人が権利を得るというタイミングのルールです。
一方、新規性はその発明自体が本当に新しいかどうか、つまり内容のルールです。
つまり、どんなに早く申請しても、その発明が新しくない(すでに知られているもの)場合は特許は認められません。逆に、発明が新しかったとしても、もし他の人が先に申請していたら、その後の申請は認められません。
この2つは特許をもらうために両方クリアしなければならない大事なポイントなのです。
先願と新規性の違いを表で比較
| ポイント | 先願 | 新規性 |
|---|---|---|
| 意味 | 早く特許申請をした順番のルール | 発明が世の中に新しいかどうかの判断 |
| 役割 | 申請したタイミングによる優先選定 | 内容の独自性・新しさの判断 |
| 重要性 | 最初に申請しなければ権利をもらえない | 新しくなければ特許は認められない |
| 例 | 複数の人が同じ発明をした場合の申請の早さ | すでに雑誌やネットで公開されているかどうか |
まとめ:特許を取得するために必要なこと
特許というのは、発明を守るための大切な制度です。そのためには先願と新規性という2つのポイントをしっかり理解し、両方をクリアする必要があります。
まずは、考えたアイデアや発明をできるだけ早く特許庁に申請することが先願を守るポイントです。そして、発明が本当に新しいものであるかを自分で調べたり専門家に確認してもらうことで新規性を確かめることが重要です。
これらをしっかり押さえておけば、あなたの発明が世界に通用する権利として守られやすくなります。
特許の世界を理解して、あなたのアイデアをしっかり守りましょう!
「新規性」って聞くと難しそうですが、実はとても大事な発明の『新しさ』のことなんですよね。たとえば、もしもあなたがアイデアを思いついても、それと同じことがすでに新聞やインターネットで公開されていたら、それはもう『新しい』とは言えません。だからそういった情報のチェックをすることは、特許申請の前にめちゃくちゃ重要なんです。意外と身近で日常的な情報があなたのアイデアの“新規性”を左右しているんですよね。これがわかると、発明って本当に面白くなりますよ!
前の記事: « 請求の範囲と請求項の違いとは?特許の基本用語をやさしく解説!





















