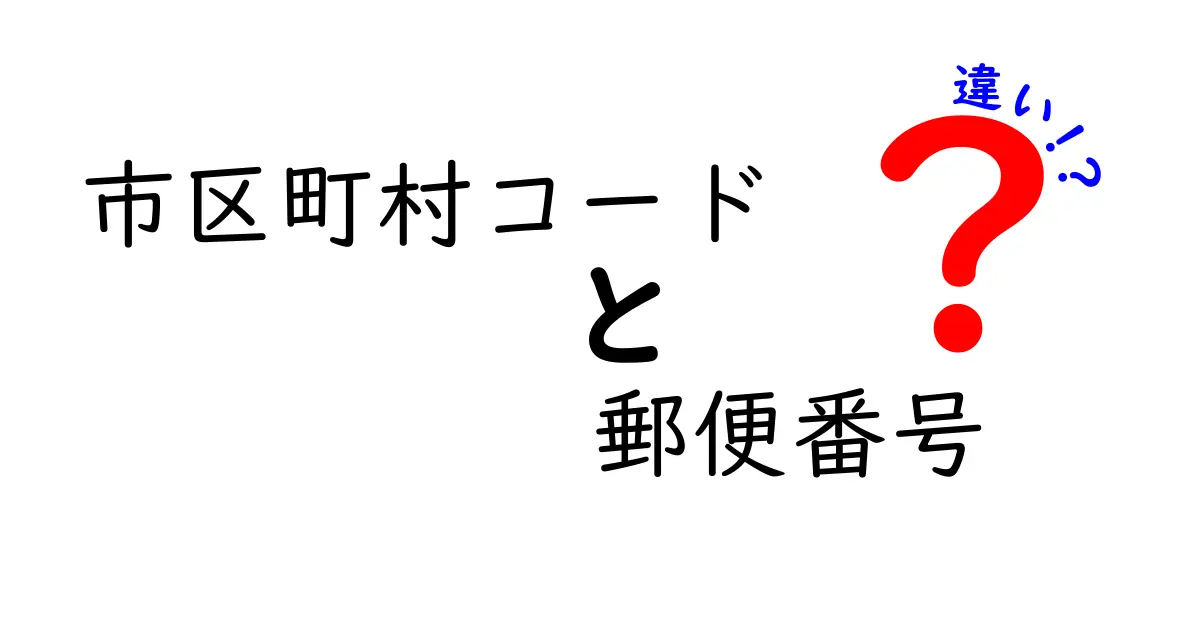

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
市区町村コードとは何か?
市区町村コードとは、日本の地方自治体である市区町村にそれぞれ割り当てられた6桁の数字のことです。このコードは総務省が管理していて、目的は行政や統計の場面で各自治体を正確に識別することにあります。たとえば、北海道札幌市、東京都新宿区、大阪市など、それぞれに固有のコードがあるため、データを整理したり分析したりする際に便利です。
市区町村コードは、「都道府県コード(2桁)」+「市区町村コード(4桁)」が一体となっており、合計6桁で表されます。例えば、東京都新宿区のコードは「13104」といった感じです(実際は正式に割り当てられているコード)。
このコードは郵便番号とは違い、実際の住所表記や郵便物の配達に直接使われるわけではなく、行政手続きや国の統計調査で主に使われています。
ですから、普段の生活ではあまり聞かない言葉ですが、役所のシステムや統計データでは不可欠なコードなのです。
郵便番号とは何か?
郵便番号は正式には「郵便番号制度」に基づき、日本郵便が割り当てている7桁の番号です。これは住所の中でも郵便物を迅速かつ正確に配達するために使われます。
郵便番号は3桁+4桁に分かれており、例えば「100-0001」は東京都千代田区の代表的な郵便番号の一つです。郵便番号は街区や建物ごとに割り当てられ、同じ市区町村内でも複数の郵便番号が存在することが多いです。
郵便番号は住所を書くときに使うもので、郵便物のラベルや宅配便の配送先情報などで重要な役割を果たします。
つまり、郵便番号は配達先を特定して郵便物を届けるための番号で、一般の方に一番馴染みのある番号と言えます。
市区町村コードと郵便番号の違いとは?
市区町村コードと郵便番号は、どちらも数字で表される住所に関わるコードですが、その役割も仕組みも大きく違います。
以下に主な違いをまとめました。
| 項目 | 市区町村コード | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 桁数 | 6桁(都道府県2+市区町村4) | 7桁(3桁-4桁) |
| 管理機関 | 総務省 | 日本郵便 |
| 主な目的 | 行政・統計目的 自治体識別 | 郵便物配達の効率化 |
| 適用範囲 | 市区町村単位 | 街区や建物単位 |
| 一般利用 | あまり知られていない | 住所記入や配達で日常的に使う |





















