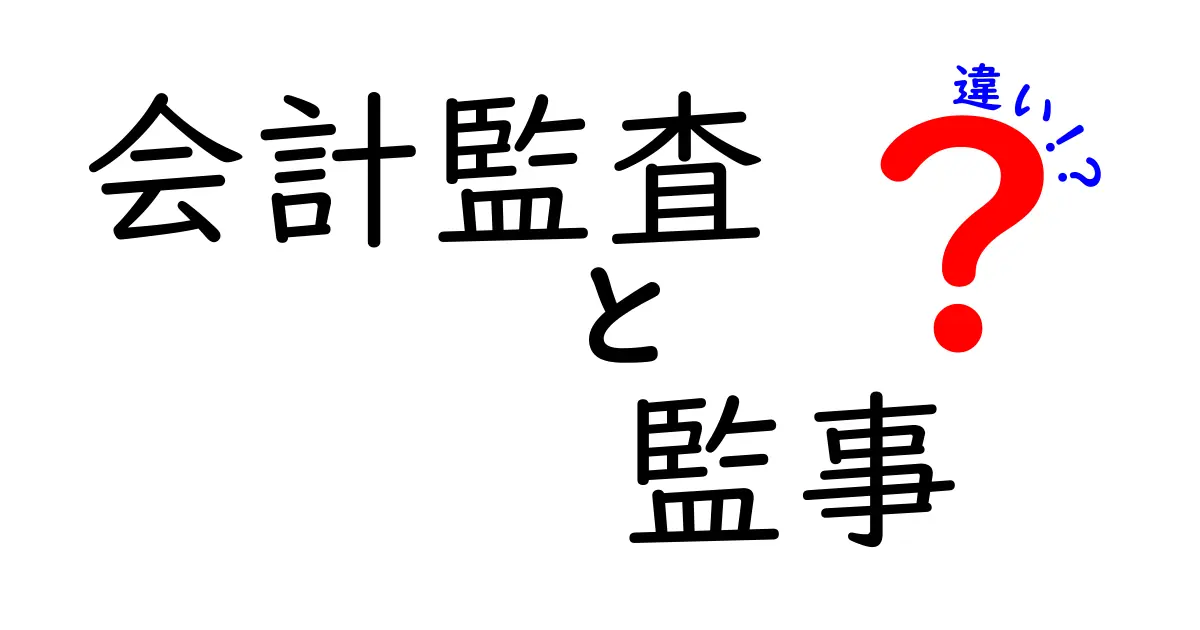

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
会計監査と監事は何が違う?基本の役割を理解しよう
会社や組織で資金の流れやお金の管理をチェックするために「会計監査」と「監事」という言葉がよく出てきます。どちらもお金の動きを見ているという点で似ていますが、じつは役割や責任、立場が違います。まずは基本的な違いから見ていきましょう。
【会計監査】は会計の専門家、たとえば公認会計士などが行う監査です。会社が作った決算書が正しくて信頼できるかどうかをチェックします。外部の専門家が第三者としてチェックするため、会社の内側からの影響を受けにくく、公正な審査が期待されます。
一方、【監事】は会社や組織の内部にいる役員の一つ。取締役会や他の経営陣から独立した立場で、会社の業務や会計の状況を監視し、問題があれば指摘します。監事の役割は法律で決まっていることが多く、会社の規模や種類によって設置が義務付けられている場合もあります。
つまり、会計監査が外部のプロの仕事なのに対して、監事は会社内部の監視役というのが大きな違いです。
具体的な違いを比較表でチェックしよう
言葉だけだと分かりにくいので、以下の表で「会計監査」と「監事」の違いを比較してみましょう。
| 項目 | 会計監査 | 監事 |
|---|---|---|
| 役割 | 決算書などの会計情報の正確性を専門家がチェック | 会社の業務や会計の監視と報告を行う内部役員 |
| 立場 | 外部の公認会計士や監査法人 | 会社内部の監事役員 |
| 設置の義務 | 会社の規模や法律により必要 | 株式会社など一定規模の会社で法律上設置義務あり |
| 報告先 | 株主総会や規制当局 | 株主総会 |
| 権限 | 監査に基づく意見を表明する権限 | 業務の調査権限や異議申し立て権限 |
この比較でわかるように、会計監査は数字の専門家が客観的にチェックし、監事は会社の運営上の問題がないか内側から見守る役割です。
なぜ会計監査と監事は別々に存在するの?役割分担の理由
もし会計監査だけ、あるいは監事だけだったらどうなるでしょうか?それぞれが持つ役割や視点には限界があります。
会計監査は専門知識が必要な会計の正確さを【外部】から厳しくチェックしてくれます。しかし、会社の中で日々行われる細かい業務や不正防止については全てを把握できるわけではありません。
一方で監事は会社の一員として【内部】から監視するため、業務の実際の流れや社内の問題点を素早く見つけやすいのです。ただし、会社の人間なので、どうしても甘く見てしまうリスクもあります。
だからこそ両者を組み合わせて使うことでバランスの良いチェック体制が実現されます。
また、法律により会社の規模や形態に合わせて両方の設置や監査義務が定められているのは、会社の透明性を高めて投資家や市場の信頼を守るためです。
このように会計監査と監事にはそれぞれ強みと役割分担があって、互いに補い合っているのです。
会計監査というと「専門家が決算書をチェックするだけ」と思いがちですが、実はかなり細かいルールに沿って仕事をしています。たとえば、公認会計士が自分の判断だけで決算書を良いか悪いか決められるわけではなく、会社の会計基準や法律に従って厳密に検査します。そう聞くと固い話に感じるかもしれませんが、この厳密さがあるからこそ、投資家やお客様も安心して会社の情報を信じることができるんですね。会社の数字を信頼できる形にする裏方の努力が、社会の経済活動を支える大事な部分なのです。
次の記事: 勘定元帳と総勘定元帳の違いを初心者でもわかるように解説! »





















