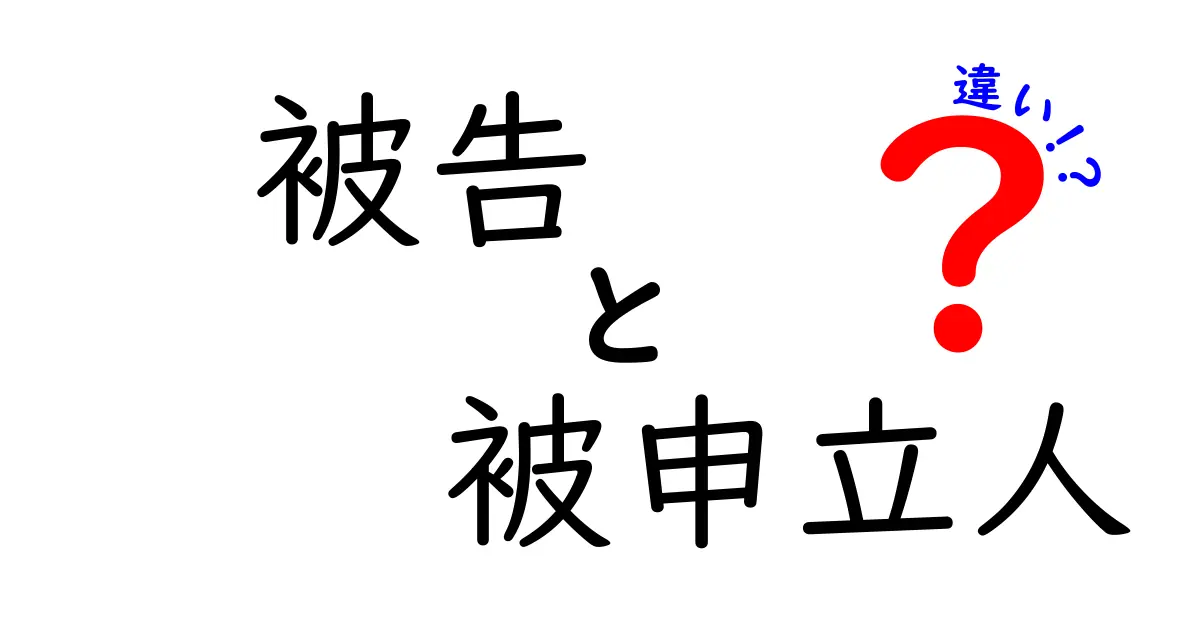

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
被告と被申立人とは何か?基本用語の違いを理解しよう
法律の世界でよく耳にする「被告(ひこく)」と「被申立人(ひもうしたてにん)」という言葉は似ていますが、それぞれ違った意味を持っています。
まず、「被告」とは民事訴訟や刑事訴訟で訴えられた側、つまり裁判で争われている相手方のことを指します。一方、「被申立人」は行政手続きや家事事件など裁判以外の申立てで対象となる人を意味します。
この違いをしっかり押さえると、法律の手続き理解が深まります。
特に、裁判の種類や手続きの目的によって使い分けられるため、混同しないことが大事です。
具体的な使用場面の違いと役割の説明
被告という言葉は、裁判所で行われる民事訴訟や刑事訴訟の当事者に対して使われます。例えば、誰かが他の人に損害賠償を求めて裁判を起こした場合、その相手が「被告」になります。
一方で、被申立人は主に家事事件や行政手続き、保護命令の申立てなど、裁判外あるいは非訴訟的な手続きの対象者に用いられます。例えば、離婚調停や後見制度の申し立てで、相手方や関係者が被申立人となります。
役割としては、被告は裁判で反論や証拠提出を行い、争いに応じますが、被申立人は行政的判断を受ける側で、協力や説明が求められることが多いです。
被告と被申立人の違いを比較表で見てみよう
| 項目 | 被告 | 被申立人 |
|---|---|---|
| 意味 | 訴訟で訴えられた側 | 申立てで対象となる側 |
| 使用場所 | 民事訴訟・刑事訴訟 | 家事事件・行政手続き |
| 法的手続き | 裁判所の訴訟手続き | 裁判外・調停・申請 |
| 役割 | 反論・防御 | 説明・協力 |
| 例 | 損害賠償請求で相手方 | 離婚調停の相手方 |
まとめ:法律用語を正しく理解して混乱を避けよう
「被告」と「被申立人」は法律手続きにおいて非常に重要な用語ですが、裁判か裁判外か、訴訟か手続きかという場面の違いによって使い分けられています。
それぞれの役割や意味をしっかり押さえておくと、法律の知識が身につくとともに、もし自分が当事者となったときに慌てず対応できるようになります。
法律用語は難しそうに見えても、一つずつ意味を理解していけば意外とわかりやすいものです。ぜひ本記事を参考に覚えてみてください。
被告という言葉はドラマや映画でよく聞きますが、実は「被申立人」とは根本的に違います。被告は裁判で訴えられた側のことですが、被申立人は離婚調停や後見申立てなどの裁判外の申請手続きの相手です。面白いのは、法律のシチュエーションによって使う言葉が変わるということ。例えば裁判なら被告、調停なら被申立人と呼び方を切り替えるんですね。これを知るだけで、法律の話がずっと理解しやすくなりますよ!
前の記事: « 弁護士会と弁護士法人は何が違う?初心者でもわかる基本ポイント解説





















