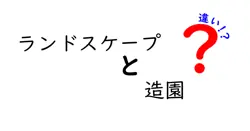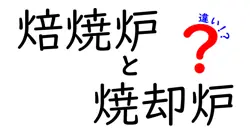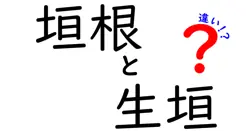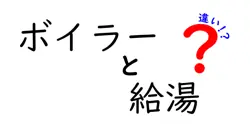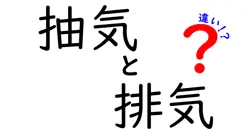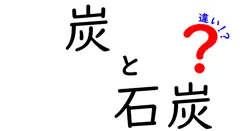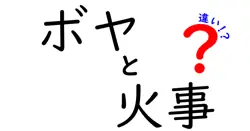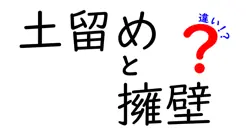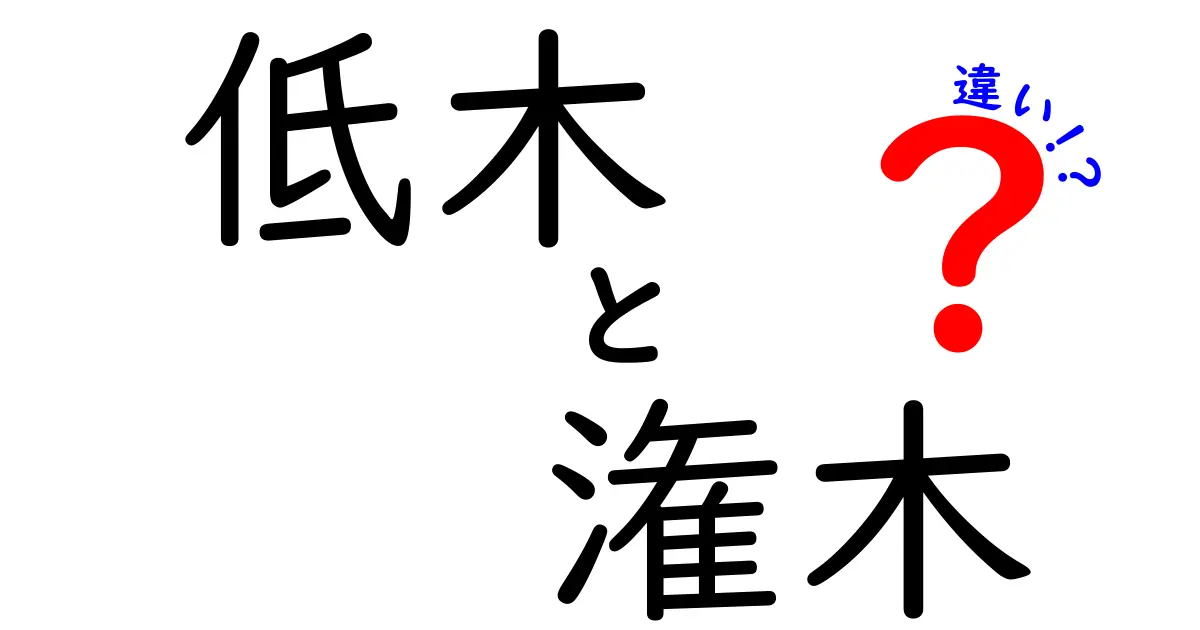
低木と潅木の違いって何?基礎知識をわかりやすく解説
私たちが日常でよく見かける植物の中には、低木(ていぼく)や潅木(かんぼく)という言葉で呼ばれるものがあります。これらは似ているようで少し違う植物の種類ですが、多くの人が混同しがちです。
まず、低木とは、地面からあまり高さがない木のことを言います。一般的には高さが1~3メートルぐらいの木を指し、茎が1本または複数本で成り立っています。これに対して潅木は、低木とよく似ているのですが、複数の茎が地面付近から分かれている木を指します。つまり、低木は高さや木質、潅木は枝の生え方に重点が置かれているのです。
例えば、庭にある小さなサツキやツツジは潅木の代表的な例。これらは地面に近いところから枝分かれしていることが特徴です。一方で、高さが2メートル程度で幹が1本のヤマボウシの低木などは低木に分類されます。
このように、低木と潅木の違いは植物の形態や成長の仕方に基づいて分類されています。見た目が似ていることが多いですが、枝の生え方や高さの目安を知ることで見分けがつきやすくなります。
そのため、ガーデニングや植物観察の際に違いを理解しておくと、植物の手入れや品種選びの役に立ちます。
低木と潅木の特徴を比較!わかりやすい表で違いをチェック
ここで、低木と潅木の主な特徴を比較する表を見てみましょう。
| 特徴 | 低木 | 潅木 |
|---|---|---|
| 高さ | 約1~3メートル | 1~3メートル程度(似ている) |
| 幹の本数 | 1本または複数本だが単幹も多い | 通常、地面から複数の枝が分かれる |
| 枝の生え方 | 幹から枝が上向きに伸びることが多い | 地面付近から枝分かれし横に広がる傾向が強い |
| 樹木質 | 木質がしっかりしている | 比較的柔らかい場合が多い |
| 利用例 | 庭木や街路樹としても使われる | 庭の生け垣やグランドカバーに利用されることも多い |
この表を見ると、両者は似ているため混同しやすいですが、枝の生え方の違いが最もわかりやすいポイントです。また、高さだけで判断するのではなく、幹の本数や枝の広がり方も合わせて観察することが大切だとわかります。
植物の名前だけでなく特徴を理解すれば、自然観察がもっと楽しくなりますね。
低木・潅木の見分け方と使い分け方、まとめてご紹介!
ここまでのポイントを押さえれば、低木と潅木の違いはしっかり理解できます。
まずは、植物を観察するときに高さは1~3メートル程度かどうかを確認しましょう。これは両者ともによく似た範囲なので参考程度に。
次に枝の生え方を見ることが大切です。地面近くから複数の枝が分かれているものは潅木、幹が1本で枝が伸びているものは低木と考えましょう。
また、用途でも違いがあります。潅木は狭い場所で横に広がりやすいため、生け垣やグラウンドカバーに向いています。低木は高さがあって見栄えもよいため、庭木や街路樹として多く利用されています。
さらに、植物の種類により例外もありますので、実際には植物図鑑や専門書を参考にするのがおすすめです。
最後に、低木・潅木という言葉は植物学的にややあいまいな部分もありますが、「枝の生え方」と「幹の本数」を手がかりに見分けることが大切ということを頭に入れておいてください。
これで、散歩やガーデニングなど、日常生活の中でより植物への興味が深まることでしょう。
ぜひ、この知識を活用してみてくださいね!
低木と潅木って、実はすごく似ているけど枝の生え方がポイントなんです。潅木は地面から枝がたくさん広がっているから、生け垣やグランドカバーにぴったり。でも、低木は幹が1本で高さがあるので庭木として目を引く存在に。自然散策でこの違いがわかると、植物の観察がもっと楽しくなりますよね。私も植物園でこれを知ってから、見る目が変わりました!
前の記事: « LED対応照度計とは?普通の照度計との違いをわかりやすく解説!
次の記事: 剪定鋏と岡恒剪定鋏の違いを徹底解説!初心者でもわかる選び方ガイド »