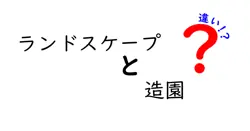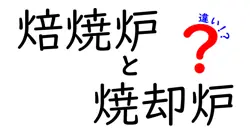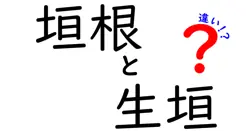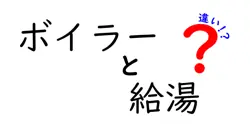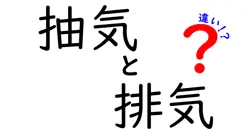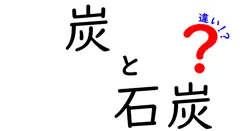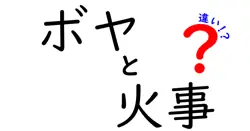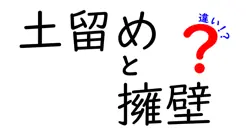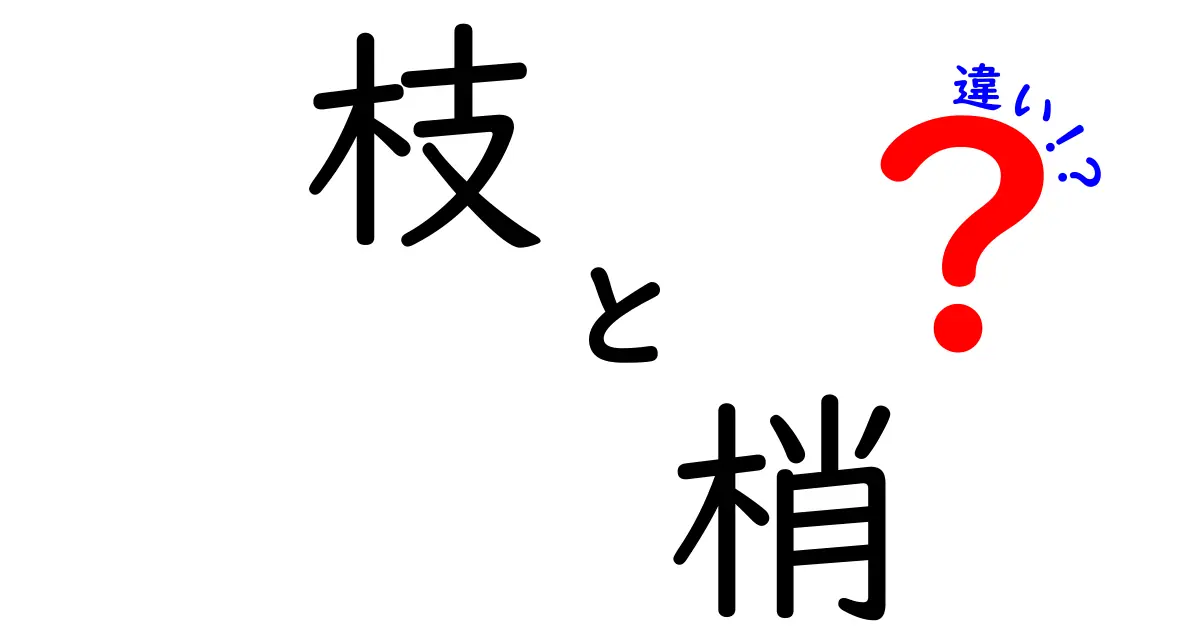
枝と梢の違いとは?基本の理解を深めよう
みなさんは、「枝(えだ)」と「梢(こずえ)」の違いをご存知ですか?どちらも木に関する言葉ですが、実は意味や使われ方に違いがあります。
まず、枝とは、木の幹から伸びている太くてしっかりした部分を指します。枝は根本に近い場所から伸びていて、葉や花、果実を支える重要な役割をもっています。
一方、梢は枝のさらに先端の細くて小さい部分を意味します。つまり、梢は枝の先にある小枝や葉っぱが集まった部分をさします。
このように、枝と梢は似ているけれど、木のどの部分を表すかで違いがあります。枝がより太くて幹に近い部分を示すのに対して、梢は枝の先端部分、比較的小さく弱そうな部分というイメージです。
この違いを理解することで、木や植物を観察する際により詳しく、正確に話すことができるようになります。
枝と梢の具体的な特徴と使い方の違い
では、それぞれの言葉の特徴や使い方も見ていきましょう。
まず、枝は、木の丈夫で太い部分です。例えば、台風の強風で折れやすいのは枝ですが、幹まではなかなか折れません。枝は樹木の構造上、葉や花や果実を支える役割がありますので、幹から直接伸びていることが多く、その太さや形は種類によってさまざまです。
対して、梢は、主に学術的な文章や詩的な表現でよく登場します。梢は風に揺れる先端部分だったり、新芽が育つ場所でもあり、季節の移り変わりや自然の微妙な変化を表現する際によく使われます。
さらに、梢は幹や枝よりずっと細いため、強い風で折れたり揺れやすい特徴があります。
枝が日常の会話や観察の際に使う言葉なのに対して、梢は文学的で繊細なイメージを持つ言葉と言えます。
枝と梢の違いを簡単にまとめた表
ここまで説明した違いを分かりやすくまとめた表を作成しました。
このように、「枝」と「梢」は木の部分を表す言葉ですが、場所や太さ、役割に違いがあり、使われる場面やイメージも変わってきます。
自然の中で木を観察するときや、文章を書くときにぜひこの違いを使い分けてみてください。
「梢(こずえ)」という言葉は、ただの木の先端部分を指すだけではなく、詩や文学の中で自然の繊細な動きや季節の変化を表す象徴として使われることが多いです。例えば、春の風に揺れる梢の新芽は、新しい生命の始まりとして描かれ、秋には色づいた葉が梢を彩って情緒的な風景を作り出します。普段あまり意識しないかもしれませんが、梢は自然の美しさや儚さを感じさせる重要な言葉なんですね。
前の記事: « 【木の葉と落ち葉の違いとは?】見分け方や特徴をわかりやすく解説!