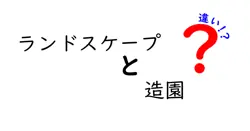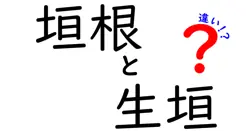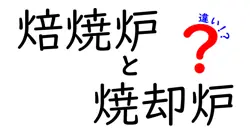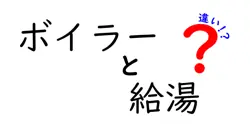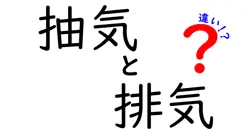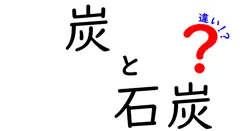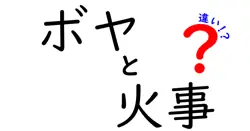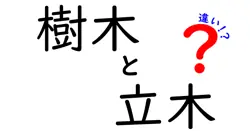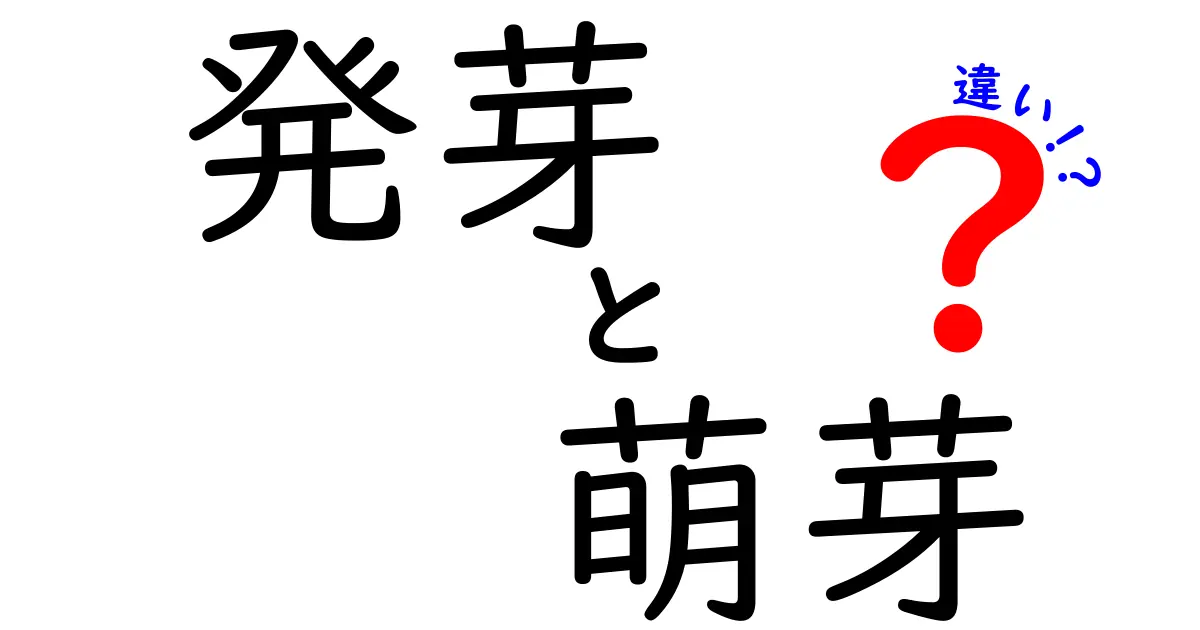
発芽と萌芽とは?植物の始まりを知ろう
植物の成長過程には様々な段階がありますが、特に「発芽(はつが)」と「萌芽(ほうが)」という言葉はよく使われます。
発芽は、種(しゅ)が水を吸い膨らみ、中の胚(はい)から新しい芽が出る最初の段階を指します。例えば、豆の種から小さな芽が出てくる様子がこれにあたります。
一方で萌芽は、主に植物の春先に、木の枝や茎から新しく芽が吹き出すことを言います。つまり、種からの芽ではなく、既に育っている植物の体の部分から新しい芽が生えることを指しています。
このように両者は似ているようで、発生の場所やタイミング、対象が違います。
発芽は植物の世界にとって最初の生命の誕生を意味し、とても大切な役割を持っています。萌芽は成長や再生を表し、植物が年々強く逞しく成長していくために必要な現象なのです。
この違いを理解することで、植物のライフサイクルをより詳しく知ることができます。
発芽と萌芽の違いをわかりやすく比較!特徴を詳しく解説
では、発芽と萌芽の違いを具体的に表で整理してみましょう。
| 項目 | 発芽 | 萌芽 |
|---|---|---|
| 意味 | 種から新しい芽が出ること | 植物の体(枝や茎)から新たに芽が出ること |
| 対象 | 種子 | 既存の植物体 |
| タイミング | 種まき後や自然環境下の適切な条件で | 主に春の生長期 |
| 役割 | 新しい生命の誕生 | 再生や成長促進 |
| 観察しやすい例 | 豆や麦の芽が土から出る | 桜の枝から新芽が出る |
このように表で見ると、発芽は“まさに新しい植物を生み出す瞬間”、萌芽は“既にある植物が新たな生命活動を始める過程”と覚えるとわかりやすいです。
植物の成長過程を理解していると、これらの違いが自然と生活や学習に役立てることができます。
例えば、農業や園芸では発芽をしっかり観察してから苗を育て、萌芽の時期には木や植物の枝の管理を行うことで、健康な植物育成を目指せます。
発芽と萌芽の違いを知るメリットと日常生活への役立て方
発芽と萌芽の違いを知っていると、植物に対する理解が深まるだけでなく、自然観察や園芸活動に大変役立ちます。
例えば、春に庭や公園で芽が出ているのを見て「これは発芽かな?それとも萌芽かな?」と考えることで、植物の成長段階についての知識が自然と増えていきます。
また、植物を育てる際にもこれらの用語を理解していると、生育状況を的確に判断でき、適切な管理がしやすくなります。
さらに、授業や試験でもこの違いを押さえておくと、生物の成長過程に関する理解が深まり、問題を解くときに役立つでしょう。
まとめると、発芽は種子から新しい生命が誕生する瞬間、萌芽は既にある植物が新しく芽を出す成長や再生の段階。
それぞれの意味を知り植物の成長を丁寧に見ることで、私たちの生活がより豊かになります。
発芽についてよく話題になるのは、“なぜ種から芽が出るのに時間がかかるの?”という疑問です。実は、発芽はただ水を吸うだけでなく、温度や光の条件、土の状態など多くの環境要因が関係しているんですよ。だから、同じ豆の種でも、時には数日で芽が出ることもあれば、なかなか出てこないこともあります。発芽の速さや成功は、植物の種類や環境の影響を強く受けている、すごく繊細な現象なんですね。これを知ると、実験で種を育てるときも観察が楽しくなりますよ!
前の記事: « コンクリートと石材の違いを徹底解説!用途や特徴をわかりやすく比較
次の記事: 「日向」と「陽向」の違いとは?意味や使い方を徹底解説! »