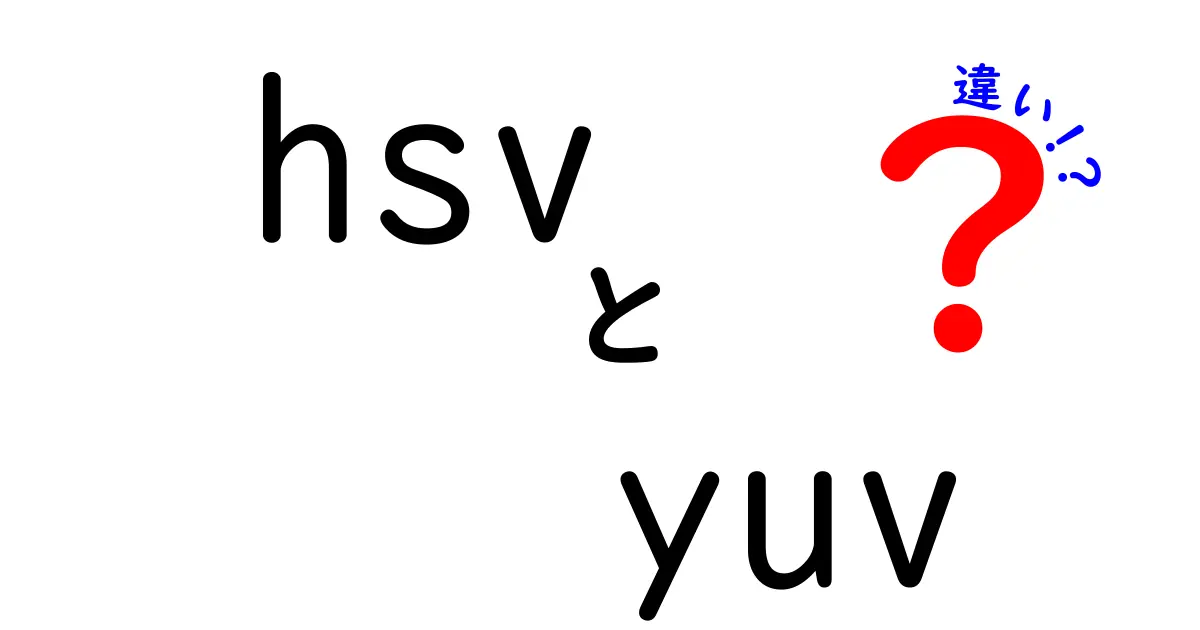

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
HSVとYUVとは何か?基本を知ろう
まず、HSVとYUVは、どちらも色を表現するための方法(色空間)ですが、それぞれの目的や仕組みが違います。
HSVはHue(色相)、Saturation(彩度)、Value(明度)という3つの要素で色を表し、人の目で見た色の感覚に近い表現方法です。例えば、赤や青などの色の種類を示すHue、色の鮮やかさを示すSaturation、明るさを示すValueで色をイメージしやすいのが特徴です。
一方、YUVは色の情報を明るさ成分のYと、色の成分のU(青と黄の差)とV(赤と緑の差)で分けて表現します。映像やテレビ、動画圧縮などでよく使われる技術的な色空間です。特にY成分は明るさ情報を持つため、白黒モードでの映像にも対応しやすいのが特徴です。
HSVとYUVの違いを詳しく比較
この2つの色空間を比べると、以下のような違いがあります。 このように、HSVは人が色を選ぶ際に使うことが多く、YUVは映像の保存や伝送に強みがある色空間です。 簡単に言うと、HSVは色の見た目に近く見やすい表現方法、YUVは明るさと色を分けて扱う技術的な表現方法です。 HSVの“Hue”は色相のことで、たとえば赤や青という色の種類を表す部分です。実は、このHueは0度から360度までの円で色が配置されていて、0度が赤、120度が緑、240度が青と決まっています。だから色の組み合わせを考えるとき、たとえば「180度離れた色は補色」という面白いルールもあるんですよ。色を円でイメージするHSVは、こうした色の関係性を直感的に理解しやすい画期的な色空間なんです。 前の記事:
« 色弱と色覚の違いとは?わかりやすく解説!見え方の秘密を知ろう特徴 HSV YUV 表現する色の要素 色相(Hue)、彩度(Saturation)、明度(Value) 明るさ(Y)、青色情報(U)、赤色情報(V) 主な用途 画像編集、カラー選択ツール、デザイン 映像信号処理、テレビ放送、動画圧縮 人間の目への親しみやすさ 直感的でカラー感覚に近い 技術的でやや難しい 色の分離 色相と明るさを分けて制御しやすい 明るさと色成分を分離し、圧縮に有利 まとめ:使い分けがポイント!
例えば、画像を加工したいときやデザインではHSVが便利です。
逆に、動画をテレビに送ったり圧縮したりするときはYUVの方が向いています。
この違いを知ることで、色に関する技術をより深く理解できるでしょう。
色の扱いに関わる仕事や勉強をしている人は、ぜひHSVとYUVの特徴や違いを押さえて活用してみてください。
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事





















