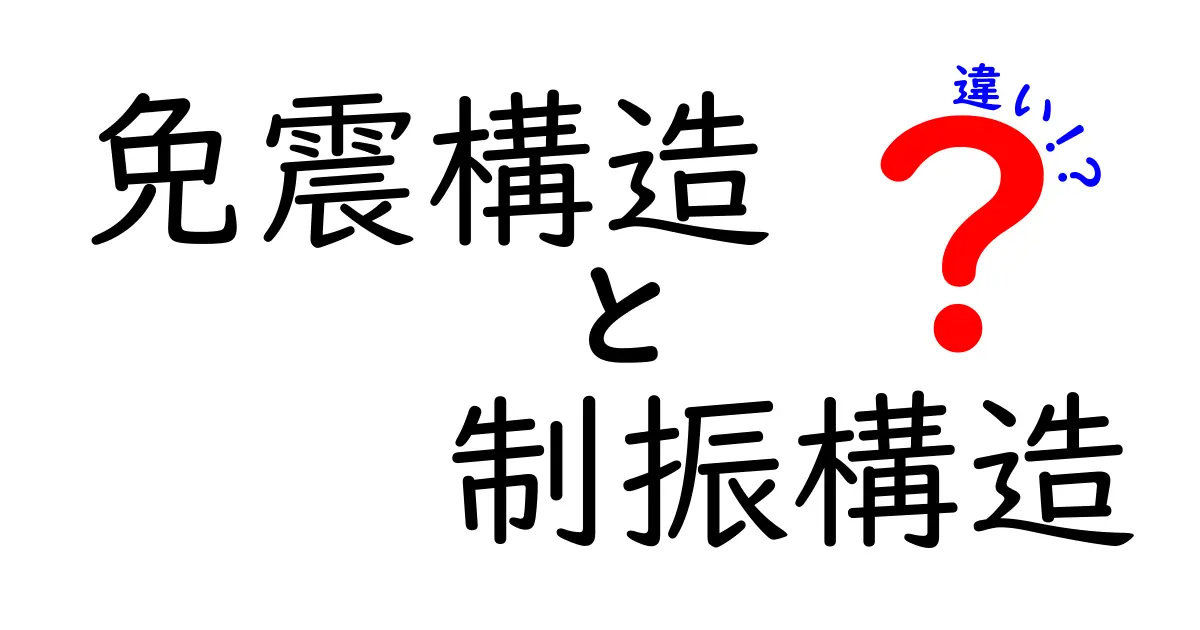

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
免震構造とは?その仕組みと特徴をわかりやすく解説
<強い地震が起きたとき、建物に直接揺れが伝わらないようにする技術が免震構造です。免震構造は、建物の基礎(建物の一番下の部分)に特殊な装置を取り付けて、揺れを大きく吸収し減らす仕組みです。
具体的には、建物と地面の間に「免震装置」と呼ばれるゴムやばねのようなものを置くことで、地震の揺れをやわらげます。これにより揺れのエネルギーが少なくなり、室内は比較的静かに保たれるのです。
免震構造は大きな地震でも建物の損傷を最低限に抑え、人の安全を守るために使われることが多いです。学校や病院、大切なオフィスビルなどでよく採用されています。
しかし、免震装置を設置するために建築費用が高くなりやすく、すべての建物に適用できるわけではない点がデメリットです。
このように、免震構造は地震の揺れを建物に伝えにくくする仕組みと覚えるとわかりやすいでしょう。
制振構造とは?特徴や働きをしっかり理解しよう
<一方、制振構造は、建物の揺れを完全に防ぐのではなく、建物の揺れを小さく抑える技術です。
建物の柱や梁(はり)に制振装置を取り付けて、地震による揺れのエネルギーを吸収し、建物の揺れの大きさを減らします。
制振装置はダンパーと呼ばれる装置が一般的で、これは車のショックアブソーバーに似た仕組みです。揺れが来ると、装置内のオイルや部品が動いてエネルギーを熱に変え、揺れを弱めます。
制振構造のメリットは免震構造に比べてコストが抑えやすいこと、そして建物の設計自由度が高いことです。
ただし、免震ほど揺れを大幅に減らす効果はないため、強い地震の場合は多少揺れを感じることがあります。
制振構造はマンションや一般のオフィスビル、小規模な建築物などに多く使われています。
免震構造と制振構造の違いを表で比較!特徴や使い分けのポイント
<| 項目 | <免震構造 | <制振構造 | <
|---|---|---|
| 仕組み | <建物と地面の間に免震装置を設置し揺れを伝えにくくする | <建物内に制振装置を設置し揺れのエネルギーを吸収する | <
| 揺れの抑え方 | <揺れを大幅に減らす(ほとんど感じない場合もある) | <揺れを小さくし被害を減らす | <
| 主な装置 | <ゴムやばね、免震支承 | <ダンパー(オイルダンパーなど) | <
| コスト | <高い(設置が複雑) | <比較的低い | <
| 適した建物 | <病院、学校、重要施設、大規模建築 | <マンション、オフィス、小規模建築 | <
| 揺れの感じ方 | <ほとんど揺れを感じないことも多い | <揺れを感じるが大きくはない | <





















