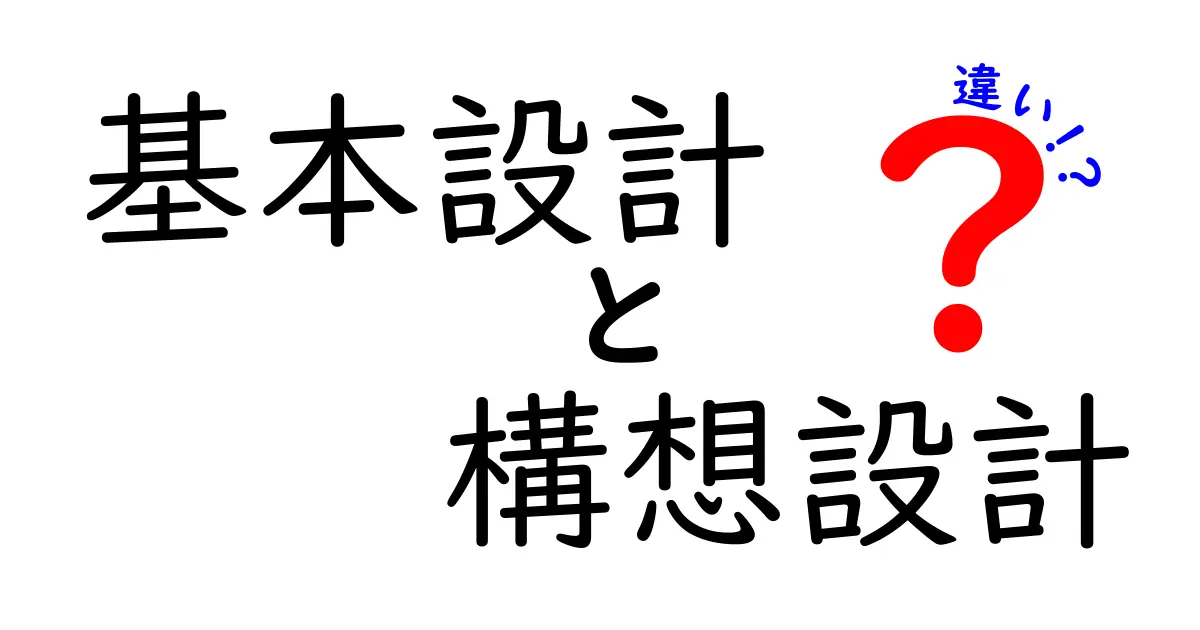

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基本設計と構想設計の違いとは?
システム開発や製品づくりにおいて、よく出てくる言葉に「構想設計」と「基本設計」があります。どちらも設計の段階ですが、似たような言葉なので混同しやすいですよね。
ここでは中学生でもわかるように、それぞれの意味や違いについて丁寧に説明します。
まずはそれぞれがどんな役割を担っているのかを理解すると、全体の開発の流れもつかみやすくなります。
構想設計とは?
構想設計は、プロジェクトのスタートに近い段階です。
ここでは「どんなものを作るのか」「何を解決したいのか」を大まかに考えます。
具体的には、使う人が欲しい機能や目的をまとめ、全体のイメージを作り出すフェーズです。
例えば、新しいスマホアプリを作るなら、どんな機能が必要か、誰が使うのか、といった大まかな方向性を決めます。
ポイントは細かい部分まで決めずに、大きな枠組みを考えることです。
この段階ではまだ詳細な設計や具体的な数値は扱いません。
構想設計がうまくできると、次の設計へスムーズに移行できます。
基本設計とは?
基本設計は構想設計の次の段階です。
ここでは構想で決めた内容をさらに詳しく具体的に決めていきます。
例えば、どんな機能が必要か、それらをどうやって実現するか、全体の構造や流れを設計します。
具体的には画面のデザインのイメージやデータの流れ、必要な処理の内容などを決定していきます。
全体の設計図のようなもので、ここで決めた内容をもとに詳細設計やプログラミングが始まります。
基本設計は、より現実的で技術的な判断が求められる段階です。
そのため構想設計よりも詳しく細かい仕様が決まります。
両者の違いを詳しく比較
下の表を見ると、構想設計と基本設計の違いがわかりやすくなります。
| 項目 | 構想設計 | 基本設計 |
|---|---|---|
| 目的 | 大まかな方向性や全体のイメージ作成 | 具体的な機能や構造の設計 |
| 内容 | ユーザーのニーズや課題の把握 | システム構成や処理の詳細設計 |
| 細かさ | あいまいで大まか | 詳細で具体的 |
| 成果物 | 構想書やコンセプト図 | 設計書やフロー図 |
| 目的段階 | 開発の初期段階 | 開発の中盤段階 |
まとめると、構想設計は「どんなモノを作るかのアイデアをまとめる段階」、基本設計は「そのアイデアを実際にどう形にするかを決める段階」と言えます。
どちらも重要な工程で、構想がしっかりしていれば基本設計も正しく進めやすくなります。
最初から細かいところを決めようとせず、段階を踏んで開発を進めていくことが成功の秘訣です。
ぜひこの記事を参考に、設計の違いを理解し、システムやものづくりの基礎をしっかり身につけてくださいね!
「構想設計」という言葉だけ聞くと、なんだか抽象的で難しそうに感じますよね。でも、実はこれってアイデアを広げて全体像をざっくりイメージする段階のこと。例えば、旅行の計画を立てるとき、まずどこに行くか、何をしたいかを決めるのがまさに構想設計のイメージです。細かい日程や宿泊先は後から決めるため、この段階は自由にいろんなアイデアを出すのがポイントです。ざっくり決めておくから、あとで具体化するときにスムーズに進められますよね。構想設計をおろそかにしないことが成功の第一歩です!





















