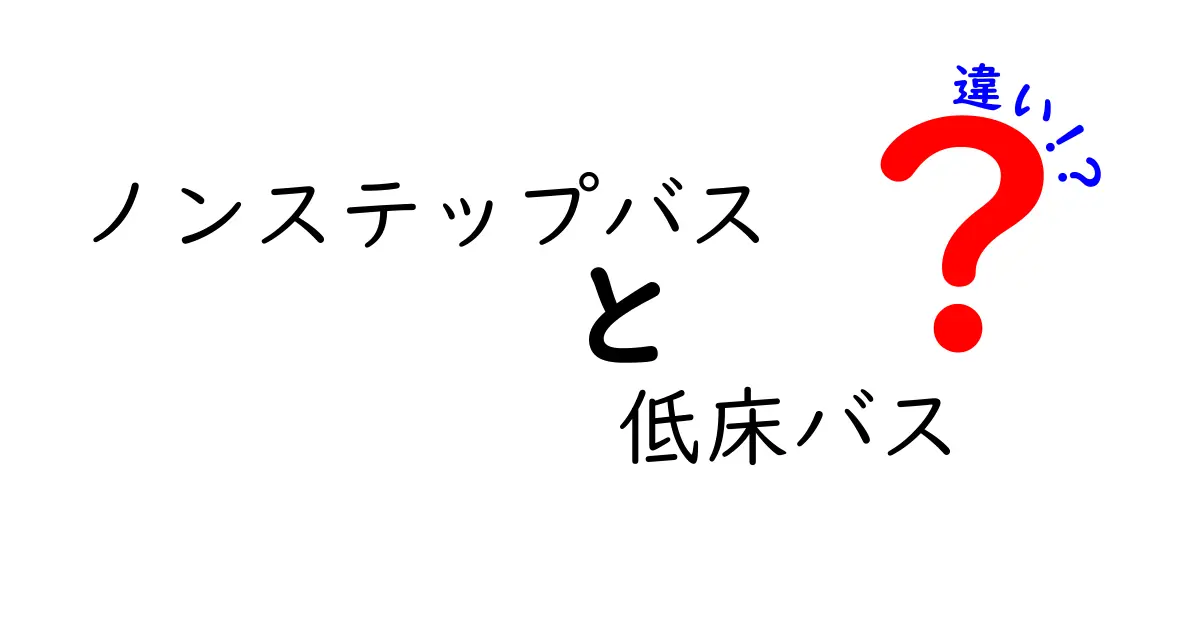

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ノンステップバスと低床バスの違いについての基礎知識
みなさんは「ノンステップバス」と「低床バス」という言葉を聞いたことがありますか?どちらもバスの特徴をあらわす言葉ですが、実は意味が少し違います。
ノンステップバスとは、乗降口のステップ(段差)がなく、地面からバスの床までがフラットで、乗り降りが簡単なバスのことをいいます。これは高齢者や体の不自由な人、そして小さな子どもたちもスムーズに乗ることができるように工夫されたバスです。
一方、低床バスはバスの床の高さ自体が低く設計されているバスのことです。これによって乗降時の段差を減らし、乗りやすさを実現しています。
簡単にいうと、ノンステップバスは段差がないことを強調したバス、低床バスは床の高さが低いバス、ということになります。
このふたつは似ているようで微妙に違う特徴を持つため、混同しやすく、知っておくと便利ですよ。
ノンステップバスと低床バスの具体的な違いを表で比較
わかりやすくするために、ノンステップバスと低床バスの違いを表で比較してみましょう。
| 特徴 | ノンステップバス | 低床バス |
|---|---|---|
| 床の高さ | 地上からバスの床まで段差なし 完全フラット・ノンステップ | 床自体が低いが段差がある場合もある 床の高さは乗降に便利な高さ |
| 乗降口の構造 | ステップが無いため車椅子も乗りやすい 電動でスロープが出る機種もある | 低い床だがステップが1段ある場合もある 機種によってはスロープなしも |
| 利用者への配慮 | 高齢者や障害のある人の乗りやすさ重視 | 一般的には乗りやすく作られている |
| バスの種類・形状 | 多くは路線バスで採用されている | 路線バスだけでなく観光バスにも使われる |





















