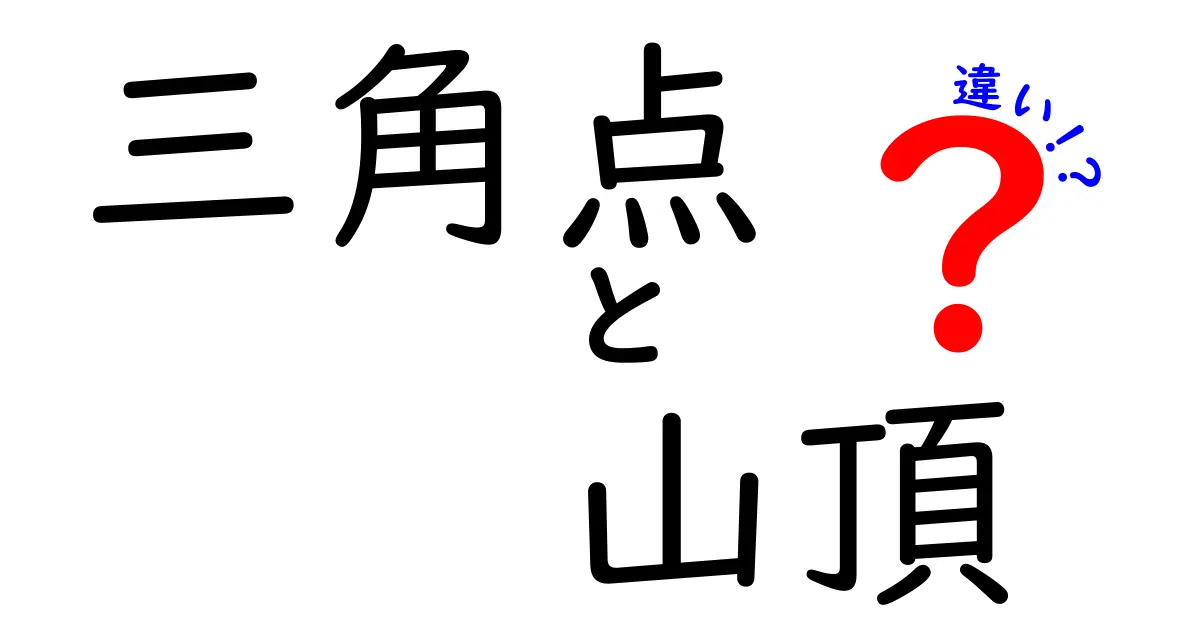

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
三角点とは?
三角点は、地図や測量で使われる重要なポイントのことです。地形や位置を正確に測るために設置されている点で、日本全国に数多く存在しています。多くの場合、石やコンクリートの杭が地面に埋められており、その上に標識が立っています。この三角点を基準にして、正確な距離や角度を測り、地図作成や土地の管理に役立てています。
三角点は必ずしも山の頂上に設置されているわけではなく、測量の精度を高めるために便利な場所に置かれています。そのため、登山道や山の頂上から離れていることも多いです。
三角点の設置には国土地理院などの専門機関が関わっており、測量の基準点としての役割がとても重要です。
三角点を見ると、地図作りの裏側が感じられ、ちょっとした探検気分にもなりますよ。
山頂(山の頂上)とは?
山頂とは、その山で一番高い場所、つまり山の頂上部分のことを指します。登山者にとっての目的地であり、景色が一望できる素晴らしい場所でもあります。
山頂は必ずしも三角点と同じ場所であるとは限らず、実際に多くの場合で山頂より少し違う場所に三角点が設置されていることがあるのです。
山頂は登山記録や地図でも「標高点」として表示されることが多く、登山者向けの情報が豊富です。山によっては看板や標柱が立っており、頂上を明確に示しています。
また、山頂は地形の最高点であるため、気象条件や自然環境が厳しいこともあります。ですから、行く際は必ず準備をしっかり行いましょう。
三角点と山頂の違いを表で比較
まとめ
三角点は地図や測量のために設置されたポイント、山頂は山の最高点を指し、必ずしも位置が一致しないというのが大きな違いです。
登山の際に三角点を見かけても、「ここが頂上ではない」ということもあるため、しっかりと地図を確認しながら楽しむと良いでしょう。
どちらも山に関係する重要な場所ですが、用途や目的によって役割が違うことを理解できれば、山や地図の見方がより面白くなります。
三角点って実は結構硬いコンクリートの杭なんです。見た目は地味で、登山中に意識していないと気づかないことも多いのですが、これがないと正確な地図は作れません。山の頂上が必ずしも三角点ではない理由の一つに、測量の際に機器が設置しやすい場所や、ほかの三角点から測りやすい場所を選んで設置していることがあります。なので、偶然見つけた三角点をチェックするのも山登りの楽しみの一つです!
前の記事: « 標高と海抜高の違いって何?初心者でもわかる完全ガイド
次の記事: 地勢図と地形図の違いとは?初心者でもわかる特徴と使い方のポイント »





















