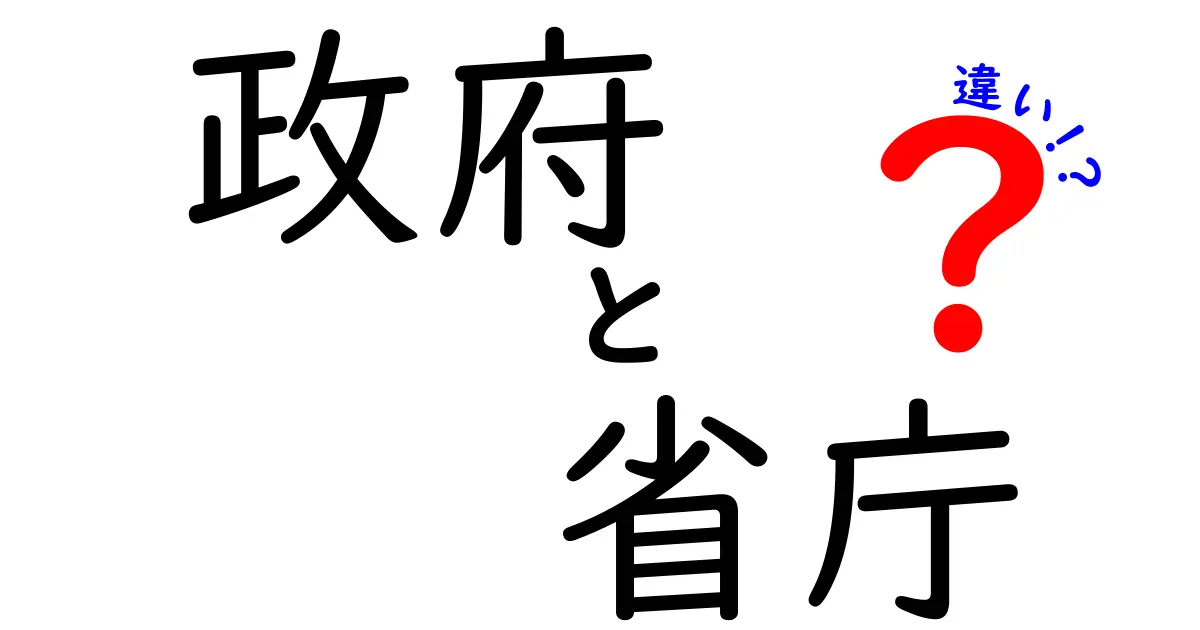

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
政府と省庁の違いとは?基本からしっかり理解しよう
みなさんは「政府」と「省庁」の違いを知っていますか?
どちらも日本の政治や行政に関係していますが、とても似ているようで違うものなんです。
今回はその違いをわかりやすく中学生にも理解できるように解説していきます。
まずは政府とは何か?
政府は日本を動かす最高の決定機関です。
国の全体を管理し、法律を実行したり国民の生活を守ったりする役割を持っています。
内閣総理大臣(首相)がトップで、内閣という形で政治を行います。
ちなみに政府は国会が作った法律を実行する役目があり、政策を決めたり実際に動いたりしています。
省庁とは何か?政府との関係は?
省庁とは政府の中にある組織のことです。
日本の国の仕事はとても多いため、さまざまな分野ごとに役割を分けて行うための組織が必要です。
それを担っているのが「省(しょう)」と呼ばれる部署です。
たとえば、教育を担当する文部科学省や、防衛を担当する防衛省、経済を担当する経済産業省などがあります。
こういった省が集まって日本の行政を動かしています。
このように省庁は政府のひとつの部分や部署であり、仕事を分担しているのです。政府は内閣であり、その内閣に所属する各省庁が専門分野ごとに仕事を行っています。
政府と省庁の違いを表でまとめてみよう
まとめ:なぜ違いを知ることが大切?
「政府」と「省庁」の違いを知ると、日本の政治や行政のしくみがよくわかります。
ニュースで「政府がこう決めた」「省庁が動いた」と言われた時に、その意味や背景が理解できるようになるからです。
例えば災害のときに防災省庁が対応するとか、消費税の改正を政府が決める仕組みなど、理解が深まります。
今後、社会のニュースを読むときにも役立つので、ぜひ覚えておいてくださいね!
省庁の中には、名前だけではピンとこないものもあります。例えば「法務省」は法律関係を担当しますが、実は裁判所とは違い、法律の管理や出入国管理などを行っています。意外と知られていない省庁の役割を知ると、ニュースをもっと楽しく理解できるようになりますね!
次の記事: 内閣と首相の違いって?初心者でもわかる政治の基本ポイント解説 »





















