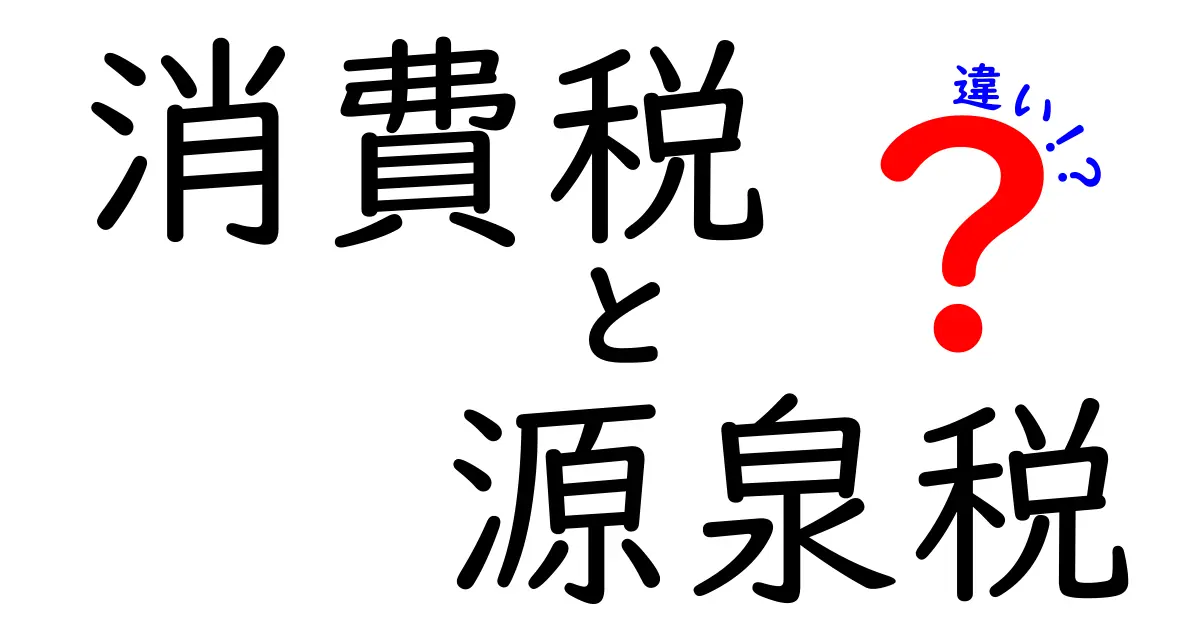

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
消費税と源泉税とは何か?基本から理解しよう
税金という言葉はよく聞きますが、中でも消費税と源泉税は日常生活や仕事の中でよく関わる税金です。
消費税は、商品やサービスを買うときにかかる税金で、私たちが何かを買うたびに店で支払っています。
源泉税は、給与や報酬などお金をもらうときにあらかじめ差し引かれる税金のことです。
この2つの税金は名前が似ているので混同されがちですが、目的や仕組みが大きく異なります。
それぞれの役割と特徴を理解することで、税金についての知識がさらに深まります。
消費税の特徴と仕組み
消費税は、国が商品やサービスを買う人から幅広く少しずつ集める税金です。
日本では現在10%(内訳は8%が標準税率、軽減税率が一部商品に適用)で、買い物やサービスを利用した時にその金額に上乗せされています。
この税金は、最終的には消費者が全額負担する形になります。つまり、働いて得たお金で買う商品にかかる税金と考えるとわかりやすいです。
消費税は社会のさまざまなサービスや国の運営資金に使われており、広く薄く税を集めるための仕組みだと言えます。
たとえば1000円の商品を買うと、消費税10%の100円が加わり、税込価格は1100円になります。
源泉税の特徴と仕組み
源泉税は、給与や報酬を支払う時に、支払う側が代わりに税金を差し引いて国に納める仕組みです。
例えば会社員の給料からは所得税があらかじめ天引きされて支払われます。
この仕組みは、税金の徴収を確実にしやすくするためで、納める側の手間も減ります。
たとえばフリーランスの方が仕事の報酬を受け取る際に、その報酬から1割程度の源泉所得税があらかじめ差し引かれて支払われることがあります。
源泉税はあとで確定申告で調整され、不足分を追加で払ったり、払いすぎた分が戻ってきたりします。
つまり税金の前払いのようなしくみです。
社会保障費や所得にかかる重要な税金の一つです。
消費税と源泉税の違いを表で比較
ここで分かりやすいように、消費税と源泉税の違いを表にまとめました。
| 項目 | 消費税 | 源泉税 |
|---|---|---|
| 対象 | 商品やサービスの購入時 | 給与や報酬の支払い時 |
| 支払う人 | 消費者(買う人) | 所得を得る人(受け取る人) |
| 納付者 | 販売者や事業者 | 支払者(会社や個人) |
| 税率 | 10%(標準税率) | 所得の種類により異なる(例:10%、20%など) |
| 特徴 | 広く薄く集める消費税 最終消費者が負担 | 給与や報酬からあらかじめ差し引かれる税金 後で確定申告で調整 |





















