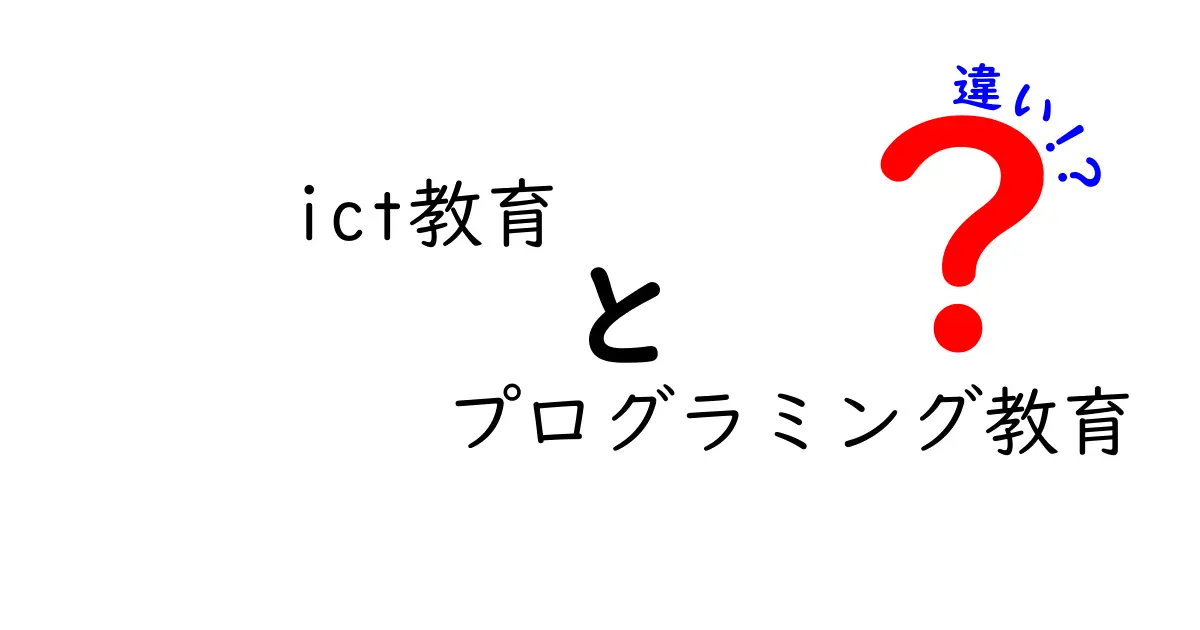

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ICT教育とプログラミング教育の基本的な違いとは?
最近、学校やニュースでよく聞く「ICT教育」と「プログラミング教育」という言葉。
この2つは似ているようで実は目的や内容が違います。ICT教育は情報通信技術(Information and Communication Technology)を使って、パソコンやタブレットなどのデジタル機器を活用しながら学ぶ学習のこと。
一方、プログラミング教育は自分でコンピュータに命令を書く「プログラム」を学ぶ授業です。
つまり、ICT教育は機器やツールを使った学習全般を指し、プログラミング教育はその中の1つで「どうやってコンピュータに考えさせるか」を学ぶ特別な分野というわけです。
この違いを理解すると学校での授業や今後の学び方がもっとわかりやすくなりますよ。
具体的な内容や目的の違いを表で比較
以下の表で、ICT教育とプログラミング教育の特徴をまとめてみました。
| ポイント | ICT教育 | プログラミング教育 |
|---|---|---|
| 目的 | コンピュータや機器を使いこなす能力を育てる (調べる・表現する力) | プログラムを作る力を身につけ 問題解決能力や論理的思考を育てる |
| 内容 | タブレットやパソコン操作、プレゼン資料作成、インターネット活用 | プログラミング言語の基本文法、アルゴリズム、ロジックを学ぶ |
| 使用機器・ツール | タブレット、パソコン、電子黒板など | プログラミング言語(Scratch、Pythonなど) +コンピュータ |
| 対象年齢 | 小学生から中学生まで幅広い | 小学生から高校生まで。学年により内容も変化 |
| 学習効果 | 情報活用力、コミュニケーション能力が向上 | 論理的思考力や問題解決能力が高まる |





















