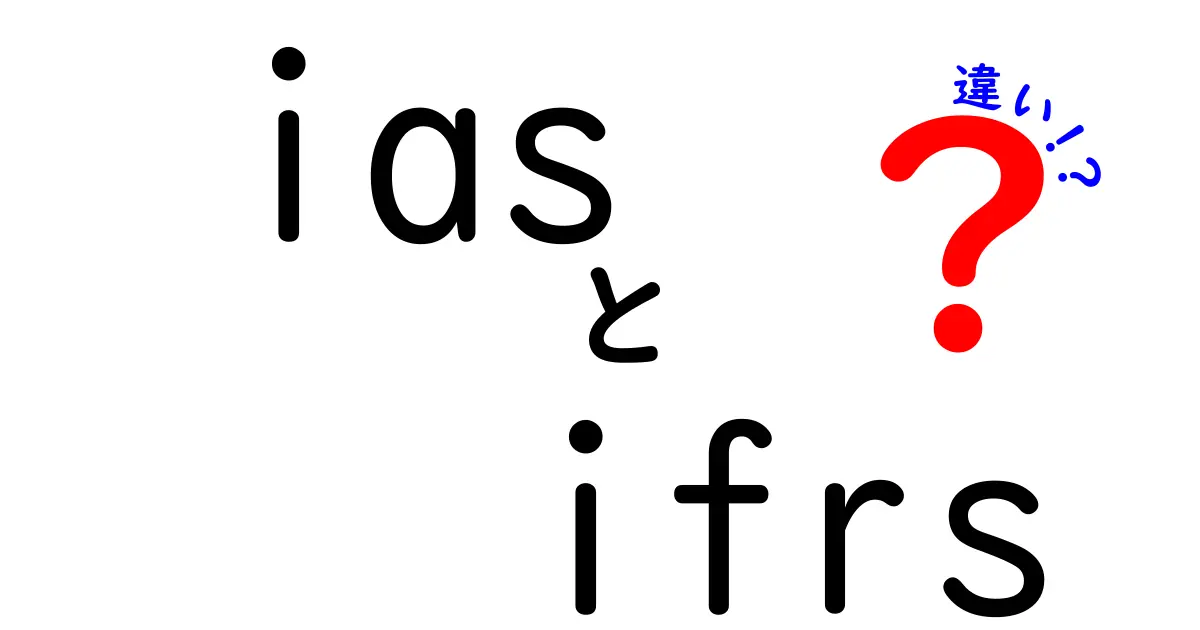

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IASとIFRSとは?基本の理解から始めよう
会計の世界でよく聞く用語にIAS(国際会計基準)とIFRS(国際財務報告基準)があります。
これらはどちらもグローバルに通用する会計のルールですが、混同してしまう人も多いです。
まずは、IASとIFRSの基本についてしっかり学びましょう。
IASは1973年に設立された国際会計基準審議会(IASC)によって作られました。
その目的は、国や企業によって異なる会計のルールを統一し、世界中の企業の財務報告を比較しやすくすることです。
一方、IFRSは2001年に設立された国際会計基準審議会(IASB)が制定している基準で、
IASを引き継ぎながらより現代的で改善されたルールです。
つまり、IASは昔の国際基準、IFRSはその後継者と考えられます。
では、それぞれがどのように違い、どう使われているのかを詳しく見ていきましょう。
IASとIFRSの主な違いとその特徴
IASとIFRSの大きな違いは、発行された時期とルールの進化度合いにあります。
IASは1970年代から1990年代にかけて作られたもので、財務諸表の作成に必要な基準の基礎を作りました。
しかし、時代の変化や経済環境の変化に伴い、基準の見直しや改正が必要になりました。
そこでIASBは、新しい基準としてIFRSを2001年より導入し、IASのうち有効な部分をIFRSとして引き継ぎつつ、より分かりやすく使いやすいルールに整備しました。
例えば、IASでカバーされていなかった新しい取引や複雑な会計処理に対応するためにIFRSは柔軟性と最新の実態に合った基準を提供しています。
表で簡単にまとめると次の通りです。
| 項目 | IAS | IFRS |
|---|---|---|
| 発行時期 | 1973年〜2001年 | 2001年〜現在 |
| 作成元 | IASC(国際会計基準審議会) | IASB(国際会計基準審議会) |
| 対象 | 基礎的な会計基準 | 最新の会計基準を含む現代的ルール |
| 特徴 | 旧基準で一部古さあり | 柔軟で適用範囲広い |
このように、IFRSはIASをベースにしながら、今の時代に合ったアップデートが加えられているわけです。
多くの国と企業がIFRSを採用する方向に進んでいます。
IASとIFRSが企業や投資家に与える影響
IASやIFRSが普及することは、企業の財務報告の透明性や比較可能性を高めるために重要です。
たとえば海外の投資家が日本の企業に投資しようとする場合、会計基準が違えば企業の利益や資産がどのようになっているか把握しにくくなってしまいます。
IFRSはその問題を解決するために世界共通のルールを提供しているので、企業も投資家も共通の基準に基づいて情報を評価できます。
また、国際的にIFRSを採用している国も多いため、多国籍企業は会計基準を統一して報告ができ、経営も効率的になります。
ただし、日本ではまだすべての企業がIFRSを採用しているわけではなく、基準の理解や運用には専門的な知識が必要です。
これから企業会計の勉強をする人は、IASとIFRSの違いをしっかり押さえ、最新のルールであるIFRSの内容を理解することが大切です。
まとめ:IASとIFRSの違いを押さえて会計を理解しよう
ここまで、IASとIFRSの違いについて、中学生にも分かりやすく解説しました。
重要なポイントは次の通りです。
- IASは1970年代〜2001年に作られた旧国際会計基準
- IFRSは2001年以降に導入された、より新しく改良された国際基準
- IFRSはIASの内容を引き継ぎつつ、時代の変化に合わせてアップデートされている
- IFRSの採用により企業の財務報告は透明で比較しやすくなる
今後、世界の会計基準はIFRSを中心に動いていくでしょう。
だからこそ基本をしっかりと理解し、国際的な視点で会計を学ぶことが求められています。
この記事がIASとIFRSの違いを理解するきっかけになればうれしいです!
IFRSはIASを改良してより現代的なルールにしたものですが、なぜわざわざ新しい基準を作ったのか気になりますよね。実は経済環境やビジネスの形が日々変わっていくため、昔の基準だけでは企業の実態を正しく表せないことが多くなりました。
たとえば新しい金融商品や国際取引が増えた今、会計処理ももっと柔軟で細かいルールが必要に。IFRSはそんな現代のニーズに合わせるために誕生し、企業や投資家がより正確に情報を理解できるようサポートしています。
つまりIFRSは単なるルールの置き換えではなく、変化する世界に対応するための“進化形”なんです。





















