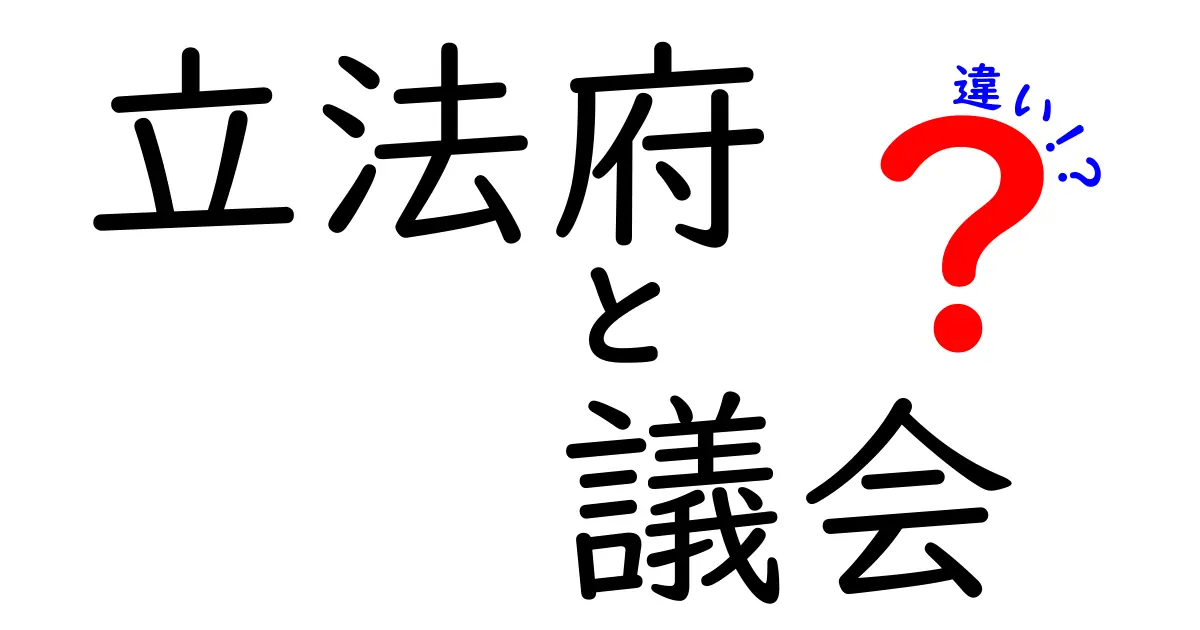

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
<みなさんは「立法府」と「議会」という言葉を聞いたことがありますか?日常生活であまり聞き慣れないかもしれませんが、政治の世界ではとても大切な言葉です。
この二つは似ているようで実は違う意味を持っています。今回は中学生でもわかるように、「立法府」と「議会」の違いについて詳しく解説します。
政治や社会の仕組みを知るきっかけにしてみてくださいね。
<
立法府とは何か?
<まずは立法府について説明します。
立法府とは、国の法律をつくる仕事をする機関のことです。日本では憲法により、国の権力を「三権分立」として司法・行政・立法に分けています。そのうちの一つが立法府です。
立法府は法律を作り、国のルールを決める役割を持っています。
また、立法府は憲法の中で「国会」として位置付けられています。つまり、日本の立法府は国会そのものを指します。
国会は国民の代表である議員から構成されており、国の政治を決める中心的な役割を担っています。法律を作るだけでなく、政治を監視したり、予算を決めたりする重要な機関です。
こちらは国全体の法律や政策を決める大きな枠組みとなっています。
<
議会とは何か?
<次に議会についてです。議会は立法府の一部というイメージですが、もっと広い意味で使われることもあります。
議会とは、住民や国民の代表が集まって話し合い、地域や国の決まりを決める集まりのことを指します。
日本には国の議会である国会のほかに、都道府県議会や市町村議会など、地方の議会も存在します。
つまり議会は立法府の中に含まれる機関の名前で、話し合いの場も意味します。
議会は法律の審議をしたり、予算や条例を決めたり、政治のチェックをしたりする仕事をします。国会も議会の一種ですが、議会という言葉は地方の政治の場にも使われています。
<
立法府と議会の違いを表で比較!
<| ポイント | <立法府 | <議会 | <
|---|---|---|
| 意味 | <法律を作る機関全体(国全体の立法機関) | <話し合いの場や代表者の集まり(国や地方の議会) | <
| 範囲 | <主に国のレベル(国会) | <国会だけでなく地方議会も含む | <
| 役割 | <法律の制定・政治の監視・予算決定など | <話し合い・法律や条例の審議・政治のチェック | <
| 例 | <国会(衆議院と参議院) | <国会や都道府県議会、市町村議会など | <





















