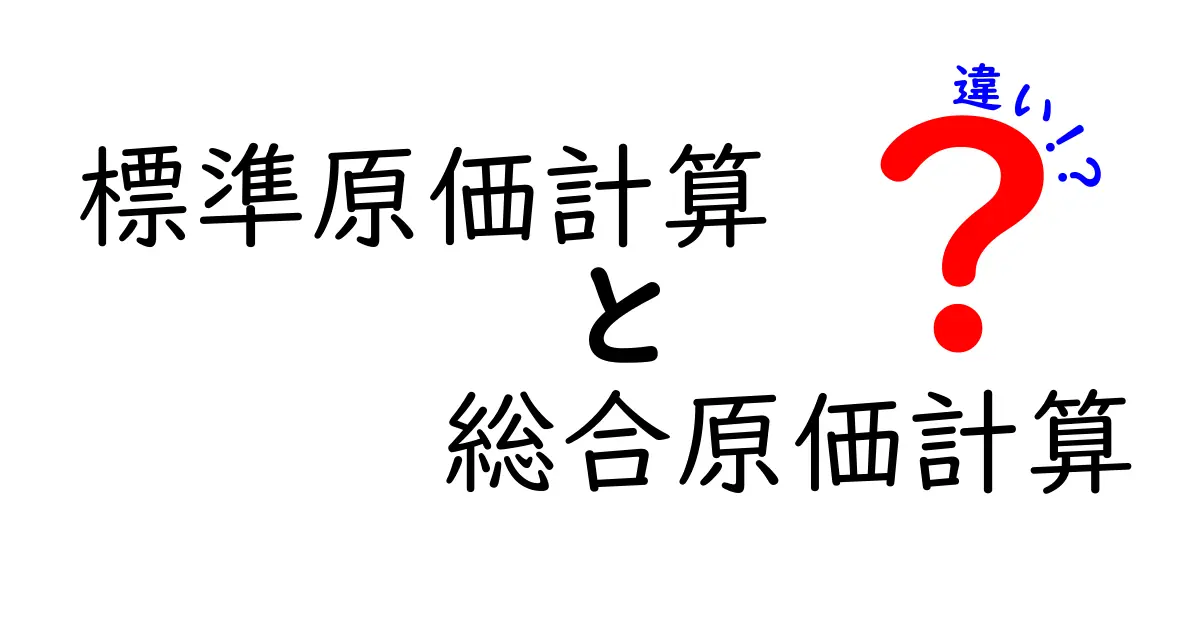

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
標準原価計算と総合原価計算の基本とは?
皆さんは「標準原価計算」と「総合原価計算」という言葉を聞いたことがありますか?
どちらも会社で使われる会計の方法の一つで、商品の原価(コスト)を計算するための仕組みです。
でも用途ややり方がかなり違うんですよ。
今回はこの二つの計算方法の特徴や違いについて、わかりやすく説明していきます。
まずは、それぞれの計算方法が何を目的にしているかを理解しましょう。
標準原価計算は、作る予定の製品にかかる費用をあらかじめ計算し、実際の費用と比べることで効率の良さをチェックします。
一方、総合原価計算は、複数の工程や大量の製品を一括して原価を計算する方法です。
この違いを押さえるだけで、どんな製品や業種でそれぞれが使われるかイメージしやすくなりますよ。
標準原価計算の特徴と使い方
標準原価計算は企業があらかじめ決めた標準的なコストを基に計算します。
たとえば、材料費や作業時間などについて「このくらいかかるはず」という基準値を作ります。
実際に作業が終わってからその標準値と比べることで、ムダや効率の悪さがわかります。
この方法は生産の効率改善やコスト管理に役立ちます。
また、部門ごとに原価を管理しやすく、改善策を立てやすいのも特徴です。
例をあげると、自動車メーカーなど、製品ごとに多くの部品を組み立てて作る業種でよく用いられています。
ポイント:
- 標準原価はあらかじめ設定した基準
- 実際の費用と比較して効率をチェック
- ムダを発見しやすい
総合原価計算の特徴と使い方
総合原価計算は、同じような製品を大量に作る時に用いる方法です。
たとえば、紙や飲み物、生産ラインでの部品など、一連の工程をまとめて原価を計算します。
この方法は細かく原価を分けにくい大量生産に向いています。
原料費や労務費などの費用を合計し、それを製品数で割ることで一つあたりのコストを出します。
大量で同じ商品を作る業種、たとえば食品工場や化学工場でよく使われる計算方法です。
ポイント:
- 大量同一製品の原価計算に便利
- 複数工程やまとめて計算する
- 個別コストが分かりにくい時に有効
標準原価計算と総合原価計算の違いを表で比較!
| ポイント | 標準原価計算 | 総合原価計算 |
|---|---|---|
| 目的 | あらかじめ決めた基準と実績を比べることで効率を改善 | 大量生産の製品の原価を一括して計算 |
| 適用範囲 | 製品ごと、部門ごとに細かく管理可能 | 似た製品や複数工程の合計原価の計算に向く |
| 計算方法 | あらかじめ決めた標準費用と実績費用を比較 | 全費用を合計し、生産量で割って単価を算出 |
| 利用業種例 | 自動車、機械製造業など | 食品工場、化学工場、紙製品など |
| 特徴 | 効率チェックやムダ発見に強い | 原価の全体把握に優れる |
このように標準原価計算は効率改善、総合原価計算は大量生産に適していることが違いのポイントです。
企業や業種によって、どちらの方法を使うか選ぶ基準となります。
ぜひ両者の特徴を理解して、将来のビジネス学習や仕事に役立ててくださいね!
標準原価計算について、よく考えると「標準」という言葉に秘密があります。
これは単に決められた数字ではなく、過去のデータや経験から計算されていることが多いんです。
まるでテストの目標点のように、みんなが目指す数字なんですね。
そして実際にかかった費用と比べて、「これだけずれてる!」と気づくことで、作り方のムダを見つけられるのが面白いところ。
なんだかゲームのスコア挑戦みたいじゃないですか?
この仕組みは企業のコスト意識をぐっと高める大切な役割を持っているんです。
だから標準原価計算は、ただの数字の計算以上に、会社の成長に欠かせないヒントを与えてくれる存在なんですね。





















