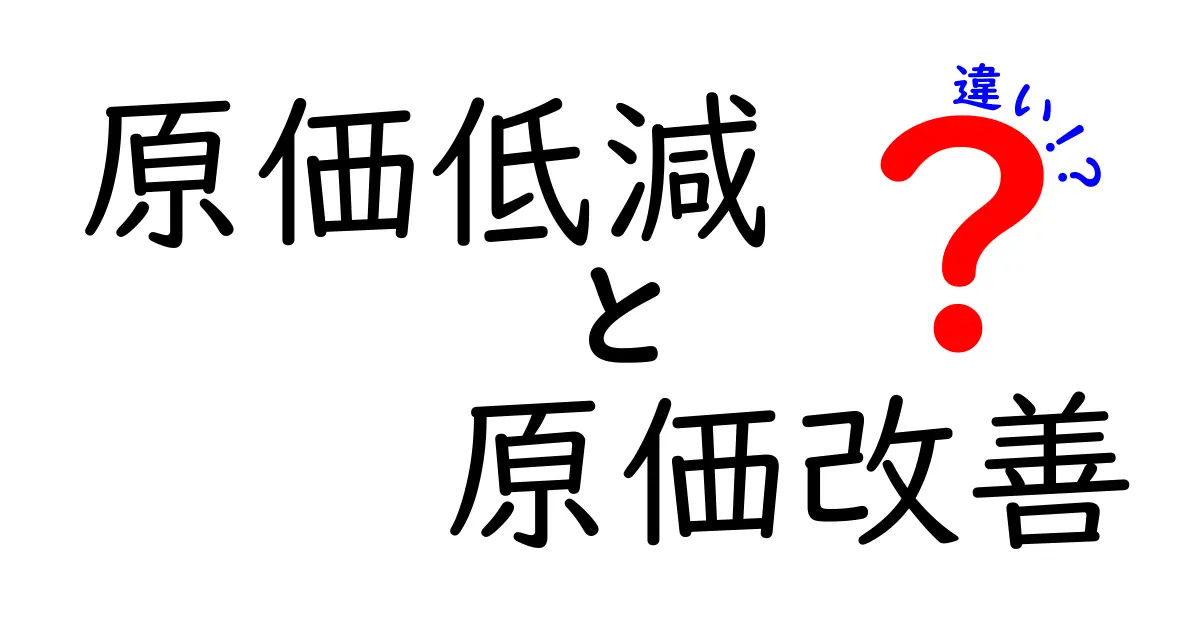

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
原価低減と原価改善の基本的な違いとは?
ビジネスの現場でよく耳にする「原価低減」と「原価改善」。
一見、似た言葉ですが、実は意味や目的に大きな違いがあります。原価低減は、製品やサービスのコストを減らすために、今ある費用を抑えることを指します。
たとえば材料費を安いものに変えたり、作業の工数を減らすなどが挙げられます。
一方、原価改善は、長期的な視点で製造やサービスの質を保ちつつ、効率よくコスト構造を見直す取り組みです。
単に安くするだけでなく、品質や生産性も考慮して全体最適を目指します。
このように原価低減は即効性を求めたコスト削減策、原価改善は継続的な経営努力による改善活動と覚えるとわかりやすいです。
どちらも会社の利益を増やすために重要ですが、目的ややり方、影響範囲が異なるため、誤解なく使い分けることが大切です。
原価低減と原価改善の具体的な方法と効果
具体的に原価低減では、原材料の見直しや仕入れ先の交渉、不要なコストの削減が中心です。
たとえば、安い材料に変えたり、数量割引を利用したり、外注から内製へ切り替えたりします。
しかし短期間で結果を出しやすい反面、品質低下や従業員の負担増につながるリスクもあります。
一方の原価改善は、工程の合理化や設備の更新、作業方法の標準化など長期的に続けやすい工夫が多いです。
これによりムダを削り、生産性の向上と品質維持を両立します。
たとえば、工程を分析して不要な作業を減らし、結果的に時間やコストを節約できるのが特徴です。
それぞれのメリットとデメリットは以下の表の通りです。
原価改善は、単なるコストカットではありません。例えば工場のラインを見直してムダな動きを減らすことも原価改善の一つです。
これは一見コストとは関係ないように見えますが、効率が上がり、人件費や時間の節約につながります。
だから原価改善は原価低減よりも深い意味があり、会社の成長につながる大事な取り組みなんです。
身近に例えると、勉強の時間配分を工夫して効率よく覚える方法を探すようなものですね。





















