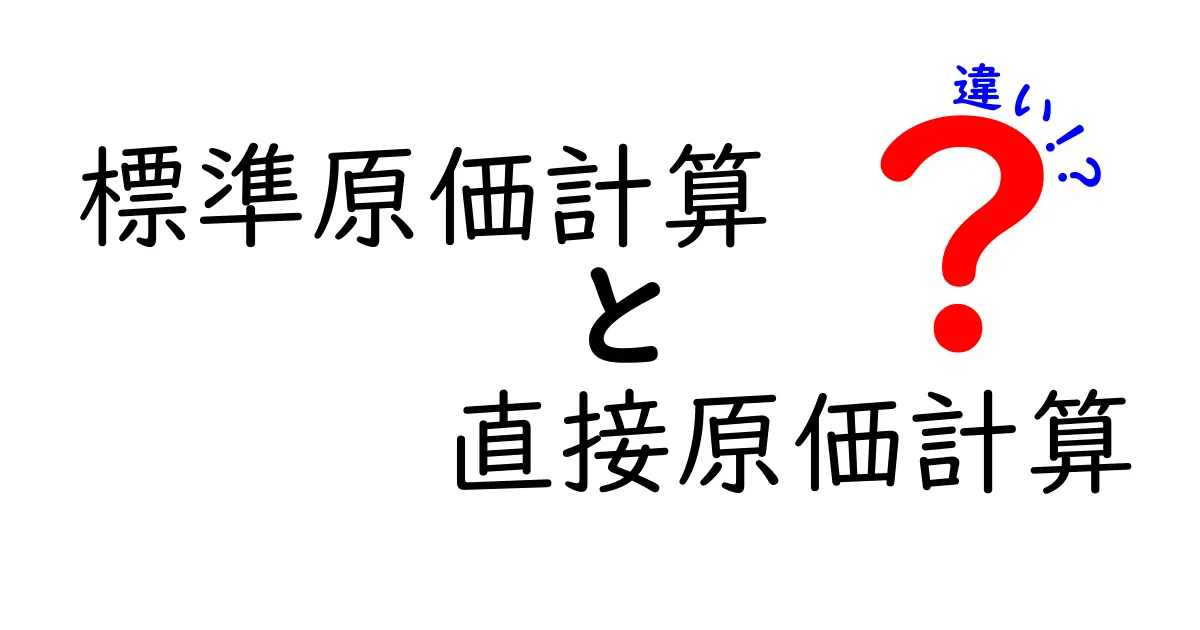

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
標準原価計算とは?
標準原価計算は、製品やサービスを作るための費用をあらかじめ決めておく方法です。
例えば、ある工場で一つの製品を作るのにどれくらいお金がかかるのか、材料費や人件費、機械の利用費などを平均的に計算して「標準の原価」を決めます。
この標準の原価と実際にかかった費用を比べることで、どこでお金の使い方が良かったのか、または無駄遣いがあったのかを調べることができます。
つまり、標準原価計算は「計画と実績の差を分析する」ための方法で、経営の効率をよくするために役立ちます。
この方法は、将来の費用も予測しやすくなり、会社の予算を立てやすくするメリットもあります。
しかし、計算が複雑になることや、実際と標準の違いに注意が必要なのもポイントです。
直接原価計算とは?
直接原価計算は、製品を作るために材料費や直接労務費など直接かかった費用だけを計算する方法です。
ここで言う「直接」とは、製品ひとつひとつに直接かかる費用のこと。
一方で、工場全体の電気代や建物の費用などは「間接費」といって、直接原価計算では費用に含めません。
この方法は、商品の利益をはっきりさせやすく、経営者が利益の変化をすぐに理解しやすいのが特徴です。
例えば、商品の売上が増えると、直接原価も比例して増えますが、固定費は変わらないので、利益の管理が簡単になります。
ただし、間接費を無視するため、会社全体の費用を正確には把握しにくいこともあります。
標準原価計算と直接原価計算の違いを比較表で解説
将来の予測に役立つ
経営のスピード判断に有効
計算が複雑
まとめ:どちらの方法を使うべき?
標準原価計算と直接原価計算は、それぞれ特徴が違います。
どちらの方法も会社の状況や目的に合わせて使い分けることが大切です。
もし長期的に原価の管理や改善をしっかり行いたいなら、標準原価計算が役に立ちます。
一方で、短期的に利益の変動をすぐ知りたい場合は、直接原価計算が分かりやすくおすすめです。
企業によっては両方を組み合わせて使うこともあります。
これらの違いを理解することは、経済やビジネスを学んでいくうえでとても役立つ知識ですよ。
ぜひ、原価計算を身近に感じて、ビジネスの世界に興味を持ってみてくださいね。
今回は「標準原価計算」について少し深掘りしてみましょう。
標準原価計算では、実際に使った費用と「標準」として決めた費用の差を分析します。
この差は「差異」と呼ばれ、良い差異ならコストが抑えられた、悪い差異なら無駄があったことになります。
この差異分析が、会社の経営を良くするヒントになるので、実はとても重要な作業なんですよ。
たとえば、ある工場で砂糖を使うお菓子作りで、標準の砂糖量より多く使ってしまうと材料費が増え「原材料差異」として経営に反映されます。
こうした細かい分析をすることで、無駄を減らせ、効率を高められるのです。
前の記事: « これでスッキリ!原価低減と原価改善の違いをわかりやすく解説





















