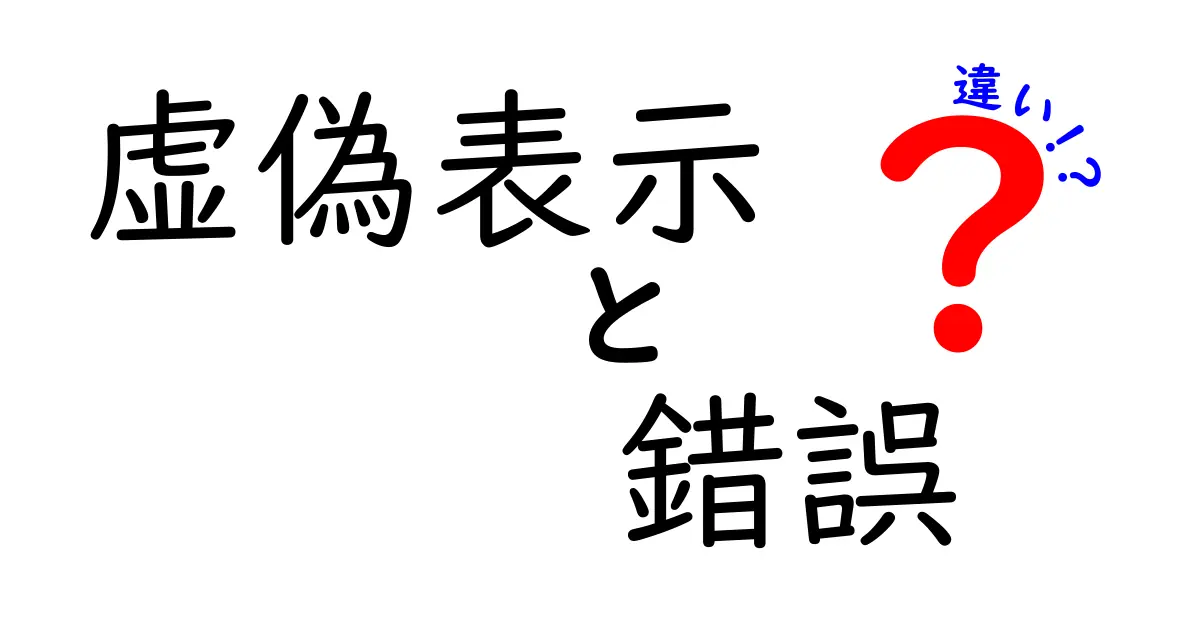

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
虚偽表示と錯誤の基本的な違いとは?
法律の世界には、似ているようで違う言葉がたくさんあります。虚偽表示と錯誤もその代表的な例です。どちらも取引や契約に関わる言葉ですが、意味や効果が違います。
虚偽表示とは、文字通り「偽りの表示」、つまり事実とは違うことをあえて言ったり示したりして、相手を誤解させる行為です。例えば、価値が低い商品を高価だと偽って売る場合がこれにあたります。
一方、錯誤とは自分が思い込んで間違った認識や理解に基づいて行動することです。間違いに気づかず契約した場合などがこれにあたります。重要なのは、虚偽表示は意図的に嘘をつくことであり、錯誤は本人の誤った認識や勘違いから起こる点です。
虚偽表示とは何か?
虚偽表示は、法律上の特別な意味を持つ言葉です。
簡単に言うと、「嘘の内容の意思表示」を指します。つまり、本当はそう思っていないのに、わざと間違ったことを伝えることです。
例えば、不動産の売買で建物の状態が悪いのに良い状態だと偽り説明した場合は虚偽表示になります。これは相手を騙そうとする行為で、法律上は原則として無効となることもあります。
また、虚偽表示は第三者が関与している場合や、社会の秩序を乱す場合に特に問題となります。
虚偽表示があった契約は取り消せる場合も多く、被害者を守るためのルールが法律で定められています。
錯誤とは何か?
錯誤は、自分の心の中の間違いが原因で生まれる問題です。
たとえば、売買で「これは純金の指輪だ」と誤信して購入したけれど、実際は金属の混ざった合金だった場合、買い手は錯誤に陥ったといえます。
錯誤は自分が誤って認識しているだけなので、悪意はありません。錯誤があった場合、契約を取り消すことができる場合がありますが、条件や程度によって違います。
法律では「意思表示の錯誤」という形で定められ、契約の有効・無効にも大きな影響を与えます。
虚偽表示と比べると、錯誤はもっと本人の心の問題に近いものと覚えておくとよいでしょう。
虚偽表示と錯誤の違いを比較した表
| ポイント | 虚偽表示 | 錯誤 |
|---|---|---|
| 意味 | 事実と違う内容をわざと表示すること | 本人が誤った認識や理解をしていること |
| 意図 | わざと嘘をつく(故意) | 本人は真実と思っている(過誤) |
| 相手への影響 | 相手を騙す可能性が高い | 相手は気付かないことが多い |
| 法律効果 | 原則として契約無効や取消しとなる | 一定の条件下で契約取消し可能 |
日常生活で注意したい虚偽表示と錯誤のポイント
日常生活でも虚偽表示や錯誤は起こりやすい問題です。
ネットショッピングやオークションでは、商品の説明が正確かどうか確認が重要です。悪意ある虚偽表示に騙されないようにしましょう。
自分が勘違いして契約したり買ったりするケースも錯誤です。たとえば、商品説明をよく読まなかったり、使い方を間違えたりすることが該当します。
どちらの場合も問題が起こったら冷静に事実確認し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
法律のルールを知っておけば、自分の権利を守りやすくなるので、最低限の知識を身につけておくことをおすすめします。
虚偽表示って聞くと、なんだか難しく感じますよね。でも実は、日常でもよくある話なんです。例えば、中古のゲームソフトを買ったら“新品同様”って書いてあったのに、実際は傷だらけだったら虚偽表示になっちゃいます。重要なのは“意図的”に嘘をつくこと。もし店がうっかり書き間違えたなら、虚偽表示とは言えません。でも、客側はその説明を信じて買うので、納得いかない時にはきちんと状況を話してみるといいですよ。法律って意外と私たちの生活に近いんですよね。
前の記事: « 窃盗罪と詐欺罪の違いとは?法律初心者でもわかる徹底解説





















