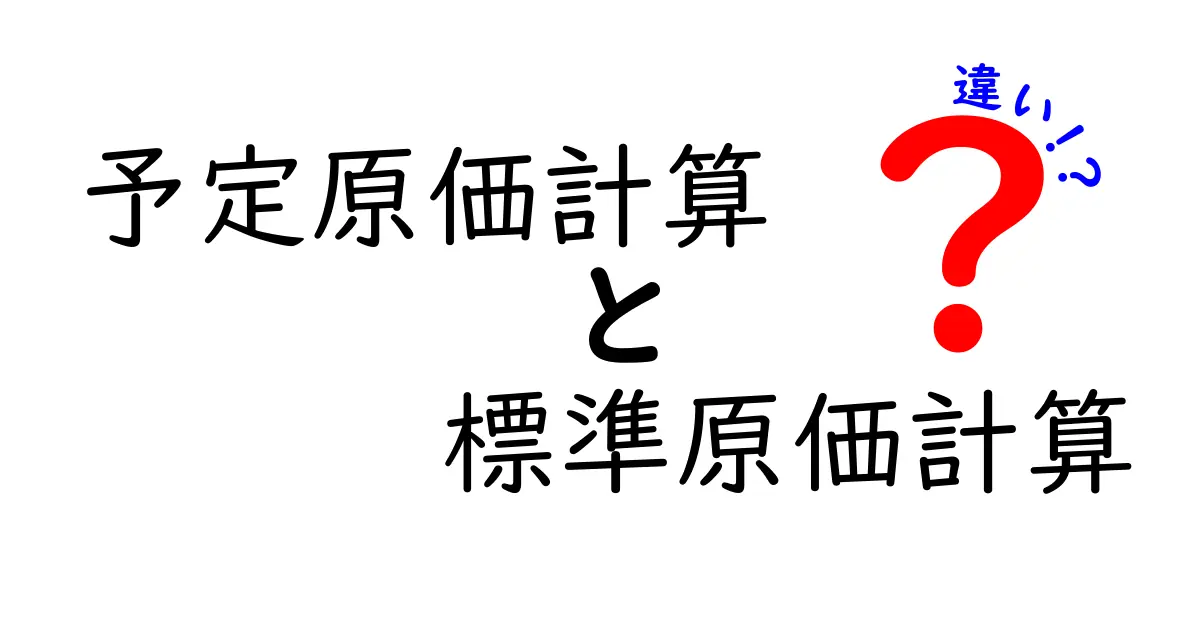

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
予定原価計算とは何か?基本をやさしく理解しよう
予定原価計算は、商品や製品を作るためにかかる原価を、あらかじめ計画して決めておく方法です。
たとえば、工場で1つの製品を作るのに材料費や人件費、機械の使用費などがかかります。この費用を未来のある時点で予想し、その予想した金額で経営や計画を立てるのが予定原価計算の役割です。
ポイントは「予定」の原価を使うこと、つまり実際にかかった費用ではなく、事前に決めた費用を使って計算する点にあります。
これによって、製造現場が計画通りに動いているかどうかを後からチェックできます。
予定原価計算は、企業が効率的に作業できているかを知るための大切なツールです。
また、計画段階でコストを予測しておくことで、製品の価格設定や利益の見込みを立てやすくなります。
標準原価計算とは?企業での活用方法と特徴を解説
標準原価計算は、商品の作成に必要な材料費や労務費、経費などをあらかじめ「標準的な水準」として決めておき、その標準を基に原価管理や費用の分析を行う方法です。
ここでの「標準」とは、効率よく作業したときにかかる費用の理想的な数値のことです。
例えば、1個の製品を作る標準時間が30分、標準的な材料費が500円と設定すると、実際の製造結果と比べてどれだけ計画通りかを判断します。
標準原価計算は計画だけでなく、企業の生産性や無駄を減らすための管理の道具として使われます。
異常があった場合には原因を掘り下げて改善に繋げることが可能です。
つまり、標準原価計算は予定原価をもとに、効果的な経営管理を目指す実践的な計算方法と言えます。
予定原価計算と標準原価計算の違いを表で比較!わかりやすく解説
| 項目 | 予定原価計算 | 標準原価計算 |
|---|---|---|
| 目的 | あらかじめ計画した原価を使ってコストや収益を予測する | 標準的な原価を設定し、生産管理や差異分析を行う |
| 原価の基準 | 過去の実績や技術、計画データを基にした予測値 | 効率的で正常な作業状態を想定した標準値 |
| 使用場面 | 経営計画や見積り段階 | 生産現場の管理やコストコントロール |
| 管理方法 | 実際の原価と比較し差異を評価 | 標準原価との差異分析で原因を探り改善へ活用 |
| 特徴 | 将来の費用を予想して計画に反映させる | 標準を使いながら生産効率を高めるための管理ツール |
まとめ:どちらも経営や製造で大切な原価計算の方法
予定原価計算と標準原価計算は、どちらも企業が製品を効率的に作りながら利益を出すために欠かせない原価計算の方法です。
予定原価計算は未来のコスト予測に役立ち、企業の計画作りを支えます。
一方、標準原価計算は具体的な作業効率の基準を設けて管理し、ムダを減らして利益を最大化するために利用されます。
両者を上手に使い分けることで、より良い経営判断ができるようになります。
原価管理に興味がある人やこれから学びたい人は、今回のポイントをしっかり押さえてくださいね。
標準原価計算の「標準」って、実は企業が理想とする生産効率やコスト水準を数字で表したものなんです。
たとえばスポーツなら「この選手が平均してどれだけ走るか」という基準があるように、商品づくりでも『これくらいの時間・材料費で作るのが普通』という基準を決めています。
この基準があることで、実際の作業が予定より効率的かどうか、ムダがあるかどうかをすぐにチェックできるんです。
だから標準原価計算は、ただの数字の計算じゃなくて、会社の仕事の質を上げるヒントがつまった仕組みと言えるでしょう。
次の記事: 一般管理費と製造間接費の違いとは?わかりやすく解説! »





















