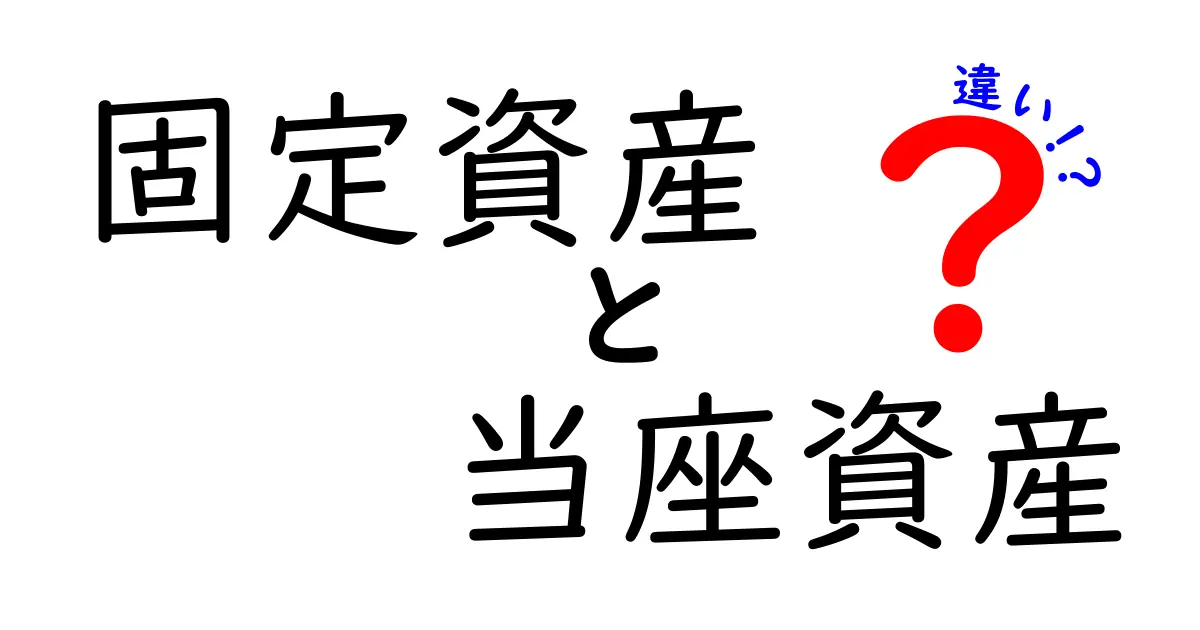

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
固定資産と当座資産の基本的な違いとは?
会計や経理の世界でよく出てくる言葉に「固定資産」と「当座資産」があります。どちらも会社の資産を表す言葉ですが、その意味や役割は大きく違います。
まず、固定資産とは、会社が長期間使うものを指します。例えば建物や土地、機械など、すぐに現金に変えられないものが該当します。これは通常、1年以上使われることが前提となっており、会社の事業に欠かせない資産です。
一方、当座資産は、すぐに現金化できる資産を指します。現金や銀行の普通預金、売掛金、株式などの短期間で流動性の高い資産が含まれます。これらは短期間で現金に変わるため、会社の日常の支払いなどで利用されます。
このように固定資産は長期間使うもの、当座資産はすぐに使えるものと覚えるとわかりやすいです。
固定資産の種類と特徴について
固定資産は主に有形固定資産と無形固定資産に分かれます。有形固定資産は目で見たり触ったりできる資産で、土地、建物、機械設備、車両などが含まれます。
無形固定資産は形はありませんが会社にとって重要な資産で、例えば特許権、商標権、ソフトウェアなどがあります。
固定資産の特徴は、購入した時の価値を何年間かに分けて費用にする「減価償却」が行われることです。これは長期間使う資産が徐々に古くなって価値が減るため、それを会計上で調整する仕組みです。
この減価償却の手続きは会社の資産管理や経費計上にとって重要で、固定資産がどんな種類でどれだけの価値があるのかを正確に把握することが求められます。
当座資産の種類と役割について
当座資産は会社の資産の中でも、短期間で現金に変えることができるものを指します。具体的には現金・預金、売掛金(お客さんからまだもらっていない代金)、有価証券などが含まれます。
これらは会社の日常の支払いに使われやすく、資金繰りの管理に欠かせません。
当座資産は流動性が高いので、会社の支払い能力を示す重要な指標になります。例えば、銀行からの借入を返済できるか、給料を払えるかなど、短期的な支払いに対応できるかを見るうえで重要です。
会社が安定して経営できているかどうかを判断するときに、この当座資産の量や質は重要なポイントになります。
固定資産と当座資産の違いを比較した表
まとめ:固定資産と当座資産を正しく理解しよう
今回ご紹介したように、固定資産と当座資産は会社の資産を2つに分けたもので、それぞれ役割や特徴が異なります。固定資産は会社が長期的に事業を続けるための大切な資産であり、減価償却を通じて徐々に価値を費用に振り分けます。
一方、当座資産は日々の支払いに使える現金やすぐに現金化できる資産で、会社の資金繰りを支えるものです。
これら両方を正しく理解し管理することが、会社経営や会計の基本です。もし将来、簿記や経理の勉強をするなら、まずは固定資産と当座資産の違いをしっかり押さえておきましょう。
売掛金(うりかけきん)という言葉、聞いたことありますか?これはお客さんからまだもらっていない代金のことを指します。たとえば、お店が商品を売ったとき、現金ですぐにもらうのではなく、あとで振り込んでもらう約束をしている場合、その代金は「売掛金」として計上されます。
面白いのは、売掛金は当座資産の一部ですが、実際にお金が入るまでには時間がかかることがあるため、会社にとってはちょっとドキドキの存在。借りたお金ではないのに、早く入金してもらえないか気になってしまうんです。だから、会社は売掛金の管理をとても大切にしています。





















