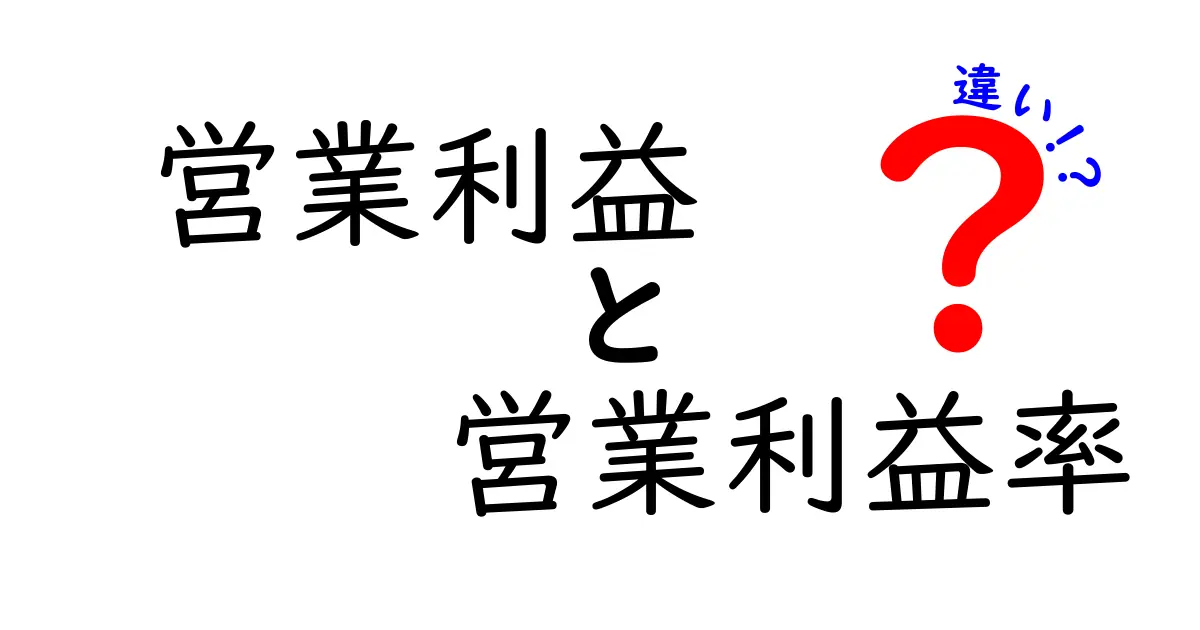

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
営業利益とは何か?
営業利益とは、会社の本業で得られた利益のことを指します。たとえば、お店が商品を売ったり、サービスを提供したりして得た売上から、その売上にかかった費用を引いたものが営業利益です。
売上高-売上原価-販売費及び一般管理費=営業利益
つまり、会社が実際に商品やサービスを販売した活動からどれだけ儲けたかを示す数字です。
この営業利益が高いほど、その会社の本業が順調に収益を上げていると理解できます。多くの経営者や投資家が重視する数字です。
わかりやすく言うと、お店が売った商品の売上から、その商品の仕入れ代金や販売にかかった人件費、広告費を引いた後に残るお金というイメージです。何か特別な収入や費用(例えば利子や税金)はここには含まれていません。
そのため、営業利益は会社の営業活動の成果をきちんと表す指標になっています。
営業利益率とは?
次に営業利益率について解説します。
営業利益率=(営業利益÷売上高)×100
営業利益率は、売上に対してどれだけ効率よく利益を出しているかを示す割合です。
たとえば、売上が1,000万円で営業利益が100万円の場合、営業利益率は10%になります。これは売上の中から10%が利益として残っている状態です。
この数字が大きいほど、無駄なコストが少なく効率よく利益を生んでいる会社といえます。逆に営業利益率が小さい場合は、売上はあってもコストや費用が大きいため、利益が少なくなっていることになります。
営業利益率は、業種や会社の規模によっても大きく異なるため、同じ業界内の会社同士の比較に使うことが多いです。
わかりやすく言うと、どれだけ売上から利益を残せているかの「効率」を表している数字です。売上が多くても利益率が低いと、その会社の収益はあまりよくないかもしれません。
営業利益と営業利益率の違いと使い分け方
ここまでで説明したように、営業利益は利益の絶対額、営業利益率は利益を売上に対して割合で表したものです。
営業利益だけを見ると「100万円稼いでいるから良い」と思いがちですが、大きい会社なら100万円の利益はあまり大きくないかもしれません。その一方で小さな会社が100万円の営業利益を出すのはすごいことかもしれません。
そこで割合の営業利益率を見て効率の良さや収益性を判断します。
たとえば2つの会社を比べるとき、営業利益が同じでも売上高が違えば営業利益率は変わります。営業利益率が高い会社の方が売上に対して利益を多く残していて効率が良いとわかります。
このように、営業利益は利益の絶対的な大きさを示し、営業利益率は利益の効率を表すため、ビジネスの状況を総合的に判断するために両方の数字を見ることが重要です。
営業利益と営業利益率の違いを表にまとめると
| 項目 | 説明 | ポイント |
|---|---|---|
| 営業利益 | 会社の本業で稼いだ利益の絶対額 | 会社の利益の大きさを示す |
| 営業利益率 | 売上に対して利益がどれだけ残るかの割合(%) | 利益の効率や収益性を示す |
いかがでしたでしょうか?
営業利益と営業利益率は似ているようで異なるものです。
会社の利益を理解する際には、単に利益の額だけでなく、利益率にも注目してみると、よりバランスのとれた判断ができるでしょう。
営業利益や営業利益率をしっかり理解して、数字の見方を身につけることで、経営判断や投資選びがぐっとわかりやすくなりますよ。
営業利益率についてもっと深く考えてみましょう。利益率が高ければ効率がいい、とはよく言われますが、実は営業利益率が高すぎる場合も注意が必要です。
例えば、無理に価格を下げて売上をきざみに増やす戦略を続けると、利益率は低くなります。逆に利益率が高い会社は高い価格設定やコスト管理が上手なことが多いんですが、あまり利益率を重視しすぎると売上そのものが伸びにくくなることもあります。
つまり、利益率は数字だけ見るより、その裏にある経営戦略や業界の特性を理解するともっと面白いんです。利益率が低くてもスケールで勝負する会社もありますから、一概に数字だけで判断せずに、会社のビジネスモデルを想像してみるといいですよ。





















