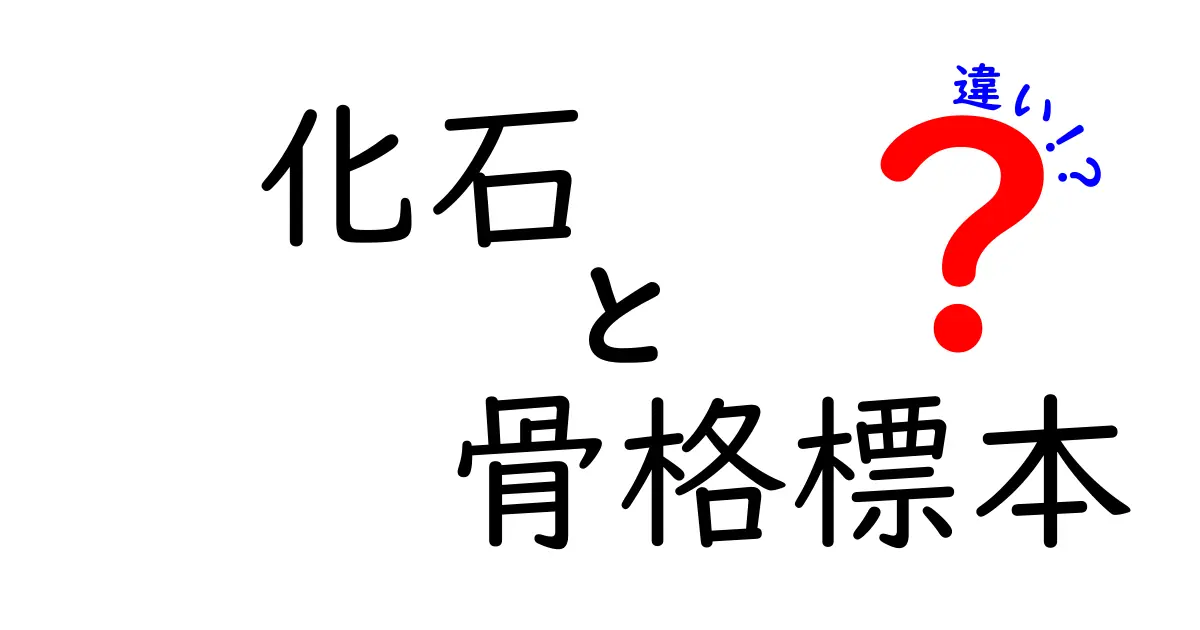

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
化石とは何か?
みなさんは「化石」という言葉をよく聞きますよね。化石とは、長い年月をかけて地面の下でできた昔の生き物や植物の遺跡のようなものです。たとえば、恐竜の骨や古い植物の葉の形が石になったものが化石です。化石は自然の力でできるため、そのままの形ではなく、石のように硬くなっています。
化石ができるには、まず生き物が亡くなり、その遺体が水や泥に埋もれます。空気に触れないため腐らず、何万年、何百万年という時間の中で周りの土や鉱物と一緒に固まっていきます。これが化石です。
つまり、化石は自然にできた生物の痕跡と言えます。
骨格標本とは何か?
一方、骨格標本は人や研究者が生き物の骨をきれいにして組み立てたものです。たとえば博物館にある恐竜の骨の模型や、動物の骨を並べて作ったものが骨格標本です。
骨格標本は自然ではなく誰かが作るものなので、骨を洗ったり壊れた骨を直したり、組み立てて形を整えます。
また、骨格標本は標本として研究や学習に使われます。実際の骨を使うこともあれば、プラスチックなどでできた模型もあります。
つまり、骨格標本は人の手で完成させた骨の見本のことです。
化石と骨格標本の主な違いまとめ
では、化石と骨格標本の違いを表にまとめてみましょう。





















