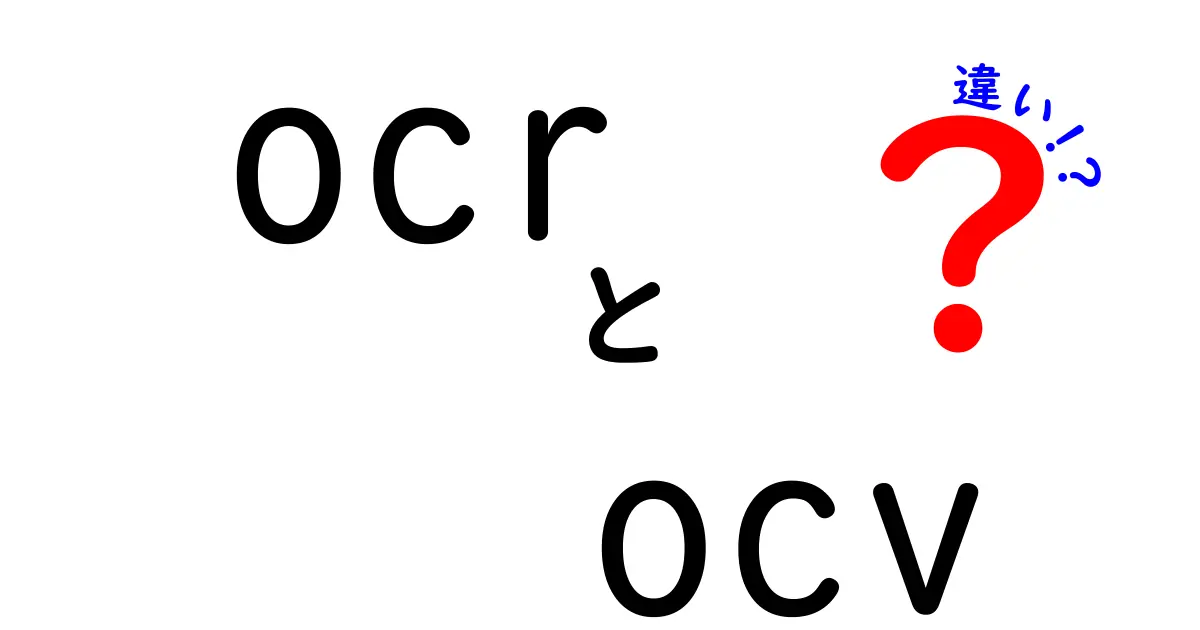

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
OCRとOCVの違いを知る前提
OCRは写真やスキャンした文書の文字を機械が認識して文字データに変える技術です。入力は画像、出力は文字列で、検索やデータ化に使われます。OCR単独で完結するケースもありますが、現場では前処理と後処理が大事です。ここで登場するのがOCVことOpenCVという画像処理ライブラリです。OCVはノイズ除去、二値化、傾き補正、対比調整といった作業を高速に行えます。つまりOCRは「何を読むか」、OCVは「どう読む環境を整えるか」という役割分担になります。実際にはOCRを使う前にOCVで画像を整え、認識を安定させるのが基本の流れです。斜めの文字、薄い文字、手書き風の文字、影・光沢のある紙などはOCRだけだと誤認識が増えます。そこでOCVの処理を入れると、認識率がぐんと上がることが多いです。OCRとOCVは別々の道具ですが、組み合わせると力を発揮します。これを理解しておくと、どの段階で何をするべきかがはっきり見えてきます。
"
実際の使い分け方と注意点
このセクションでは現場での使い分け方を具体的に見ていきます。OCRは文字認識の中心的機能であり、紙の文書をデジタル文字に変換する目的に特化しています。エンジンの違いとしてTesseractやEasyOCRなどがあり、用途ごとに適切に選ぶと良い結果が得られます。前処理と後処理を工夫することが精度のカギです。前処理としてはOCVを使ってノイズ除去、二値化、コントラスト強化、傾き補正を施します。OCRの出力は時に誤字だらけになりますが、後処理でスペル補正や言語モデルを活用することで正確性を高められます。OCVはこうした前処理を可能にする土台です。両方を組み合わせると、読みづらい文字がある紙でも文字を拾えるようになります。以下の表に要点を整理します。
実務ではOCRエンジンの選択も重要です。日本語対応の精度はエンジンごとに差があり、フォント、紙質、照明、言語設定が影響します。前提をそろえることで結果は安定し、修正作業も減ります。最後に、ライセンスとコストにも注意してください。オープンソースのOCRは無料ですが、商用利用時にはライセンス条件を必ず確認しましょう。
ねえ、OCRって実際どう動くの?と友だちに聞かれた時、私はこう答えます。OCRは写真やスキャンした紙の文字を、コンピューターが読むことができる文字列に変える仕組みなんだ。まず画像を見やすく整え、ノイズを減らして読みやすくするのが前処理。次に文字の特徴をモデルに伝えて、1文字ずつ「A」「B」のように識別するのが認識の段階。最後に結果を人間が使いやすい形に整えるのが後処理。OpenCVと呼ばれる画像処理ライブラリはこの前処理を手助けしてくれる。つまりOCRだけで完結するのではなく、OCVの力で読みにくい文字を読みやすくしてからOCRに投げるのが現実的なんだ。もしOCRの精度がいまいちなら、前処理を見直したり、別のOCRエンジンを試してみたりすると新しい発見がある。





















