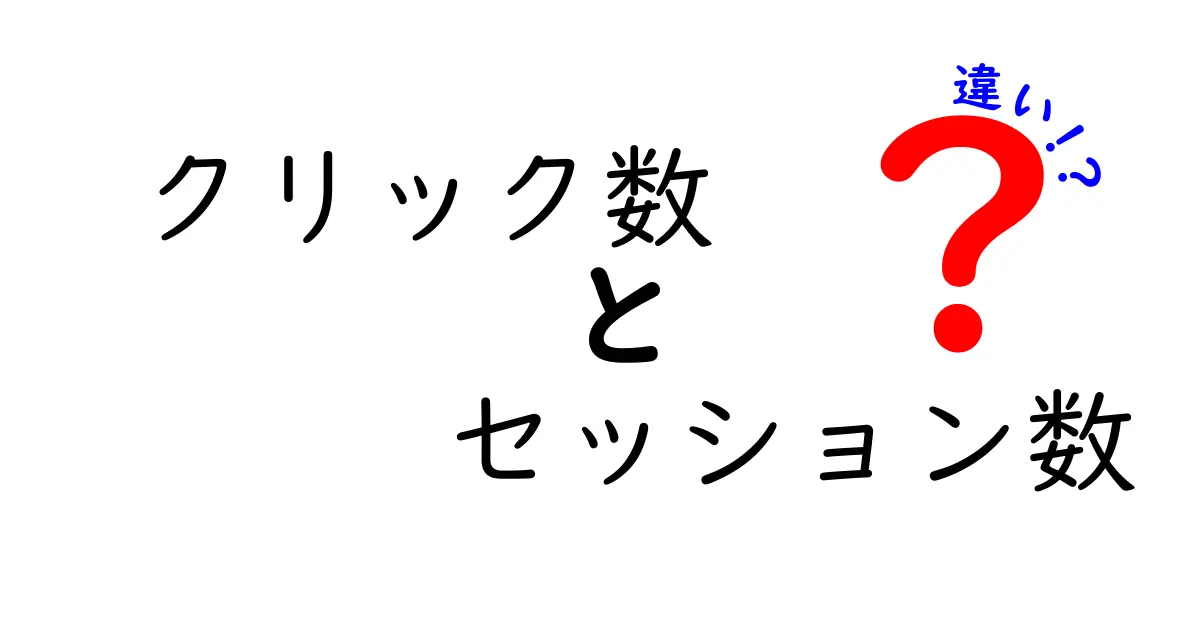

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
クリック数とセッション数の違いを理解するための基本
この二つの指標はウェブサイトのパフォーマンスを測るうえで頻繁に登場します。クリック数はリンクやボタンが押された回数をそのまま数える指標であり、同じユーザーが何度クリックしても回数は積み上がります。一方でセッション数はあるユーザーがサイトに訪れてから一定時間内に発生した一連の行動を一つの区切りとしてカウントします。たとえば同じ人が別のページへ移動しても、30分間の無操作が続くと新しいセッションとして扱われることが多いです。これらの違いを押さえると、データの読み方が格段に変わります。
実務ではクリック数はCTAの魅力や誘導の強さを測る指標として有効ですが、サイト全体の健康状態を判断するにはセッション数やバウンス率、閲覧ページ数など他の指標と組み合わせる必要があります。
この記事ではまず基礎を固め、次に実務での使い分け方を具体的な例と図解で紹介します。
読者のあなたが知っておくべきポイントは以下の三つです。1つの指標だけで判断しないこと、2指標同士の関係性を理解すること、3目的に合わせて指標を選ぶこと。これらを意識するだけで分析の精度はぐっと上がります。
それでは個別の定義と使い方へ、詳しく見ていきましょう。
クリック数って何?
クリック数はクリックの総数を指す指標です。ウェブ上のリンクやボタンが押された回数をすべてカウントします。ポイントは同一ユーザーによる複数回のクリックも別々にカウントされることです。私たちがよく見るのは広告のクリック数やCTAのクリック数です。クリック数が多いからといって必ずしも売上や成約につながるとは限りません。なぜなら、クリック自体は興味の入り口にすぎず、その先の体験が良くなければ成果にはつながりにくいからです。
実務での使い方としては、CTAの最適化やリンク先の誘導の強さを評価する指標として活用します。例えばボタンの色や文言を変えたときにクリック数がどう変化するかを比較する実験(A/Bテスト)を行うことが多いです。
ただしクリック数だけを見てはいけません。高すぎるクリック数は混雑や誤クリックの可能性を含むため、他の指標と併せて判断することが重要です。
セッション数って何?
セッション数は一連の訪問行動を一つのまとまりとして数える指標です。通常は一定時間内の無操作を境に新しいセッションが始まります。たとえば30分間操作がない場合には次の訪問を新しいセッションとしてカウントします。セッションにはページビュー、イベント、スクロール、検索などその訪問中の全ての活動が含まれ、同一の訪問で複数ページを閲覧しても一つのセッションとして扱われます。
この指標の強みは、訪問者がサイト内でどれだけ継続的に関与しているかを把握できる点です。セッション数が増えるときはサイト内のナビゲーションがうまく機能している、またはコンテンツが魅力的で回遊が促されている可能性が高いと考えられます。反対にセッション数が増えず、しかも滞在時間が短い場合は、離脱の原因を探る必要があります。
セッション数を正しく解釈するには、閲覧ページ数や平均セッション時間、直帰率と組み合わせて見ることが大切です。
まとめるとセッション数は訪問の質と量の両方を示す総合的な指標であり、サイトの使い勝手やコンテンツの価値を評価する上で欠かせないデータです。
違いを実務でどう使うか
クリック数とセッション数は補い合う関係にあります。クリック数だけを追うと、たとえば広告費の過剰投資につながるリスクがあります。一方セッション数だけを見ると、訪問者がどのページから入ってどのページまで回遊しているかの細かな動きが分からず、改善点を特定しづらいことがあります。そこで両者を組み合わせて分析します。具体的には、CTAのクリック数を増やしつつ、セッションあたりのページ閲覧数を上げることを目指します。これには以下の実践が有効です。
- 入口ページのクリック率と離脱率を同時に監視する
- ボトルネックとなるページを特定し改善する
- セッション数が増えたときの滞在時間や直帰率の変化を確認する
以下の表は実務での使い分けの目安です。
ポイントは箇条書きで整理します。
・クリック数は誘導力の強さを測る指標
・セッション数は訪問の質と量の両方を測る指標
・両者を同時に監視して改善の優先順位をつける
友だちの健太と放課後のデジタル広告話。健太はクリック数が多いと嬉しそうだけど、僕はいつも「クリックだけじゃ本当に大事なのか分からないよ」と返します。実はクリック数は話の導入に過ぎず、そこから先の体験が大事。話を深掘りすると、セッション数は訪問者がサイト内でどれだけ回遊しているかを教えてくれる重要なヒントになります。ある日、健太が「クリック数を増やす施策を試したい」と言いましたが、僕はこう答えました。"クリックを増やすことよりも、訪問者が長くいる理由を作ることが成否を分ける"と。二人でその日から、クリックとセッションの関係性を意識した改善を地道に続けることにしました。
次の記事: OCRとOCVの違いを徹底比較!初心者にも分かる使い分けガイド »





















