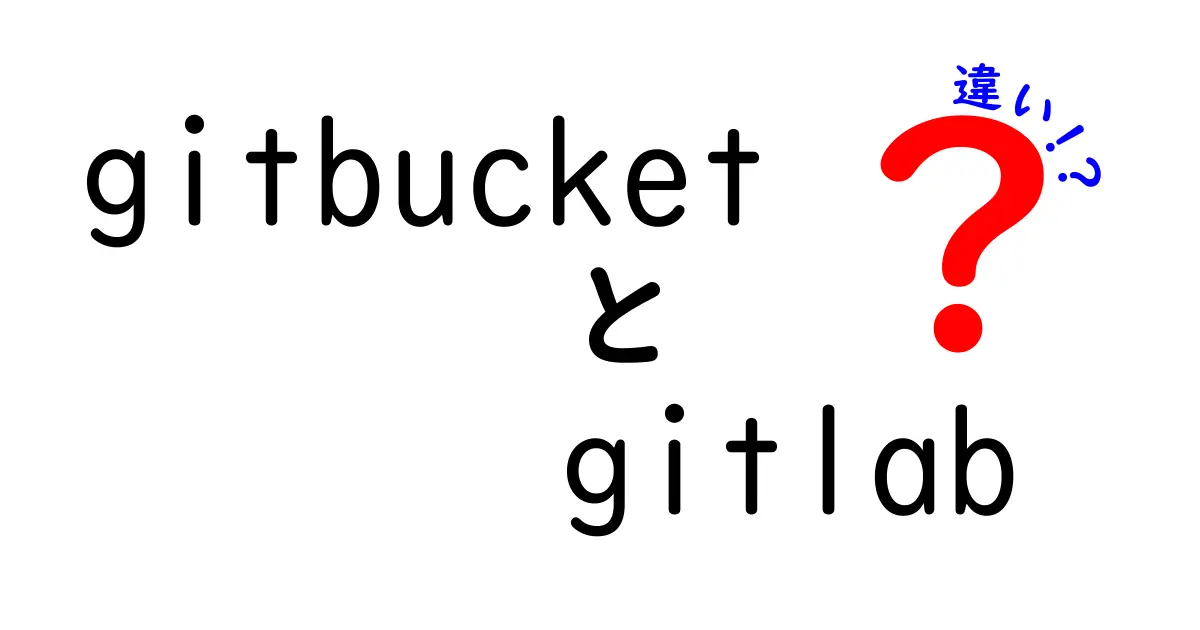

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:GitBucketとGitLabの違いを理解する理由
GitBucketとGitLabは、どちらもソフトウェア開発で使われる「Gitリポジトリの管理ツール」です。目的は似ていますが、設計思想や現場での使い方には大きな違いが生まれやすいです。まず大事な点は、自己ホスティングの可否、CI/CDの統合、そして機能の範囲です。
GitLabは「1つのプラットフォームでリポジトリ管理と開発の全プロセスを完結させる」ことを目指しており、CI/CDの内蔵・自動化・監視機能などが初めから組み込まれています。これにより、開発チームは別のツールを探して組み合わせる手間を減らせます。一方、GitBucketは比較的シンプルなリポジトリ管理を中心に設計されており、リポジトリの閲覧・コードの差分確認・プルリクエストの基本機能を高い安定性で提供します。CI/CDや高度なワークフローを求める場合には、外部のCIサービスと組み合わせる選択肢が自然と出てきます。結果として、使う場面や規模感によって最適な選択が変わるのです。なお、どちらを選ぶにしても自己ホスティングの可否、セキュリティの設定、バックアップの計画といった運用の基礎は変わりません。これらの観点を最初に整理しておくと、後から後悔が少なくなります。
この先のセクションでは、具体的な機能差と選び方のコツを、実際の運用を想定して丁寧に比較していきます。
1つ目の大きな違い:ホスティングとライセンス
最初に押さえるべき点は ホスティング形態とライセンスの取り扱いです。GitLabはクラウド版と自己ホスティング版の両方を提供しており、企業規模の導入に適した機能セットを用意しています。CI/CDが組み込まれており、パイプラインの設定はUIとYAMLベースの両方で行えます。
一方、GitBucketはリポジトリ管理を核にしたシンプルな設計で、自己ホストも可能ですが、CI/CDは基本的には外部ツールと連携する形が多いです。これは“外部ツール連携の自由度”にもつながり、あなたの現場で既に使っているCIサービスをそのまま利用できる利点があります。ライセンス面ではGitLabが複数のエディションを提供しているのに対し、GitBucketはオープンソースの利点を活かして透明性の高い運用を実現しやすい点が特徴です。導入コストと運用の透明性を重視する組織には特に影響が大きく、ここをどう選ぶかが長期の運用負担を左右します。
2つ目の大きな違い:機能の範囲とCI/CDの使い勝手
次に重要なのは、機能の範囲と使い勝手の差です。GitLabはプロジェクト管理、課題追跡、マージリクエスト、CI/CD、監視・分析など、多くの機能を1つのプラットフォームで提供します。これにより、開発者はツールを横断して情報を探す手間が減り、意思決定の速度が上がる場合があります。対してGitBucketは、主にコードのリポジトリ管理を安定させることに集中しており、複雑なパイプラインや大規模なCI/CDワークフローを必要とする場合には外部連携が前提になることが多いです。ここで覚えておきたいのは、「必要な機能を1つの画面で完結させたいか、それとも小さな部品を組み合わせて最適化するか」という観点です。運用の手間、学習コスト、サポート体制、セキュリティのガバナンスなど、その他の要素も同時に検討してみましょう。
この差を理解することで、あなたのチームに最適な選択肢を絞り込みやすくなります。
実践的な比較と使い分けのコツ
実際の現場では、“規模感と運用リソース”が最も大事な判断材料になります。小さなプロジェクトや学習目的ならGitBucketのシンプルさが強みです。導入が早く、基本機能の安定性が高いため、初学者がGitの運用に慣れるには最適です。一方で、企業規模の開発や長期的な運用を考えるならGitLabが堅実です。統合されたCI/CD、課題追跡、コード品質の監視などが一元管理できる点は強力な武器になります。
ただし、GitLabはフル機能を使いこなすには学習負荷が高い一方で、外部ツールとの連携を減らせるメリットも大きいです。実際には、以下のような選択パターンが現実的です。
1) すぐに試したい場合 → GitBucketを選んで、基本機能と自己ホスティングの運用を体験
2) 最低限の自動化で済ませたいが将来的に拡張したい場合 → GitLabのCommunityエディションを導入して徐々にCI/CDを組む
3) 全体最適を狙う組織 → 最初からGitLabを導入して、開発プロセスを統合的に管理する。
このような観点から、自分たちの開発規模・人材・予算・セキュリティ方針を地道に棚卸ししてから選択を進めると、後悔は少なくなります。
まとめと次のステップ
最終的な選択は、実際の運用環境で試してみるのが一番です。
小規模で学習目的ならGitBucketのシンプルさと自己ホスティングの自由度が魅力です。逆に、組織全体の開発を一元管理したい場合はGitLabの統合機能が強力な武器になります。
まずは「どの程度の自動化が必要か」「既存ツールとの相性はどうか」「セキュリティポリシーはどの程度厳格か」を判断基準に設定しましょう。期間を決めて両方をお試しするのもおすすめです。
これらを踏まえると、後から後悔することなく、現場に最適なツールを選べるはずです。
ねえ、CI/CDって知ってる?GitLabには最初からパイプラインが組み込まれていて、ビルド・テスト・デプロイを自動化できるんだ。GitBucketは基本のリポジトリ機能に専念していて、CI/CDは外部ツールと組み合わせるのが普通。つまりカスタムの自由度と運用の手間のバランスをどう取るかが決定的。小さなプロジェクトならGitBucketのシンプルさが助けになるし、大きな開発ならGitLabの統合機能が時間を生む。結局は、チームの規模と現実的な作業量のマッチングが大事だと感じるね。





















