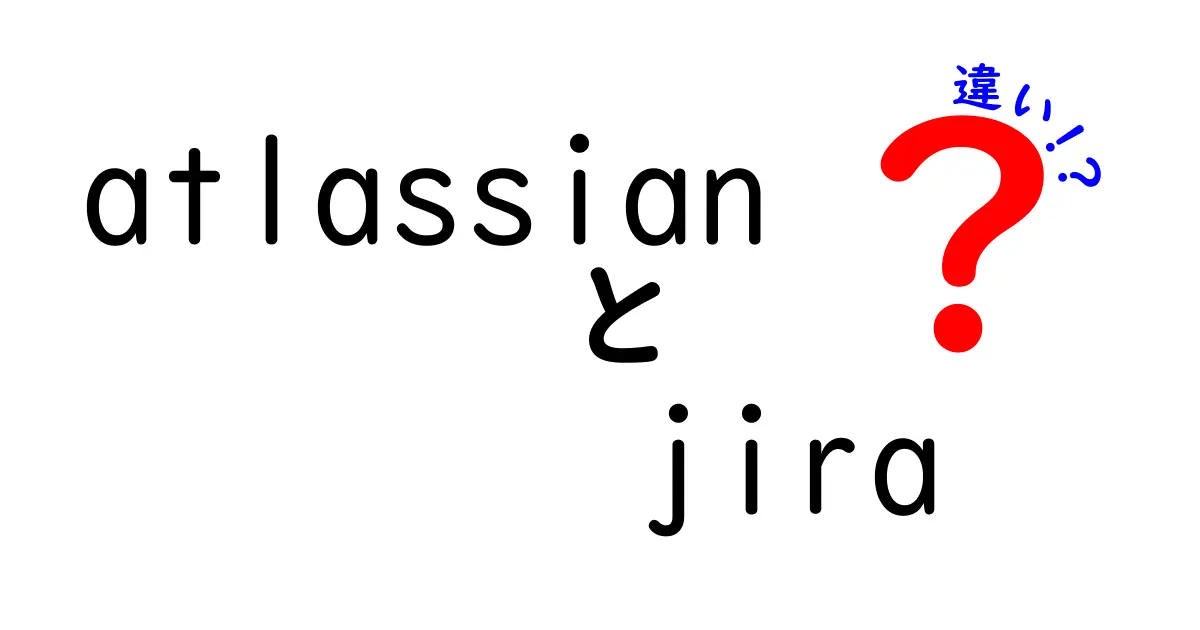

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
atlassian jira 違いを徹底解説:基礎から使い分けまで
この文章では「atlassian」と「jira」の違いを紐解き、どう使い分ければよいのかを中学生にも分かるように丁寧に説明します。
まずは大前提を確認しましょう。
Atlassianはソフトウェア開発や業務プロセスを改善するための世界的な会社名です。
この会社が提供する製品の中でJiraは最も有名なタスク管理ツールの一つであり、開発チームだけでなくビジネス部門にも広く使われています。
ではAtlassianとJiraはどう違うのでしょうか。結論から言えば、Atlassianは企業名、Jiraはその会社が作った製品の総称です。
この差を混同すると、どの機能が自分の目的に合うのかが分かりづらくなります。ここから先で具体的な違いを3つの観点で見ていきましょう。
観点1:企業名と製品名の違いを正しく理解する
まず最初に覚えておきたいのは「Atlassianは会社名で、Jiraはその会社が提供している製品の総称」という点です。ここを間違えると、導入検討の場で誰が責任を取るべきか、どの製品を導入すべきかがわからなくなります。
Atlassianは複数のソフトウェアを開発しており、その中にはタスク管理以外のツールも含まれています。
そのため、企業の組織形態や業務フローによっては「Jira以外の製品を選ぶべきケース」も出てきます。この区別を正しく認識しておくことが、後々のコスト削減と運用の安定化につながります。
またJiraという名前自体にも複数のエディションが存在し、それぞれの用途が微妙に異なることを理解しておくと、導入時の質問に対しても明確な答えが出せます。
観点2:Jira の派生製品と用途の違い
Jiraには大きく分けていくつかのエディションがあります。代表的なのはJira Software、Jira Core、Jira Service Managementです。これらは同じ“Jira”という名前を共有しますが、想定されるユーザーや目的が異なります。
Jira Softwareは開発チーム向けで、アジャイルボードやスプリント管理、課題追跡機能が充実しています。
Jira Coreはビジネス部門向けで、タスク管理やプロジェクト進行の可視化を主目的としています。
Jira Service ManagementはITサービス管理(ITSM)向けで、サービスポータル、インシデント管理、変更管理といった機能を備えています。
このように同じJiraでも用途に応じて適切なエディションを選ぶことが重要です。
以下の表は各エディションの主な対象と用途を簡単に比較しています。製品名 対象 主な用途 Jira Software 開発チーム アジャイル管理、タスク追跡、リリース計画 Jira Core ビジネス部門 プロジェクト管理、業務タスクの整理と可視化 Jira Service Management IT部門、サポート部門 ITSM、サービスポータル、インシデント管理
この表を見れば、同じJiraという名前の下でも“どのエディションを選ぶべきか”が直感的にわかります。
また、組織が成長して業務が複雑になるほど、複数のエディションを組み合わせて利用するケースも多いです。例えば開発部門はJira Softwareを使い、IT部門はJira Service Managementを使うといった形です。これにより、部門ごとに最適な機能を使い分けつつ、全社としての進捗管理も統一されたプラットフォームのもとで行えます。
観点3:実務での使い分けと導入のコツ
実務での使い分けにはいくつかのコツがあります。まず第一に「目的の明確化」です。何のためにJiraを導入するのか、開発なのかITSMなのか、あるいは雑務の一元化なのかを最初に決めることが肝心です。次に「部門間の連携ルールを決める」こと。部門ごとに使い方が異なる場合、共通のルールがないと情報が断絶します。
また「標準テンプレートと運用ガイドを用意する」ことも効果的です。新入社員が入ってきても、すぐに同じやり方で作業を開始できるようにするため、初期設定から運用までの手順を文書化しておくと良いでしょう。最後に「評価と改善のサイクルを回す」こと。機能は日々進化します。定期的に使い方を見直し、不要なワークフローを削除したり新機能を取り入れたりすることで、運用コストを抑えつつ効果を最大化できます。
このように導入時にしっかり目的を定め、部門間で連携ルールと運用ガイドを共有することが、プロジェクト管理の効率化と成功につながります。
ねえ、Jiraについて少し深掘りしてみよう。Jiraは一つの“ツール名”だと思っている人が多いかもしれないけれど、実はJiraという名の製品がいくつかあって、それぞれ向き合う現場が違うんだ。たとえば開発チームにはJira Software、ITサポートにはJira Service Management、そしてビジネス部門にはJira Coreがぴったり。名前は同じでも用途が違うから、導入前に“どの現場をどう支えるか”をはっきり決めると失敗が減るよ。最近は部門間で同じデータベースを使いながら、ボードの見せ方だけを変える運用も増えてきている。つまりJiraをうまく使えば、全体の進捗が見える化され、会議の時間を短縮できる可能性が高いんだ。だからこそ、まずは自分のチームの「何を達成したいのか」を考えることから始めよう。





















