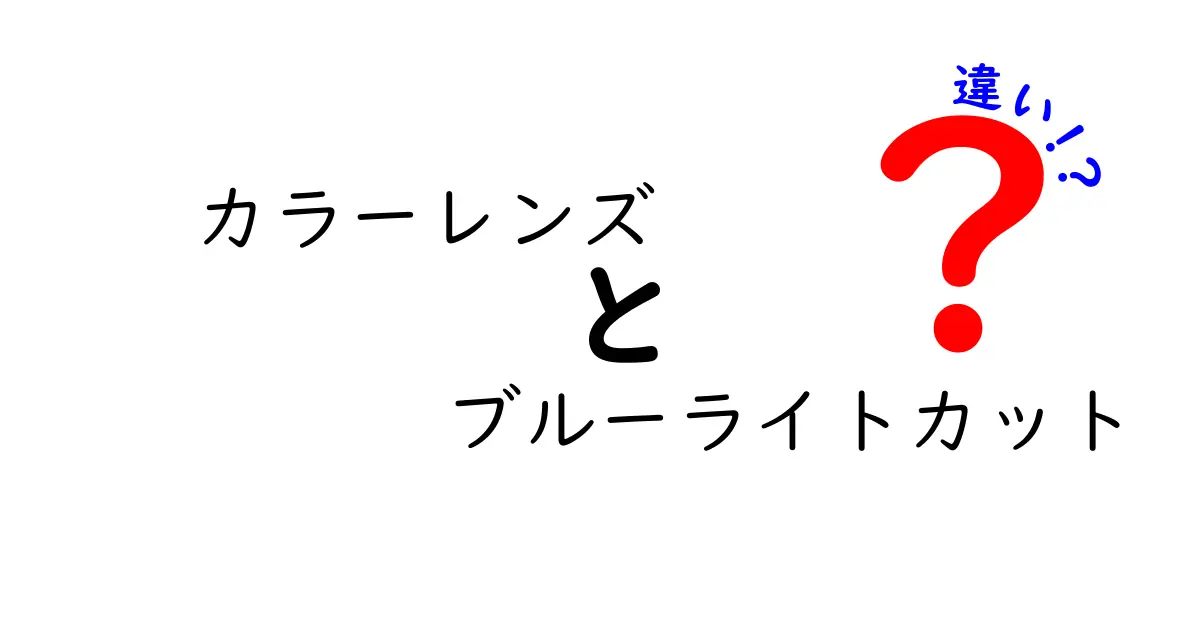

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
カラーレンズとブルーライトカットの違いを理解するための基本
現代の眼鏡市場でよく目にするカラーレンズは、見た目の色だけでなく視界の感じ方を変える目的で使われます。
ブルーライトカットは、スマホやパソコン、テレビなどの液晶画面から出る青い光を軽減する機能です。
ただし「カラーレンズ」と「ブルーライトカット機能」は別の概念であり、同じものを指すわけではありません。
二つの違いを理解しておくと、日常生活での目の疲れを減らす選択がしやすくなります。
まず大切なのは、カラーレンズは基本的に見え方の演出や偏光・コントラストの調整を目的とする製品であるのに対して、ブルーライトカットは主にデジタル機器の長時間使用による目の疲労を緩和する機能である、という点です。
さらに、実際には「色がつく」ことと「青色光を減らす機能」は別の技術であり、組み合わせても使える場合があります。
この章では、それぞれの特徴と使い分けの目安を、身の回りの場面と照らし合わせながら丁寧に解説します。
ブルーライトカット機能の仕組みを知ろう
ブルーライトカット機能を選ぶときは、どの程度の光をカットするのか、実際に自分の視界に影響を与えるのかを見極めることが大事です。
多くのレンズにはブルーライトカットと可視光透過率の表示がありますが、数字だけを見て決めるのは危険です。
数字はメーカーごとに基準が異なるため、実際の体感が大切です。
長時間デスクワークをする人には画面の反射を抑えるタイプが楽になります。
ただし、目の保護は個人差が大きく、過度な期待をしないことも重要です。
効果は睡眠の質改善や頭痛の軽減として感じられることが多いですが、それが全てではありません。
またノンハードコートのレンズは傷つきやすく耐久性が低くなる場合があるので、用途に応じたケアが必要です。
結局のところ、デジタル機器の使用時間の管理と、適切なレンズ選択、そして眠る前の光の扱いを見直すことが、実際の快適さにつながります。
友だちとスマホの話をしていると、ブルーライトカットの話題で盛り上がります。彼は「ブルーライトカットは本当に目に効くの?」と疑問に思っていて、私は「それぞれの生活スタイルで効果の感じ方が違う」と返す。私は夜遅くまで勉強するときにブルーライトカットのメガネをかけると目が疲れにくいと感じました。けれど、睡眠の質を変えるには光の色だけではなく、就寝前のスマホ習慣を見直すことも必要です。つまり、ブルーライトカットは道具の一つであり、生活習慣の改善と組み合わせて初めて力を発揮します。
次の記事: 視角と視野角の違いを徹底解説!中学生にもわかる図解つきガイド »





















