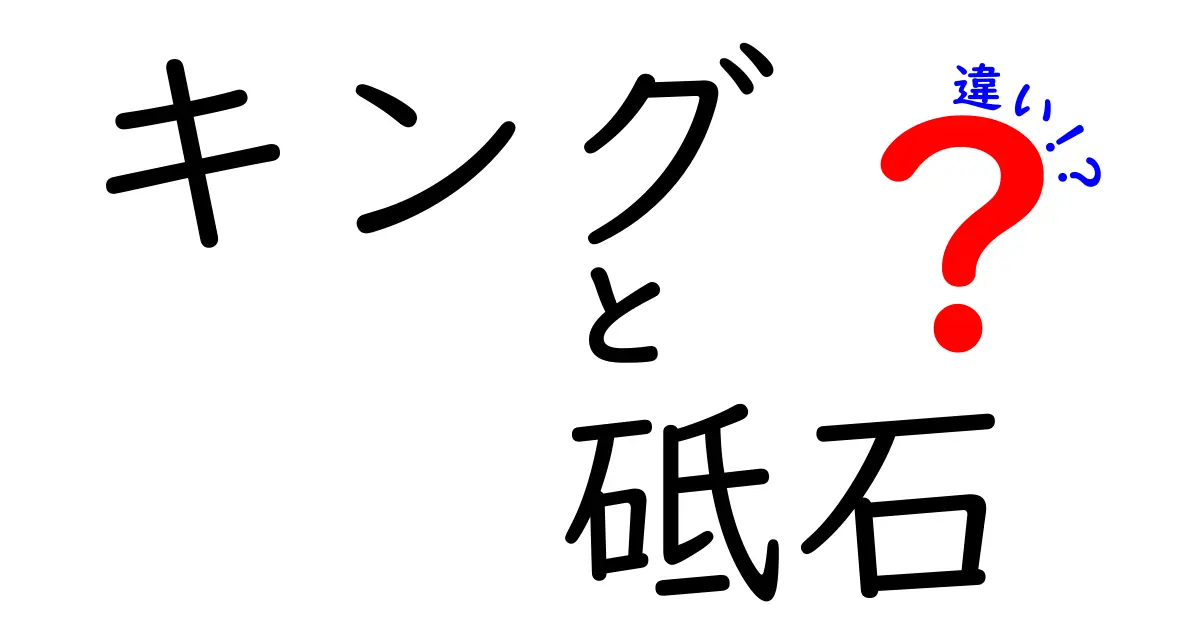

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
キング 砥石 違いを徹底解説!初心者にも分かる特徴と選び方
本記事は、包丁や刃物を研ぐときに使うキング砥石の“違い”を、初めての人にも分かるように解説します。キングは日本を代表する砥石ブランドの一つで、木工・料理の現場で長く信頼されてきました。砥石には粗さ(粒度)や硬さ、材質の違いがあり、それが“どう削れるのか”“どんな仕上がりになるのか”を左右します。まず覚えておきたいのは、砥石の目的は“鋭さを作ること”と“刃を傷つけずに整えること”の2つです。荒く削るとダメージを直せることが多く、細かく整えると切れ味を長く保つことができます。キング砥石は、初心者が始めやすいセットが揃っていることが多く、価格帯も手ごろなものから上位モデルまで幅広く販売されています。
この違いを知ることで、道具を長く大切に使えるようになり、包丁の切れ味を安定させることができます。ここからは、基本情報・種類・選び方・使い方の順に、実践的なポイントをわかりやすく整理します。
キング砥石とは何か?基本情報
キング砥石とは、 KING のブランドが提供する水砥石の総称です。刃を研ぐときは水を使い、砥石の目が出てくるとともに刃が滑らかに整います。キングの砥石には、細目から中目、粗目まで幅広いラインナップがあります。粗さは「荒さ」と読み、数字が小さいほど細かい粒子、大きいほど粗く削れます。初心者には #1000 から始めるのが一般的です。さらに、硬さは、水を含んだときの反応に表れ、硬い砥石は砥ぎ味が安定しやすく、柔らかい砥石は目詰まりに注意が必要です。キング砥石の特徴として、表面の仕上げや、均一な研ぎ出し感、またコストパフォーマンスの良さが挙げられます。実際の選択では、最初に粗さを揃え、次に中目・仕上げと順番に揃えるのが基本です。 King の砥石は、セットで揃えると使い勝手が良く、研ぎの工程を理解しやすくなります。水を使う利点として、熱を持ちにくく、刃の微細な傷を抑えやすい点が挙げられます。
使い始めのときは、砥石の表面を水で十分に湿らせ、滑らかな研ぎ心地を得られるようにしましょう。
キング砥石の種類と違いを知ろう
キング砥石には、荒目・中目・仕上げ目などのグリットサイズの違いだけでなく、素材の違い(人工砥石、天然砥石)も存在します。人工砥石は安定した研ぎ味を提供し、初心者にも扱いやすいことが多いです。天然砥石は個体差があるため、日によって仕上がりが変わることがありますが、個性的な研ぎ味を楽しむ人もいます。以下の表は、キングシリーズの代表的な品番と粗さの目安をまとめたものです。 このような違いを理解すると、どの砥石を日常のどの目的に使うべきかが見えてきます。さらに、刃物の種類(ステンレス、鋼、セラミック)によって最適な砥石の選択が変わるため、実際に手に触れる機会を作って感触を確かめることが重要です。荒削りには粗目を、整えには中目・仕上げ目を組み合わせるのが基本パターンです。「自分の包丁にはこの組み合わせが合う」という感覚を少しずつ覚えることが、長い目でみると一番の近道になります。 砥石を選ぶときは、まず自分が何を研ぎたいのかをはっきりさせることが大事です。以下のポイントを押さえておくと、失敗が減ります。 最後に、選ぶときは実店舗で実際に手にとって感触を確かめるのが一番です。自分の手の感覚に合うかどうかを重視してください。オンライン購入の場合は、返品ポリシーとセット内容をよく確認し、初期不良の懸念を減らしましょう。 正しい使い方とメンテナンスを知ると、砥石の寿命が伸び、刃物の切れ味も安定します。砥石を使う前には必ず水に浸し、砥ぎ始めの1、2分は水分を十分に含ませます。研ぎ始めの角度はおおよそ15〜20度を目安にすると、刃の根本まで均一に削れ、刃先の細かいカーブにも対応できます。 雑談風の小ネタ記事です。ある日の放課後、友だちとキング砥石の話をしていたとき、彼がこう言いました。『粗さって、コーヒーの粒みたいなものだよね。粗い粒は勢いよく削る力をくれるけど、結局はどう使うかが勝負だよ』。僕はそれを聞いて、砥石の粗さもコーヒーの濃さみたいに“使い分ける楽しさ”があると感じました。実際には、日常の包丁には粗さ#1000〜#3000を中間に置き、仕上げには#6000以上を使うのがセオリーです。友人は、砥石を選ぶときに「自分の手の感覚に合うかどうか」を一番大事にしていると言います。私はその言葉を胸に、家で砥石をいじる時間を大切にしています。粗さの違いを理解することが、道具との対話を豊かにし、料理の質を少しずつ上げていく近道だと気づいたのです。品番 KH-100 粗さ #1000 用途 日常の包丁の整え 特徴 安定感が高い 材質 人工砥石 価格帯 中程度 選ぶときのポイントと注意点
使い方とメンテナンスのコツ
研いだ後は、砥石の表面を滑らかに保つために、裏面まで水で洗い流し、乾燥させます。水を使うときのコツは、必ず冷たい水で研ぐこと、熱を持つと砥石の効きが落ちるため注意が必要です。砥石を平らに保つためには、平面出し用の軽石(フラットナー)を定期的に使うことが大切です。面が歪むと、刃が一方向に偏ってしまい、仕上がりも不安定になります。日々の小さなケアが、長期的には大きな差を生みます。
科学の人気記事
新着記事
科学の関連記事





















