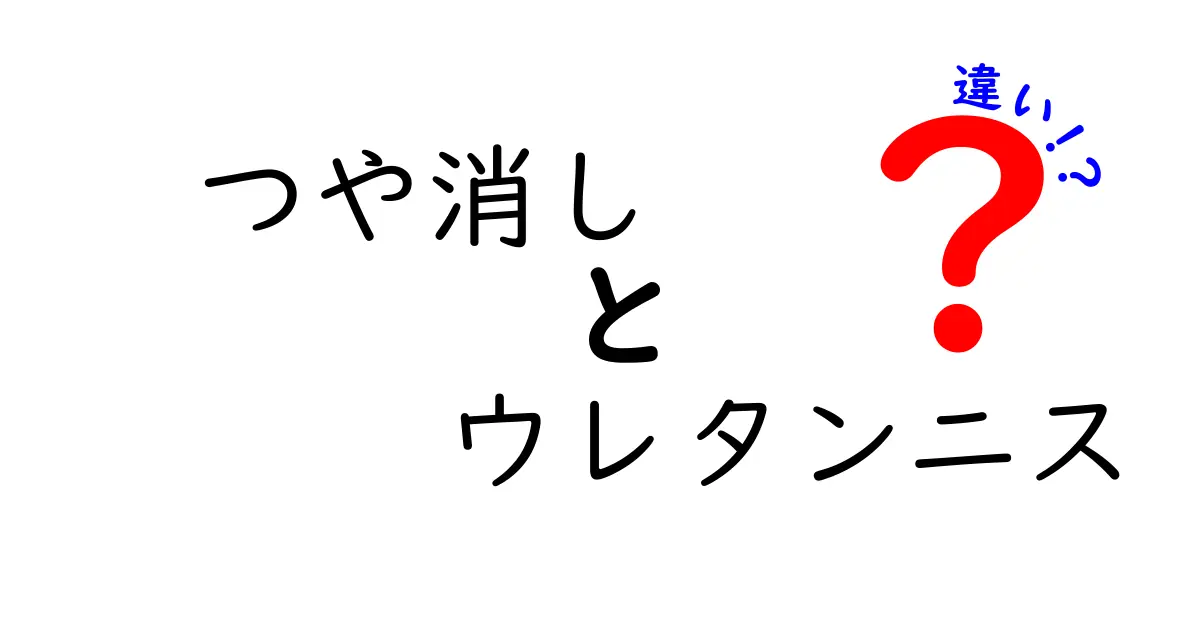

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
つや消しとウレタンニスの違いを知る基本
つや消しとは、表面の光沢を抑え、光の反射を少なくする仕上げの総称です。用途や塗装材料の組み合わせにより、非常にマットに見えるものから半光沢程度まで幅があります。つや消しの実体は「膜の表面を平滑にするだけでなく、光を乱反射させる微細な凹凸を残す」ことです。これにより、木材の木目がやわらかく見え、傷の目立ちにくさも向上します。
一方、ウレタンニスは主にウレタン樹脂を成分とする透明の保護膜材で、光沢を自由に調整できるのが特徴です。ウレタンニスの膜厚が厚くなると、鏡のような光沢からマット寄りの仕上げまで選べます。耐摩耗性や耐水性、傷つきにくさを高めるための添加剤が入っていることが多く、実用性が高い点が魅力です。
この両者の決定的な違いは「見た目と耐久性のバランス」をどう取るかです。つや消しは視覚的な落ち着きを重視する場面に向き、ウレタンニスは実用性、長期間の保護を重視する場面に向きます。塗装現場では、下地処理の平滑さ、塗布方法、乾燥条件、筆記の道具選びなどの要素も絡み、仕上がりは大きく変わります。
以下の表は、基本的な特徴の比較を簡単に整理したものです。表を見れば、光泽の程度、耐久性、用途の指向性などがひと目で分かります。なお、実際にはブランドや製品ごとに差があるため、購入前にサンプルで確認することをおすすめします。
用途別の使い分けと実践テクニック
木製家具の仕上げを例にとると、落ち着いた雰囲気を出したい場合にはつや消しが適します。木目を強調しすぎず、表面の傷が目立ちにくくなるのが利点です。特にカラーの濃淡がはっきりした木材では、つや消しが美しく映えます。
逆に高級感や清潔感を演出したい時にはウレタンニスを選ぶと良いでしょう。膜厚を厚くして光沢を出すと、家具の面の固さと滑らかさが強調され、光の反射が美しく映えます。屋内の家具や床、またはキッチンの棚など、日常の使用頻度が高い場所では耐摩耗性と耐水性の高いウレタンニスが向いています。
塗布方法にもポイントがあります。刷毛塗りとスプレー塗装のどちらを選ぶかで膜形成の仕方が変わります。刷毛は自分の手の動きで厚みを調整しやすく、細かな凹凸を均すことができます。スプレーは膜を均一に広げやすく、しぶきの飛散を抑えやすい反面、塗布の回数と乾燥時間を管理する必要があります。いずれも換気と温度・湿度の管理を徹底してください。
実践的なコツとして、下地が木目である場合は、目止め剤を薄く塗ってから仕上げ材をかけると、木目の美しさを失わず、均一な膜厚を作りやすくなります。仕上げ前の下地研磨は#320〜#400程度の細かさで十分です。最後の仕上げには、表面を軽く拭いて塵を取り、乾燥後に軽いサンドで微細な傷を整えると、長期間美しい状態を保てます。
この章の最後に、実践的な注意点を整理します。有害溶剤の換気、作業着の保護、乾燥時間の遵守、そして尺度の記録を習慣化してください。適切な管理があれば、つや消しとウレタンニスの両方を安全かつ美しく活用できます。
下地処理と塗布条件を最適化するための追加ヒントとして、ボンドの種類や下地の吸収性にも注意を払うことが大切です。下地の吸い込みが強い場合は、クリアな下地材を先に薄く塗布して固定した後、本塗りへ移行するのが良い方法です。こうした細かな点が、仕上がりの美しさと耐久性を長く保つコツになります。
実践的なコツとよくある質問
家具の塗装でよくある質問として「つや消しは傷が目立ちやすい?」という問いがあります。答えは用途次第で、「傷の目立ちにくさ」は膜の硬さと表面の滑りの組み合わせ次第です。つや消しは傷が目立ちにくいことが多いですが、鋭利な傷には目立つことがあります。ウレタンニスは耐久性が高く傷つきにくいことが多い一方、光沢が出すぎると傷の形がくっきり見えることがあります。
また、メンテナンスとしては、密閉性の高いボトルで保存し、開封後はなるべく早く使い切ること、不要な混合を避けることが肝心です。結論としては、仕上がりのイメージと用途の要件を最初に決め、試し塗りを3〜4回程度行い、乾燥・硬化の過程を観察してから本番に進むのが安全で効率的です。
最後に、現場の実践として、天候が悪い日には膜厚が均一になりにくいことがあります。その場合は、室温を安定させ、換気を十分に確保して、湿度が高すぎない時間帯を選んで作業を進めてください。これらの注意点を守ることで、つや消しとウレタンニスの両方を、目的に合わせて最大限活用できます。
友達と雑談で塗装の話をすることが多い僕の“小ネタ”を紹介します。つや消しとウレタンニスの違いをただ説明するだけではつまらないので、実際の現場の雰囲気を交えた会話風に深掘りします。つや消しは光の反射を抑え、木目をやさしく見せる魔法のような仕上げ。でも傷や汚れを気にする場面では、ウレタンニスの方が固く丈夫で扱いやすい。だから実際には、部屋の雰囲気、使う場所、手入れの頻度を考慮して選ぶのがコツです。測定や乾燥時間の話題も自然と会話に入ります。こうした雑談は、子どもにも伝わりやすく、失敗を避ける第一歩になるのです。
次の記事: サテンとポリッシュの違いを徹底解説!見分け方と使い分けのポイント »





















